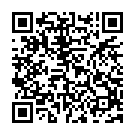学校長より
洲本高等学校 学校長
越田 佳孝
|
 |
4月1日。洲本高校定時制では四人の方が転出し、新たに四人の方をお迎えしました。新しい年度のはじめ、職員会議で学校のミッションとビジョンについて話しました。
新しい年度のはじめにあたって学校のビジョンについて話をします。「どういう生徒を育てるか」という話です。「どういう生徒を育てるか」を明確にするためには、今、現在、教育に課せられているミッション(使命)を理解しなければなりません。社会からの期待、地域からの期待、そして保護者からの期待、それぞれレベルは違いますが、それらのミッション、期待に応えるのが公教育の勤めであり、洲本高校の義務なのです。
昨年の9月にみなさんに「教育のミッションと洲本高校」と題してお話ししました。その話です。教育のミッション(現在の教育課題)は二つあります。
(1) 格差の連鎖を断つ ~子どもの格差問題~
一つは「子どもの貧困」です。これはもう社会問題と言ってもよいのです。平成26(2014)年には「子どもの貧困対策の推進に関する法律」が施行されました。教育には、資産格差、雇用格差、教育格差等から生じる貧困の連鎖を断ち、生まれ育った環境(経済的・文化的な環境)が、子どもの将来に与える影響を低く抑え、格差を低減させる役割が託されています。
(2) 社会の変化に対応する資質や能力の育成 ~21世紀型能力~
二つ目が、変化が激しく、予測の難しい社会で生き抜いていく「人財」を育成することです。内閣府の「人間力」(2003)、経済産業省の「社会人基礎力」(2006)、中教審第2次教育振興計画の「社会を生き抜く力」(2013)、国立教育政策研究所の「21世紀型能力」(2013)といわれている様々な「○○力」も同じ危機意識から発しています。これらは未知の問題に答えを見出す「思考力」、多様な価値観を持つ他者と協働して問題を解決する「実践力」を重視したものであり、今、学校は「どのように学ぶか」という学びの質や深まりが問われています。
現在、学校の教育は、学校だけで完結するものではありません。保護者や地域社会、そして関係機関との協力なくして成り立ちません。保護者や地域社会、関係機関の協力をえるためには、学校が行っている様々な教育活動について、私たちがしっかりと説明できるものを持っていなければなりません。説明責任ということです。説明責任を果たすためには、私たち自身が、今、自らの学校で、自らが行っている教育活動について説明できなければなりません。なぜなら教育は、意図的で、計画的な営みだからです。
説明責任をしっかり履行するためには、「何を行うのか?」だけではなく、「なぜ、それを行うのか?」も含めて、私たち自身が自分のものにしておかなければなりません。そのためには、学校の使命、存在意義を意味する「ミッション」と、「ミッション」達成のために学校が目指す姿・形を具体化した「ビジョン」、つまり「目指す学校像」「目指す生徒像」「目指す教師像」を常に意識化し、明確に説明していけることが必要になってきます。
まず、淡路島の唯一の定時制高校である洲本高校定時制に与えられたミッションです。本来、定時制は、「働く青少年に高校教育を保障するとともに、多くの有為な人材を育成する」という目的で設置されました。今年度、定時制はその発足以来、69年の歴史を刻んできました。もちろん社会環境の変化の中で、「働く青少年のために高校教育を」という設立当初の目的から、現在では、過年度卒業者や不登校経験生徒など多様な生徒を受け入れているのが現状です。しかし、設立以来変わらないものがあります。それは、生徒たちに社会人として必要な基礎学力を定着させ、卒業と同時に社会的自立を目指してきたということです。社会の変化に伴い、定時制教育が果たす役割も変化し、それに対応して私たちの教育実践も変化してきています。しかし、生徒たちに、社会で自立していく「力」をつけるという点は変えてはならないものです。
社会の変化に対応する、洲本高校定時制の取り組みのキーワードが「学び直し」です。洲本高校でいう「学び直し」には二つの意味があります。一つは、小学校・中学校で「学び残してきた部分」を、高校生としての発達段階をも配慮して、もう一度学ぶということです。あと一つは、何らかの理由で一度は高校を離れたけれども、やはり「高校で学びたい」「高校卒業の資格をとりたい」と考える人に、再び学ぶ機会を提供するという意味です。
大切なのは、この高校生としての発達段階にも配慮してというところです。いくら小学校・中学校で「学び残してきた部分」があるといっても、相手は高校生。生徒の学ぶ意欲を萎えさせないためにも、高校生としてのプライドにも配慮した指導が必要です。ここは、まさに専門職としての教師の力量が問われるところです。毎年、生活体験発表会の県大会出場者の原稿には、洲本高校定時制に出会うまで、自らの居場所、自分自身がしっくりとくる「学びの場」を求めて彷徨っていた小中学校時代の日々を、赤裸々に綴ってくれたものもあります。小中学校時代になかなか学校に行くことができなくて、やっと見つけた自分自身が落ち着いて学べる場、安心して友だちとつながることができる居場所、それが洲本高校定時制だったと語ってくれています。何らかの事情で小中学校時代学校に行くことができなかった人、一旦は高校を離れたけれども、やはり「学ぶこと」の大切さに目覚め、もう一度学びたいという人、そういう人にとって、洲本高校定時制は「学び直し」を保障する貴重な場であるわけです。そういう貴重な「学びの場」を提供することが、淡路島の唯一の定時制、洲本高校定時制に課せられたミッションなのです。
私は、生徒たちに、まず学校に来る、そして授業をしっかり受けて学ぶ、さらには学んだ「成果」をいかし自らの将来への道筋をつける、と機会ある毎に話し続けてきました。洲本高校定時制は、その魅力・特色を「できる」「わかる」「つながる」の三つのコンセプトで説明できます。まず、学校に来れば、小中学校の時に学び残してきたものを学び直すことができる。さらには、一旦は学校を離れてしまったが、もう一度学びたいと思う人は再び学び直すことができるのです。これが「できる」です。学校に来て授業を受ければ、少人数で丁寧な先生の指導により、授業内容がわかるようになります。また、ホームルーム活動等をつうじて友だちの気持ちもわかるようになります。これが「わかる」です。そして、体育祭、文化祭、ボランティア活動、生徒会活動等の様々な学校行事によって、友だち、先輩、先生、さらには地域の人たちとつながっていきます。そういう人たちとのつながることによって視野が広まり、意識が深まり、そのことで自らの将来に道筋がつき、自分の未来につながるのです。それが「つながる」です。こういう「できる」「わかる」「つながる」を三つのコンセプトとした教育活動を展開していくことが、「学び直し」という「ミッション」の達成のために、学校が目指す姿や形、教育内容を具体化した「ビジョン」です。
私は、高校で学ぶということは、三つの点で成長することだと思っています。一つは「知識が増える」ことです。英単語や数学の公式等これまで知らなかったことを知るようになります。新しい「知識」が増えるのです。二つ目は、部活動、ボランティアという体験活動によって「視野が広まる」ことです。体験をつうじて自分とは違う行動や考え方をする人に出会います。そうすることで「そういう考え方もあるんだ」とか「こういう方法もできるんだ」と自分自身の考え方が広まるでしょう。それが「視野が広まる」ということです。
三つ目は「意識が深まる」ということ。インターンシップ、ボランティア等で仕事を任されることによって「しっかりしなくては」と思い、「もっといい方法はないか」といろいろ工夫します。それが「意識が深まる」ということです。そうなれば、それは誰かに命令されてする「受け身の仕事」ではありません。「自分の仕事」です。仕事を任され「もっといい方法はないか」と思案するとき、役に立つのがこれまで学んだ「知識」であり、自分とは違う行動や考え方の人と出会うことによって身につけた「視野の広さ」です。その域に達すれば、三つの成長が統合されます。それが高校で学ぶということです。
この洲本高校定時制のミッションやビジョンは、洲本高校定時制誕生のその時から、DNAのように組み込まれていたのです。それは、洲本高校定時制の歴史を振り返ればわかります。今の高校教育は、太平洋戦争後の昭和23年10月、新しい高校の制度が発足すると同時に生まれました。しかし、洲本高校定時制は、その4ヶ月も前から、洲本市立幼稚園を間借りして「夜間高校準備教育」として始まっていたのです。この洲本高校定時制の歴史は、学校のために「学び」があるのではなく、「学び」のために学校がつくられたという、「教育」と「学び」の本質を体現しています。その教育の原点を忘れることなく、ともに頑張っていきましょう。
平成28年度
平成27年度
平成26年度
平成25年度
|