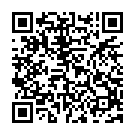学校長より
洲本高等学校 学校長
越田 佳孝
|
 |
10月10日(土)、神戸市長田区のピフレホールで、第65回兵庫県高等学校定時制通信制生徒生活体験発表大会がありました。洲本高等学校定時制は、学校行事として2台のバスに分乗して、全員で参観してきました。今回は残念ながら、本校生徒は県大会に出場していませんが、県大会への出場者の有無に関わらず、学校の行事として全員で県大会を参観すると決めていたのです。
本校は、昨年度から「高校生 心のサポートシステム コミュニケーションの在り方実践研究」指定校として研究を続けています。そもそも「コミュニケーション」の語源はラテン語で、コムニカチオ(communicatio)、意味は「分かちあうこと、共有すること」ということを意味します。「コミュニケーション能力がある」とか「コミュニケーション能力が高い」というのは、知識や情報をやりとりする能力が高く、秀でているということよりも、相手との感情や気持ちを共有する能力が高く、優れているということなのです。ですから、「コミュニケーション」の基本は、相手が伝えようとすることを、自分がしっかり理解しようとする姿勢にあります。同時に、相手に自分を正確に理解してもらおうと努力することでもあります。そういう意味で、生活体験発表会には大きな教育的意義と効果があるのです。
本校の生活体験発表会への取り組みは、生活体験発表作文を書くことから始まります。その作文を書くための指導プリント「生活体験文について」はこう言っています。
「この生活体験文は、自分の体験を通して、自分を語るものです。自分を語ると言うことは簡単なようでいて、実は結構難しいものです。第一に自分自身のことをよく知らなければなりませんし、第二に人が誤って受けとらないように、表現に気をつけなければならないのです」。
今回、定時制通信制生徒生活体験発表大会(県大会)に、学校行事で参観すると決めたのは、こういうきめ細やかな丁寧な指導がなされていることを前提とした取り組みです。
担任からは、当日までに、県大会を参観する意義について話してもらいました。自分たちと同じ定時制通信制の生徒の体験と成長の物語を聞くことによって、自分の生活も振り返ることができる。それぞれの「思い」を伝えたいという熱い気持ちと、その気持ちに裏付けられた巧みな表現にも直接触れることで自分の成長にもつながる。さらに人前で発表すると言うことはとても勇気がいることであり、まして自分を語る生活体験発表となるとなおさらである、そういう人に対しては聴く姿勢にも配慮し、敬意を払わなければならないと話してもらいました。
この体験は、若い先生にとっても、生活体験発表作文等を指導する上で、指導の目標が明確になって、結果として指導力の向上につながります。当日、生徒全員にプログラムが配られたことを知った私は、生徒に提案しました。「みんなで、審査員になったつもりでしっかり聴こう。そして順位をつけてみよう。見事順位が一致した者には賞品を出すぞ」と。急な出費になりましたが、生徒はしっかり聴き、審査をしていました。「コミュニケーション」は、「話すこと」からではなく「聴くこと」から始まるのです。
平成28年度
平成27年度
平成26年度
平成25年度
|