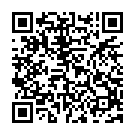学校長より
洲本高等学校 学校長
越田 佳孝
|
 |
9月2日は二学期の始業式。生徒と会うのは、7月19日の一学期の終業式以来40日ぶりです。洲高の定時制では、始業式で校歌も応援歌も歌います。校長式辞は、校歌斉唱と応援歌に挟まれて「式次第」に組み込まれています。何か意図があるのかしらと勘ぐりたくなりますね。以下は、洲本高等学校定時制の課程、二学期始業式での私のあいさつです。
今日から二学期です。皆さんに会うのは一学期の終業式以来ですから、40日ぶりです。この夏いろいろな体験をしたでしょう。仕事・アルバイトに頑張った人、部活動で全国大会に出場した人、インターンシップを経験した人、そしてサマーボランティアに参加した人ときっと様々な体験をしたことでしょう。夏休みや冬休みといった長期のまとまった休みは、皆さんが大きく「成長」する絶好の機会なのです。7月の生活体験発表会でも話しましたが、「成長」とは、昨日に比べて今日、昨年に比べて今年の「変化」をいいます。これまでの自分に比べて現在の自分の「変化」なのです。生活体験校内発表会で、皆さんが姿勢を正して友だちの発表に聞き入っていたのは、友の成長に自らの成長を重ねて聞いていたからです。
私は、高等学校で学ぶということは、三つの点で成長することだと思っています。一つは、高校で学ぶことにより「知識が増える」ことです。漢字や英単語、数学の公式等を学ぶことにより、これまで知らなかったことを知るようになります。新しい「知識」が増えるのです。二つ目は、部活動、さらには仕事・アルバイト、インターンシップ、ボランティアという体験活動によって「視野が広まる」ことです。体験を 通じて様々な人と知り合いになりますね。自分とは違う行動や考え方をする人に出会います。そういう体験をすることで「そういう考え方もあるんだ」とか「そういうやり方もできるんだ」と自分自身の考え方が広まるでしょう。それが「視野が広まる」ということです。「考え方」の幅が広がるのです。
三つ目は「意識が深まる」ということです。仕事・アルバイト、インターンシップ、ボランティア等で、「ここはあなたが責任持ってね」と仕事を任されることがありますね。そういう風に仕事を任されることによって「しっかりしなくては」と思い、「もっといい方法はないか」といろいろ工夫しますね。それが「意識が深まる」ということなのです。そういう域に達すれば、それは誰かに命令されてする「受け身の仕事」ではありません。「自分の仕事」です。
仕事を任され「もっといい方法はないか」と思案するとき、役に立つのがこれまで学んだ「知識」であり、自分とは違う行動や考え方の人と出会うことによって身につけた「視野の広さ」です。それはもう皆さんがやっていることかもしれません。スーパーの棚に商品を並べるときに、商品名に「ふりがな」をつけたり、先輩がやっていたように、一番買って欲しい商品をお客様の目線と一致する棚に置いたりする工夫がそれです。それが高等学校で学ぶということです。皆さんはすでに成長の一歩を踏み出しています。ともに学びましょう。
平成28年度
平成27年度
平成26年度
平成25年度
|