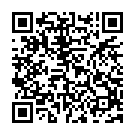学校長より
洲本高等学校 学校長
越田 佳孝
|
 |
7月17日(水)に、洲本市立市民交流センター(ビバホール)で、平成25年度生活体験発表校内大会がありました。各クラス予選を通過した合計11名の生徒が、友だちのことや部活のこと、学校生活のこと、職場でのことなどの演題で、熱弁をふるいました。
生活体験発表大会は、定時制や通信制高校に通う高校生が、学校生活を通して、感じ、学んだ貴重な体験を自らの「ことば」にして発表する、定時制・通信制高校ならではの長い歴史と伝統を持つ事業です。校内大会を経た代表者は、地区大会(東播磨・淡路地区)、兵庫県大会と進み、最終は全国大会につながります。今年、全国大会は「61回」をかぞえますが、なんと兵庫県大会は「63回」。県大会の方が歴史はあります。昭和26(1951)年11月に、「定時制弁論大会」として始まったからです(『兵庫県教育史』374頁)。
校内大会の話をします。武中教頭も講評で話していましたが、すべての発表者のレベルが高く、素晴らしかった。それぞれの発表者が、友だちや部活などの学校生活、仕事や将来のこと等を、自分が「体験したこと」、「見たり」、「聞いたり」、「感じたこと」を、具体的に自分自身の「ことば」で話していたからです。そこには伝えたいという「力強い意志」が感じられました。そのことが聞く者をして、姿勢を正さしめたのでしょう。聞いている生徒たちの態度も文句なしによかった。それがまた校内大会によい効果をもたらしました。
人の前で話すこと、特にしっかり相手に伝わるように話すには、二つの要素が必要です。それは「話しの中味(内容)」と「話し方(技術)」です。「話しの中味(内容)」で必要なのは「具体性」です。誰でも、どこでも当てはまりそうな抽象的な話は、聞く者の興味を引きません。また、どれだけ素晴らしい内容でも、「話し方(技術)」がつたないと相手に伝わりません。その反対に、いくら「話し方(技術)」(声の大きさ、スピード、抑揚、間の取り方)が上手でも、中味に具体性がないと聞く者の関心を呼びおこさないのです。
私は、校内大会の11人の発表のすべてに明確な「物語」を感じ取りました。それは「成長の物語」です。「成長」とは、昨日に比べて今日、昨年に比べて今年の「変化」をいいます。これまでの自分に比べて現在の自分の「変化」です。「成長」を実感するためには、まず、昨日の、昨年の、そしてこれまでの自分に向き合わなければなりません。それは決して楽しいことではありません。時には避けたいことなのかもしれません。それを避けている限り「成長」は実感できません。自分のものにならないのです。生活体験発表は、定時制の生徒の「成長の物語」です。その生徒たちの「成長の物語」にかかわることができる。それが定時制教育の素晴らしさでしょう。審査員の私たちも成長させていただいた時間でした。
平成28年度
平成27年度
平成26年度
平成25年度
|