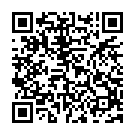学校長より
洲本高等学校 学校長
越田 佳孝
|
 |
今年の冬の厳しい寒さは、本校の南側の敷地に沿って植わっている、水仙の開花を遅らせたようです。しかし、3月を目の前にして校庭をながめると、日差しは格段に明るくなり、春の香りがあちこちに漂い始めました。冬から春への季節の巡りと、つぼみから花への生物の成長を感じさせます。このつぼみがふくらむように心も大きくふくらむ早春の良き日に、洲本市長 竹内 通弘 様 本校同窓会長 細川 末勝 様はじめご来賓の方々、多くの保護者の皆様のご出席をいただき、兵庫県立洲本高等学校定時制の課程、第64回卒業証書授与式が挙行できますことをうれしく思います。
ただ今卒業証書授与した 男子7名、女子13名、計20名の皆さん、ご卒業おめでとうございます。みなさんの在学中の努力に対し、賛辞と祝福を送ります。みなさんは、それぞれ一人ひとりが、数えきれないほどの苦労と喜びを積み上げて、今日の日を迎えられました。人生80年の時代においては、本校で過ごした時間は、決して長いものではありません。しかしながら、みなさんは思っているよりもはるかに「大事な時」を過ごし、4年前、あるいは3年前より着実に成長して、今日の日を迎えたのです。
洲本高校の定時制は、太平洋戦争後の昭和23年10月、新しい高等学校の制度が発足すると同時に生まれました。県下で一番古い定時制です。今から67年前のことです。実は、昭和23(1948)年の1月には、「働く青年のために夜間学校をつくろう」というポスターが、洲本市内いたるところの電柱や家々に貼り巡らされました。「洲本市夜間高校期成同盟」に集まった15歳から20歳にも満たない少年たちの「学ぶこと」に対する真摯でひたむきな魂の叫びの運動です。
この運動では、市内全域にわたって行った戸別訪問で、短期間の間に約5,000人の署名が集まり、それを洲本市長に提出しました。結果、その年の6月には、洲本市の全面的な支援のもと、洲本市立幼稚園を間借りして「夜間高校準備教育」が始まりました。記録では6月25日から9月25日まで授業を行っていたとあります。まだ正式に定時制が発足する4ヶ月も前の話です。この洲本高校定時制の歴史は、学校のために「学び」があるのではなく、「学び」のために学校がつくられたという、「教育」と「学び」の本質を体現しています。
与えられた環境の中で、なんとかして学びたい、新しい知識を身につけたいとして、未知のものに果敢に挑戦していく姿勢にこそ「学び」の本質があります。試験に受かりたいから学ぶ、資格を取りたいから学ぶ、誰かに賞賛されたいから学ぶ。それらも学ぶ動機の一つでしょう。私は否定しません。しかし、それらの「○○のために」という「目的」から自由な「学び」にこそ、「学ぶこと」の本来の在り方があると私は思っています。
昨年度に着任した私は、今回、みなさんが本校を卒業するに当たって、みなさんが洲本高校の定時制で過ごした4年間、あるいは3年間に少しでも触れようと、4年分の『夜学の歳時記』を読み通してみました。『夜学の歳時記』は、洲本高校定時制通信『夜学の灯』をはじめ、年間の行事予定、生活体験発表会の県大会出場者の原稿、部活動の記録などを掲載した、洲本高校の定時制の1年間の記録です。
『夜学の歳時記』第11号には、今から4年前の平成23年5月27日発行の洲本高校定時制通信『夜学の灯』91号がおさめられています。その中には、担任の金戸先生を囲んで、定時制集会室の前の満開の桜の木の下での記念写真が掲載されています。当日はあいにくの雨模様だったようです。しかし、そこには、その雨を振り払うかのように、一抹の不安を醸し出しながらも、晴れがましいみなさん一人ひとりの満面の笑顔がありました。
つづいて「1年生の声」を紹介しています。定時制らしく「仕事と勉強を両立させる」という声、「自分の限界をこえてみる」、さらには「定時制を辞めずにがんばる」「がんばって卒業する」と意気込みを語ってくれています。頼もしい限りです。生活体験発表会の県大会出場者の原稿では、洲本高校定時制に出会うまで、自らの居場所というか、自分自身がしっくりとくる「学びの場」を求めて、彷徨っていた小中学校時代の日々を、赤裸々に綴ってくれたものもありました。小中学校時代に悩んで、悩んで、悩み抜いて、やっと見つけた自分自身が落ち着いて学べる場、安心して友だちとつながることができる居場所、それが洲本高校定時制だったと語ってくれています。これも嬉しい限りです。
学校のために「学び」があるのではなく、「学び」のために学校がつくられた。この教育と学びの本質を、私たちはややもすると忘れがちです。私は、現在の教育や学校がかかえる様々な問題の病巣は、「学校のために「学び」があるのではなく、「学び」のために学校がつくられた」という、ほんの少し冷静になって考えてみればわかる自明の理を忘れ、それを取り違えてしまったところにあると考えています。学校のために『学び』があるのではなく、『学び』のために学校がつくられた。これが洲本高校の定時制です。
私は、みなさんに、まず学校に来る、そして授業をしっかり受けて学ぶ、さらには学んだ「成果」をいかし自らの将来への道筋をつける、と機会ある毎に話し続けてきました。みなさんが4年間または3年間学んだ、洲本高校定時制は、その魅力・特色を「できる」「わかる」「つながる」の3つのコンセプトで説明できます。まず、学校に来れば、小中学校の時に学び残してきたものを学び直すことができる。さらには、一旦は学校を離れてしまったが、もう一度学びたいと思う人は再び学び直すことができるのです。これが「できる」です。学校に来て授業を受ければ、少人数で授業内容がわかるようになり、ソーシャルスキルトレーニング等を通じて相手の気持ちもわかるようになります。これが「わかる」です。そして、体育祭、文化祭、ボランティア活動、生徒会活動等の様々な学校行事によって、友だち、先輩、先生、さらには地域の人たちとつながっていきます。そしてそういう人たちとのつながることによって視野が広まり、責任感などの意識が深まり、そのことで自らの将来に道筋がつき、自分の未来につながるのです。それが「つながる」です。
みなさんはそのことを実践してきて、今日、晴れて卒業の日を迎えることができました。卒業は、新しい世界への旅立ちです。しかし怯んではなりません。みなさんには「大きな力」が身についています。洲高の定時制で学んだ「自信」と「誇り」です。私は、これからの皆さんの生き方を信じています。だれのでもない自分の人生です。悔いのないよう生きて欲しい。その際、「誇りと思いやり」を忘れないで欲しい。自分は誇りを持って生きているか、他に対して思いやりのある言動をしているかと、常に自分に尋ねて欲しいのです。それが校訓にいう「至誠」です。
果物は、種であることを否定して芽となり、花となり、花であることを否定して初めて実となります。人間も同じように、自分の中の子供の部分を否定して、大人になるのです。みなさんは、洲高の定時制での4年間、または3年間で大きく成長したのです。
最後になりましたが、保護者の皆様に一言申し上げます。お子様のご努力が実って本日のご卒業を迎えられたこと、まことにおめでとうございます。私どもはお預かりして4年、または3年間、不十分な点もあったかとは思いますが、学級担任を中心に全力で教育にあたってきました。ここにいたるまでに賜りましたご支援に対し、この場を借りて深く感謝申し上げます。なによりも、私どもは、素直ですばらしい生徒と、師弟同行、この洲本高等学校定時制で一緒に生活できたことをうれしく思っています。
卒業生の皆さん、いよいよ新しい出発の時です。私たちは、皆さんの今後の発展と活躍を心から期待し、信じています。皆さんの前途が幸せの多いものとなりますようお祈りし、式辞といたします。
平成27年2月26日
兵庫県立洲本高等学校長 越田 佳孝
平成28年度
平成27年度
平成26年度
平成25年度
|