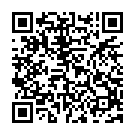学校長より
洲本高等学校 学校長
越田 佳孝
|
 |
春の陽光天地に満ち満ちて 風ふくよかな香りを運びくるこのよき日に、育友会・同窓会役員の皆様をはじめご来賓の方々、保護者の皆様のご臨席を賜り、ここに兵庫県立洲本高等学校定時制の課程の入学式を挙行できますことは、私のこの上ない喜びであります。
ただいま入学を許可いたしました27名の新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。皆さんを昭和23年、1948年、新制高等学校の誕生と同時に創立された歴史と伝統を誇る本校定時制の生徒として迎え入れることを、在校生、教職員一同、本当に嬉しく思いますとともに、今日まで、新入生の皆さんを支えてこられた保護者の皆様に、心よりお祝い申しあげます。
さて、今、皆さんの心は、入学の喜びとこれから始まる高校生活への期待に大きく膨らんでいることでしょう。しかし、皆さんは、それよりもまず先になさなければならないことがあります。それは、みなさんの今日の喜びの陰には、ご両親をはじめ家族の方々、小中学校の先生、また、直接間接に皆さんを守り育ててくださった数多くの人たちの有形無形の協力と支援、そして指導があったことを振り返ってみることです。高校生になるということは、こういうはっきりと形に見えないことがらを、実感をもって分かるようになるということでもあります。そして、それに対する感謝の気持ちを何らかの形で言葉や態度に表すとともに、これからの高校生活を通して、高い知識と教養、豊かな人間関係、逞しい心と体を備えた人間として自らを鍛えあげていくことが、これらの方々のご恩に報いる道であります。
さて、本校の教育は、第二次世界大戦後すぐに、洲本市内で始まった「働く青年のために夜間学校をつくろう」という二十歳にも満たない少年たちの運動で始まりました。「学びたい」しかし、もろもろの事情で働かなければならない。そういう少年たちの「学び」に対する渇望の声。学ぶことの本当の楽しさ、すばらしさを知るものたちの真摯でひたむきな魂の叫びでした。県立洲本高等学校定時制の課程を作り上げてきたのはそういった先輩たちだったのです。その伝統は、本校の校訓「至誠・勤勉・自治・親和」に脈々と受け継がれています。「学ぶ」ということの大切さを知り、「○○のために」という学びから、ひたすら「学びたい」ただその一念でもって、夜の洲本市内の各所に「働く青年のために夜間学校を」というポスターを貼りまわった皆さんの先輩たちの姿こそ、「学ぶこと」の本来の在り方を知っている者の姿だといえるでしょう。
何かの目的のために、前へ、前へと前のめりに駆り立てられていく「学び」は本来の「学び」ではありません。しかし、一方でそういう時期をすごさないと本来の「学び」は体得できないのかも知れません。そういう意味で、六十数年前に、本校の定時制を作るために奔走した先輩たちは、学ぶ前に、学ぶことの本質を体得していたのでしょう。
今日、洲本高等学校定時制に入学した皆さんは、そういった素晴らしい先輩たちの歴史に加わったのです。そういう先輩たちを心に描き、洲本高等学校定時制での生活を充実したものにしていって下さい。六十数年前の先輩たちも、まだ見ぬ今の皆さんを心に描き、夜の洲本市内の各所にポスターを貼りまわったのでしょう。自分のことだけではなく、自分以外の人のことも、そして、自分に連なるまだ見ぬ人のために行動する。それが成長です。
成長とは、昨日に比べて今日、昨年に比べて今年の変化をいいます。これまでの自分に比べて現在の自分の変化です。成長を実感するにはまず、昨日の、昨年の、そしてこれまでの自分にしっかりと向き合わなければなりません。それは決して楽しいことではありません。時には避けたいことかも知れません。しかし、それを避けている限り成長はありません。自分のものにならないのです。
この洲本高等学校定時制には、しっかりと皆さん一人ひとりに向き合ってくれる先生がいます。そして、一緒に学ぶ仲間がいます。さらには、皆さんを温かく見守ってくれる先輩たちがいます。洲本高等学校の定時制ではまず学校へ来ること、そしてしっかり学びましょう。そして、仲間たちと関わり合い、楽しく過ごしましょう。対象に働きかけて対象を変えることは、それと同時に、あるいはそれ以上に自分自身が変わることです。ある人は「成長とは今ある自分を否定して生まれ変わることだ」といっています。果物は、種であることを否定して芽となり、花となり、花であることを否定して初めて実となります。人間は、自分のなかの「子ども」を否定して「おとな」になります。
本校の校訓の最初に上がってくる「至誠」とは、真心がこもっているということを意味します。自分の良心に従い、相手の立場や気持ちを考え、全力を尽くすこと。これが大切であるのは、だれも否定しないでしょう。しかし、人間はいつも理想どおりには行動できないのであり、また過ちもおかし、自己嫌悪に陥ったりするのです。大事なことは、そういう場合に、目を背けずに真正面から自分のいたらなさや過ちを認め、もう一度勇気を奮い起こして再出発することです。
第二次世界大戦後すぐに洲本市内で始まった「働く青年のために夜間学校をつくろうという」という運動を主導したのは、皆さんと同じ年頃の少年です。皆さんが、今日ここに新入生としてたつことができるのは、その「学ぶこと」に何よりも飢えていた少年たちの思いがあったからです。伝統というのは、そういった諸先輩の思いをしっかり受け継ぎ、新たな新しいページを、来年、再来年、そして十年、二十年後の「わたし」のために尽くすということです。それが、大人になるということなのです。
あとになりましたが、保護者の皆様に対して、心からご子弟の本校入学のお祝いを申し上げます。本日確かに、ご子弟をお預かりいたしました。四年ないし三年後の卒業時には、県立洲本高等学校に入学させてよかったと喜んでいただけるよう、私どもは教え、育むことの専門職としての誇りと矜恃にかけて、全身全霊を込め、真剣勝負をするつもりでご子弟の教育に当たりますので、保護者の皆様にも、本校教育に対するご理解とご支援をよろしくお願い申し上げます。
後に、改めて、本校の校歌に歌う「洲高の若きもの」27名の今後の成長・発展を心からお祈りするとともに、応援歌にあるように「築け洲高の定時制」との期待を申し上げて、私の式辞といたします。
平成二十六年四月八日
兵庫県立洲本高等学校長 越田 佳孝
平成28年度
平成27年度
平成26年度
平成25年度
|