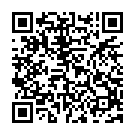学校長より
洲本高等学校 学校長
越田 佳孝
|
 |
私の家の書斎に置かれたうす桃色のシクラメンは、この冬から春にかけて毎日美しい花を咲かせてくれています。冬から春への季節の巡りと、つぼみから花への生物の成長を日々感じさせてくれるのです。このつぼみがふくらむように心も大きくふくらむ早春のこの良き日に、洲本市副市長 森屋 康弘 様 本校同窓会長 細川 末勝 様はじめご来賓の方々、多くの保護者の皆様のご出席をいただき、兵庫県立洲本高等学校定時制の課程 第63回卒業証書授与式が挙行できますことを心からうれしく思います。
ただ今卒業証書授与した 男子15名、女子10名、計25名の皆さん、ご卒業おめでとうございます。みなさんの在学中の努力に対し、心からの賛辞と祝福を送ります。保護者の皆様には、4年、または3年前にお預かりいたしましたお子様がこのように立派に成長され、本日めでたくご卒業を迎えられましたことを心からお喜び申し上げます。
みなさんは、それぞれ一人一人が、数えきれないほどの苦労と喜びを積み上げて、今日の日を迎えられました。人生80年の時代においては、本校で過ごした時間は、決して長いものではありません。みなさんの中には「取り立てて言うべき期間ではなかった」という意識があるのかもしれません。しかしながら、みなさんは、思っているよりもはるかに「大事な時」を過ごし、4年前、あるいは3年前より着実に成長して今日の日を迎えたのです。
私が、この学校に着任したのは昨年の4月で、皆さんとはわずか1年という短いつきあいでした。はじめての校長職を拝命して、県立洲本高等学校定時制に着任して一番驚き、素晴らしいと感じたことは、4月の始業式、そして今の一年生の入学式でした。卒業生のみなさんを含めて、洲本高等学校定時制の生徒たちが校歌を大きな声で歌い、応援歌を熱唱することです。しかも、このことをみなさんは「当たり前のこと」と思い、当然のこととしており、特段気にかけている様子が微塵もないことです。
私が「おどろき」「素晴らしい」と感じたことは、校歌・応援歌を大きな声で歌うということよりも、その自体、それはそれで素晴らしいことなのですが、それを取り立てていうべきことではない、当たり前のこと、当然のこととしてすましているみなさんの姿勢であり、態度なのです。もちろん、新入生は当然声も小さいです。当たり前です。初めて聞く歌詞、メロディーなのですから。しかし、それを圧倒する先輩たちの熱唱です。新入生は、それを耳で聞き、体で感じ、心で触れて、洲高の定時制で学ぶということの意味を自分のものにしていく、第一歩を踏み出すのです。今日卒業を迎えられるみなさんも4年前、3年前はそうだったのでしょう。生徒だけでなく先生も含めて、そこに集い、学ぶものが、誇りをもって大きな声で校歌・応援歌を歌う。それが洲高の定時制だと感じたのです。このことは、どんなに巧みな美辞麗句よりも、雄弁に洲高の定時制の在り方を伝えています。
私は、今回、みなさんが本校を卒業するに当たって、みなさんが洲高の定時制で過ごした4年間あるいは3年間に少しでも触れようと、3年分の『夜学の歳時記』を読み通してみました。『夜学の歳時記』は、洲本高等学校定時制通信『夜学の灯』をはじめ、年間の行事予定、生活体験発表会の県大会出場者の原稿、部活動の記録などが掲載された、洲高の定時制の一年間の記録です。その中に一年間、そして私が読んだ3年分の『夜学の歳時記』、いやもっとそれ以前から、洲高の定時制教育の底流に、あたかもバロック音楽でいうところの「通奏低音」のように厳然として存在する「教育理念」があります。それは「体験活動」という「外」に対する働きかけです。先ほどの生活体験発表会もそうですし、陶芸家の先生をお招きしての「陶芸教室」、地元「川西みどり会」の方々とともにする「グランドゴルフ」、交通安全実技教室、そして清掃活動、由良総合福祉センターを訪問するボランティア活動もそうです。対象を学校内から「外」へ向けた活動です。この「外」に対する具体的な働きかけこそが、物事を変え、自分を成長させてくれるのです。
7月の生活体験発表会でも話しましたが、「成長」とは、昨日に比べて今日、昨年に比べて今年の「変化」をいいます。みなさんなら、4年前、3年前の自分比べて現在の自分の「変化」です。私は、常々高等学校で学ぶということは、三つの点で成長することだといってきました。一つは、高校で学ぶことにより「知識が増える」ことです。漢字や英単語、数学の公式等を学ぶことにより、これまで知らなかったことを知るようになることです。
二つ目は、仕事・アルバイト、インターンシップ、ボランティアという体験活動によって「視野が広まる」ことです。体験をつうじて様々な人と知り合いになります。自分とは違う行動や考え方をする人に出会うことで「そういう考え方もあるんだ」とか「そういうやり方もできるんだ」と自分自身の考え方が広まることです。<br>
三つ目は「意識が深まる」ということです。仕事・アルバイト、インターンシップ、ボランティア等で、「ここはあなたが責任持ってね」と仕事を任されることがあります。そういう風に仕事を任されることによって「しっかりしなくては」と思い、「もっといい方法はないか」といろいろ工夫します。それが「意識が深まる」ということです。
対象に働きかけて対象を変えることは、それと同時に、あるいはそれ以上に自分自身が変わることです。私は、これからの皆さんの生き方を信じています。だれのでもない、自分の人生です。悔いのないよう生きてほしいと思います。その際、「誇りと思いやり」を忘れないでください。自分は誇りを持って生きているか、他に対して思いやりのある言動をしているかと、常に自分に尋ねてほしいのです。それが、校訓にいう「至誠」です。
果物は、種であることを否定して芽となり、花となり、花であることを否定して初めて実となります。人間も同じように、自分の中の子供を否定して大人になるのです。
最後になりましたが、保護者の皆様に一言申し上げます。お子様のご努力が実って本日のご卒業を迎えられたこと、まことにおめでとうございます。私どもはお預かりして4年、または3年間、不十分な点もあったかとは思いますが、学級担任を中心に全力で教育にあたってきました。ここにいたるまでに賜りましたご支援に対し、この場を借りて深く感謝申し上げます。なによりも、私どもは、素直ですばらしい生徒と、師弟同行、この洲本高等学校定時制で一緒に生活できたことをうれしく思っています。
卒業生の皆さん、いよいよ新しい出発の時です。私たちは、皆さんの今後の発展と活躍を心から期待し、信じています。皆さんの前途が幸せの多いものとなりますようお祈りし、式辞といたします。
平成26年2月27日
兵庫県立洲本高等学校長 越田 佳孝
平成28年度
平成27年度
平成26年度
平成25年度
|