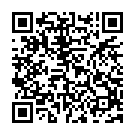学校長より
洲本高等学校 学校長
越田 佳孝
|
 |
今年は本当に暖かいお正月でした。いつも紹介している、石川啄木の「何となく 今年はよいことあるごとし 正月の朝 晴れて風なし」(『悲しき玩具』)という心境でした。
二学期の終業式で、「成長」という話をしました。学校へ来て授業を受けるだけではなく、生活体験発表、体育祭、文化祭、遠足、交通安全教室、由良総合センターへの慰問ボランティアでも学校行事を休まずに、そして楽しんでいることが、周りの人たちに力と元気を与えています。それぞれが、それらの学校行事の集団活動の中で一人一人の果たすべき役割と責任ということです。私は、みなさんが自覚しているか否かにかかわらず、集団活動の中で一人一人の果たすべき役割と責任を果たすという意味では、大きく成長していると思います。
私は、これまで創立記念式や入学式・卒業式などで、ことあるごとに洲本高校定時制が生まれた話をしてきました。洲本高校の定時制は、昭和23年10月、太平洋戦争後、新しい教育制度が発足するのと同時に生まれました。県下で一番古い定時制です。しかも、洲本を中心とした淡路の人々の「教育」や「学ぶこと」に対する凄まじいまでの欲求、学びに対する真摯な渇望、魂の叫びが、学校を作ろうという運動を呼び起こし、その運動の成果が実を結んで、生まれた学校です という歴史と伝統のはなしです。
伝統というのは、「伝統とは何か」という問いを常に発するところに芽生えていくものです。ただ単に時間を過ごしているだけでは「伝統」にはなりません。自分が、今、学んでいる学校はどういう学校なのか、ということを知ることが、今、この学校で学んでいる意味を自分のものにするのです。それが「誇り」となります。みなさんは、それぞれ違う一人一人の人間です。誰しも「その他大勢」として扱われたくはないでしょう。そのためには、自分は何者であるのか、自分は、今、何をしなければならないかをしっかり持っている必要があります。その自分が何者であるかを考える一つのヒントが、自分はどういう歴史と伝統を持っている学校で学んでいるのかということを知ることです。
みなさんの学んでいる洲本高校定時制は、「学び」のために作られた学校です。洲本高校定時制では、生徒はもちろん先生もみなさんと一緒に学びます。仁木先生は、二学期から新聞の「切り抜き」をしています。新聞を読んで、気になった記事、みなさんに話してあげたい記事を切り抜き、スクラップして、職員室で他の先生にも回しています。そうすることで、仁木先生も学びますし、そのスクラップを読んで他の先生も学びます。そして、授業やホームルームで、先生方が紹介してくれる新聞の記事をとおして、社会の動きがわかるようになり、みなさんも学ぶのです。洲本高校定時制はそういう学校です。今日から三学期です。卒業予定者には、この学校で学ぶ時間はあと少しです。ともに頑張りましょう。
平成28年度
平成27年度
平成26年度
平成25年度
|