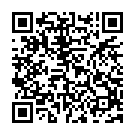学校長より
洲本高等学校 学校長
越田 佳孝
|
 |
今日は9月1日、今日から2学期を始めます。約40日間の夏休み、誰一人、事故にあうことなく過ごしたようです。今日から友だちとワイワイと楽しめる学校が始まりました。
2学期は体育祭、文化祭、交通安全教室等とさまざまな行事があります。毎日の授業や一つ一つの行事を大切にして充実した日を過ごしましよう。
もう一つ9月1日は「防災の日」です。「防災の日」は、1960(昭和35)年に岸信介内閣の閣議了解により始まりました。1923(大正12)年9月1日に発生した関東大震災は、マグニチュード7.9、震度6の規模で、死者・不明者14万2,807名、家屋全半壊25万4千軒余、焼失した家屋は44万7千軒余といわれています。防災の日は、関東大震災の惨禍を忘れないということで制定されました。関東大震災の日に「防災の日」が定められたもう一つの理由に、例年8月~9月1日付近は、台風の襲来が多いとされる二百十日にあたり、「災害への備えを怠らないように」との戒めも込められているそうです。
「天災は忘れた頃にやって来る」は寺田寅彦の言葉だそうです。実際は、寺田寅彦のどの著作を見てもそういう記述がないそうですが、そのように流布しています。誰が言い出したにしても、そのような言葉で「災害」について思いを新たにするのは、「想定外」などという責任逃れの「言い訳」を二度と聞きたくないためには有益でないかと思います。「防災の日」とは、災害に対して思いをはせ「備えを怠らない」という思いを新たにする日だからです。
昨日、私は中井久夫さんの『災害がほんとうに襲った時 阪神淡路大震災50日間の記録』(みすず書房2011)という本を読み返しました。中井久夫さんは、精神科医で神戸大学医学部の名誉教授。阪神淡路大震災当時は神戸大学医学部精神科救急の責任者でした。後にこのときの活動がきっかけで、PTSDや心のケアへの関心が高まり、「兵庫県こころのケアセンター」が設立され、初代所長に就任されました。『災害がほんとうに襲った時』は、未曾有の災害に遭遇した時、人はどう行動したかを記録した本です。
中井さんはその本の中でこう言っています。「指示を待ったものは何ごともなしえなかった。」「統制、調整、一元化を要求したものは現場の足をしばしば引っ張った。」そして結果として「有効なことをなしえたものは、すべて、自分でその時点で最良と思う行動を自己の責任において行ったものであった」と。「何ができるかを考えてそれをなせ」は災害時の一般原則です。何かを為し、一歩踏み出さなければ、その先は見えてこないからです。中井さんの極めつけの一言は、「災害においては柔らかい頭はますます柔らかく、硬い頭はますます硬くなる」の一言です。心身の余裕のない状態になるとそうなるでしょう。大切なのは、普段からいかに「柔軟なものの考え方」を養っていくかです。それは何も特別なことではありません。
定時制では、教育活動のすべての場面で、一人一人を大切にした丁寧な指導を心がけ、生徒たちが学校に行くことが楽しくてしかたがない学校づくり、授業づくり、教師と生徒との人間関係づくりを進めています。さらには、学ぶことが楽しいと思えるような授業づくりです。本校では、全学年・全教科で基礎・基本の定着をはかるとともに、小・中学校ですでに学んだ内容や事項ももう一度しっかり身につけるようにする「学び直し」に力をいれています。次に、学んだ成果を進路実現(就労)つなげる取り組み就業体験(インターシップ)にも力を入れています。その普段の丁寧な取り組みが、いざというときにいきてくる「柔軟なものの考え方」を育んでいくのです。
ですから、私たちは、まず学校に来ること、次に授業を受けて学ぶこと、そして学んだ成果を活かして、自らの将来の進路実現へと道筋をつけていくことです。
本校の定時制の生徒たちは、他のどの学校の定時制の生徒よりも、あいさつをしてくれますし、学校行事では校歌・応援歌を大きな声で歌います。学校に対してそれだけ愛着を持ってくれているのでしょう。教えるものとしてこれ以上のうれしいことはありません。洲高の定時制での「学び」は、皆さんがこれから一生たくましく生きていく上での「資本」となっています。2学期、さまざまな行事を経験して一回り大きく成長していきましょう。
平成28年度
平成27年度
平成26年度
平成25年度
|