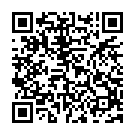学校長より
洲本高等学校 学校長
越田 佳孝
|
 |
| 「県立洲本高等学校定時制の課程第65回卒業証書授与式式辞」
|
今年の冬は暖かさに恵まれ、本校の南側の敷地に沿って植わっている、水仙の開花を早めました。冬から春への季節の巡りと、つぼみから花への生物の成長を感じさせます。このつぼみがふくらむように心も大きくふくらむ早春の良き日に、洲本市長 竹内 通弘 様 本校同窓会長 川端 通 様はじめご来賓の方々、多くの保護者の皆様のご出席をいただき、兵庫県立洲本高等学校定時制の課程 第65回卒業証書授与式が挙行できますことを、うれしく思います。
ただ今卒業証書授与した 男子8名、女子10名、計18名の皆さん、ご卒業おめでとうございます。みなさんの在学中の努力に対し、賛辞と祝福を送ります。みなさんは、それぞれ一人一人が、数えきれないほどの苦労と喜びを積み上げて、今日の日を迎えられました。人生80年の時代においては、本校で過ごした時間は、決して長いものではありません。しかしながら、みなさんは、思っているよりもはるかに「大事な時」を過ごし、4年前、あるいは3年前より着実に成長して、今日の日を迎えたのです。
私が、みなさんの洲本高校定時制での成長を実感したのは、校長として洲本高校定時制に着任した年、ちょうどみなさんが2年生ないし1年生の時の生活体験発表会校内大会でした。場所は、今日と同じ、この洲本市立市民交流センタービバホールです。優勝は、「部活」と題した4年生でしたが、準優勝には2年の伊勢 未彩さん(演題「高校生活」)と同じく2年の濵田 奈々実さん(演題「将来のために」)が選ばれました。私は、その時、生活体験発表会校内大会で発表した11人のすべてに明確な「成長の物語」を感じ取りました。
「成長」とは、昨日に比べて今日、昨年に比べて今年の「変化」をいいます。これまでの自分に比べて現在の自分の「変化」です。「成長」を実感するためには、まず、昨日の、昨年の、そしてこれまでの自分に向き合わなければなりません。それは決して楽しいことではありません。時には避けたいことなのかもしれません。
生活体験発表では、それぞれの発表者が、これまでの自分はどうだったのかから始まり、洲本高校定時制に入学してからの、友だちとの関係や部活などの学校生活、仕事や将来のこと等を、自分が「体験したこと」、「見たり」、「聞いたり」、「感じたこと」を、自分自身の「ことば」で話していました。そこには、これまでの未熟な自分を赤裸々にさらけ出し、それが洲本高校定時制に入学して、仲間と出会い、やさしい先生方に触れ、学校行事・生徒会活動を通して責任を委ねられ、バイトや仕事ではその責任を全うすることの厳しさと同時に誇りを感じ取っていった自分自身の成長の話を聞くことができました。そこには伝えたいという「力強い意志」が感じられました。そのことが聞く者をして、姿勢を正して聞かせたのでしょう。そういう仲間の発表をしっかり聞いている生徒の姿勢もよかった。
今、この変化の激しい世の中で、逞しく生き抜いていくためには、「コミュニケーション能力」が必要だと言われています。しかし、私には、「コミュニケーション能力」が必要だと言われている割には、そもそも「コミュニケーション能力」とは何かということをしっかり理解して使われているようには思えません。
英語の「コミュニケーション」とは、もともとラテン語でコムニカチオ(communicatio)といい、「分かちあうこと、共有すること」ということを意味します。「コミュニケーション能力がある」とか「コミュニケーション能力が高い」というのは、知識や情報をやりとりする能力が高く、秀でているということよりも、相手との感情や気持ちを共有する能力が高く、優れているということなのです。
ですから、「コミュニケーション能力」の基本は、相手が伝えようとすることを、自分がしっかり理解しようとする姿勢にあります。同時に、相手に自分を正確に理解してもらおうと努力することでもあります。そういう意味で、私が、洲本高校定時制の生活体験発表会で、成長を感じ取ったのは、壇上の発表者だけではなく、その発表者が壇上からの発表している気持ちを、自らのこととして分かちあい、共有して、粛として聴いていた聴く者の姿勢にあります。それが洲本高校定時制の素晴らしさなのです。
私は、高等学校で学ぶということは、三つの点で成長することだと思っています。一つは「知識が増える」ことです。英単語や数学の公式等これまで知らなかったことを知るようになります。新しい「知識」が増えるのです。二つ目は、部活動、ボランティアという体験活動によって「視野が広まる」ことです。体験をつうじて自分とは違う行動や考え方をする人に出会います。そうすることで「そういう考え方もあるんだ」とか「こういう方法もできるんだ」と自分自身の考え方が広まるでしょう。それが「視野が広まる」ということです。
三つ目は「意識が深まる」ということ。インターンシップ、ボランティア等で仕事を任されることによって「しっかりしなくては」と思い、「もっといい方法はないか」といろいろ工夫します。それが「意識が深まる」ということです。そうなれば、それは誰かに命令されてする「受け身の仕事」ではありません。「自分の仕事」です。仕事を任され「もっといい方法はないか」と思案するとき、役に立つのがこれまで学んだ「知識」であり、自分とは違う行動や考え方の人と出会うことによって身につけた「視野の広さ」です。その域に達すれば、三つの成長が統合されます。それが高等学校で学ぶということです。
私は、着任以来、みなさんが学んでいる洲本高校定時制とはどんな学校であるかについて、ことある毎に話をしてきました。卒業式にあたってもう一度同じ話をします。洲本高校の定時制は、太平洋戦争後の昭和23年10月、新しい高等学校の制度が発足すると同時に生まれました。県下で一番古い定時制です。ただ一番古い定時制だけではなく、「設立された」とか「創立された」というように「受け身形」で語ることのできない存在であるということです。それは、洲本を中心とした淡路の人々の「教育」や「学ぶこと」に対する凄まじいまでの欲求、真摯な渇望が、学校を作ろうという運動を呼び起こし、その運動の成果が実を結んで、生まれた学校だからです。今から67年前のことです。
さらに前史があります。昭和23(1948)年の1月、「働く青年のために夜間学校をつくろうという」というポスターが、洲本市内いたるところに貼り巡らされ、短期間の間に約5,000人の署名が集まりました。結果、その年の6月には、洲本市の全面的な支援のもと、洲本市立幼稚園を間借りして「夜間高校準備教育」が始まりました。まだ正式に定時制が発足する四ヶ月も前の話です。
この洲本高校定時制は、学校のために「学び」があるのではなく、「学び」のために学校がつくられたという、「教育」と「学び」の本質を体現している学校です。私は、みなさんに、まず学校に来る、そして授業をしっかり受けて学ぶ、さらには学んだ「成果」をいかし自らの将来への道筋をつける、と機会ある毎に話し続けてきました。みなさんはそのことを実践してきて、今日、晴れて卒業の日を迎えることができました。卒業は、新しい世界への旅立ちです。しかし、怯んではなりません。みなさんには「大きな力」が身についています。どこの学校でもない、洲本高校の定時制で学んだという「自信」と「誇り」です。
最後になりましたが、保護者の皆様に一言申し上げます。お子様のご努力が実って本日のご卒業を迎えられたこと、まことにおめでとうございます。私どもはお預かりして4年、または3年間、不十分な点もあったかとは思いますが、学級担任を中心に全力で教育にあたってきました。ここにいたるまでに賜りましたご支援に対し、この場を借りて深く感謝申し上げます。卒業生の皆さん、いよいよ新しい出発の時です。私たちは、皆さんの今後の発展と活躍を心から期待し、信じています。皆さんの前途が幸せの多いものとなりますようお祈りし、式辞といたします。
平成二八年二月二五日
兵庫県立洲本高等学校長 越田 佳孝
平成28年度
平成27年度
平成26年度
平成25年度
|