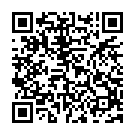学校長より
洲本高等学校 学校長
越田 佳孝
|
 |
今日から3学期が始まります。新しき年は始まりましたが、あと3月までが今年度です。
今年は穏やかなお正月でした。石川啄木は「何となく 今年はよいことあるごとし 正月の朝 晴れて風なし」(『悲しき玩具』)という歌を残しています。おだやかな天気となった元旦の朝、その雰囲気を「すがすがしい」と感じ、「清浄な気分」を味わったのでしょう。それで「何となく 今年はよいことがあるようだ」といっているのです。石川啄木がこの歌をよんだのが明治44年です。実は、この時期、啄木は重い病に冒されていました。そういうことがあって、「今年はなんとかよい年になって欲しい」という思いでこの歌を作ったのかも知れません。「今年はなんとなくよい年になりそうだ。だから頑張ろうと」。
元旦という日は不思議な日です。たった一日しか変わらないのに、昨日を去年といい、今日を今年といいます。私たちは、そこに何か大きな違いを感じてしまうのです。去年という昨日と今年という今日はほとんど変わっているとは見えないのにです。古い歌にも「いかに寝て 送るあしたにいふことぞ 昨日を去年と けふを今年と」(後拾遺集)「去年という 昨日にけふは変わらぬを いかに知りてか 鶯の鳴く」(千五百番歌合)があります。
このことは、終業式でお話しした、日本人は「節目の時」が大変好きで、こういう「節目」に襟をただし、大きく成長する機会としてきたということに通じる考え方でしょう。こういう感覚を大事にし、そういう中で、居住まいを正し、目を閉じて祈り、決意を新たにしてきたのです。石川啄木も、昨日と今日が、たった1日で去年と今年になる元旦の朝が、おだやかな天気だったことに感じ、「よい年にしよう」と自分言って聞かせたのです。
今年は午年(うまどし)。午は十二支の7番目の干支、一日に置き換えれば、「午の刻」とは、午前11時頃から午後1時頃の時間に当たります。午前・午後、正午という言葉は「午の刻の前」「午の刻の後」「正に午の刻」という意味です。一日の中心を意味し、昔から活気あふれる最高の歳とされているようです。何事も「ウマくいく年」です。
さて、4年生にとっては、高校生活もいよいよ残り少なくなってきました。今日は「最後の始業式」。これからは「最後の○○」という言葉を頻繁に聞くこととなります。洲本高校でのこれまでの生活をかみしめ、残された時間をこれまでと同じように大切に過ごしていきましょう。他の生徒もそれぞれ課題を抱えた3学期です。課題の大きさ・難しさ等に負けることなく、皆さんがもてる能力を最大限に発揮してくれることを期待しています。
「よい年」というのは、自然に「なる」のではなく、「する」のだということを確認して始業式の言葉とします。
平成28年度
平成27年度
平成26年度
平成25年度
|