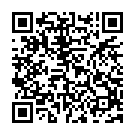いじめ防止基本方針
学校いじめ防止基本方針
兵庫県立洲本高等学校定時制の課程
1 本校の教育方針
本校の教育方針は、校訓の「至誠・勤勉・自治・親和」を原点におき社会の変化に対応できる柔軟性を身につけ、生涯を通して自ら学ぶ態度と豊かな心を培い、自己を生かし、社会の一隅を照らすことができる人づくりを目指すことであり、地域から信頼される学校を目指す教育活動を展開している。同時に、働きながら学ぶ定時制の特性を生かし、地域社会との連携を深め、生命を尊重する心や他者を思いやることができる心豊かな人間性と社会性を持つ生徒を育てることを目指している。
そのために、全ての生徒が安心して学校生活を送り、有意義で充実した様々な活動に取り組むことができるよう、いじめ防止に向けて日常の指導体制を定め、いじめの未然防止を図りながらいじめの早期発見に取り組むとともに、いじめを認知した場合は適切に且つ速やかに解決するための「学校いじめ防止基本方針」(いじめ防止全体計画)を定める。
2 基本的な方向
本校では、社会生活のルールやマナーが守れない生徒も少なくない。善悪の判断が不十分で、他者を誹謗、中傷したり、それをネットに書きこむような生徒、陰口を言ったりする生徒もいる。また、小中学校で不登校であった生徒や、支援を必要とする生徒も在籍していていることからトラブルが発生することもある。一方で、近隣の方々が参加するグラウンドゴルフや体育祭、学校周辺での清掃ボランティアなど地域と交流する活動も積極的に行っている。
ルール違反を繰り返す生徒については、根気よく注意し、毅然とした指導をするとともに、保護者・地域・関係機関・学校が連携することが必要である。生徒と教師が良好な人間関係を保ち、生徒自身がルール違反を認識し、生徒の内心に迫る指導をすることで根本的解決をはかり生徒の成長を目指している。普段から生徒との信頼関係を築きながら規範意識を醸成するとともに他者を思いやる心を育む指導を実践していきたい。
このような現状を踏まえながら生徒指導を行い、いじめを決して起こさないためにも、以下の指導体制を構築し取り組んでいく。
3 いじめ防止の指導体制・組織的対応等
(1)日常の指導体制
いじめ防止等に関する措置を実効的に行うため、管理職を含む複数の教職員、心理等に関する専門的な知識を有する関係者により構成される日常の教育相談 体制、生徒指導体制などの校内組織及び連携する関係機関を別に定める。
別紙1 校内指導体制及び関係機関
また、いじめは教職員や大人が気づきにくいところで行われ、潜在化しやすいことを認識し、教職員が生徒の小さな変化を敏感に察知し、いじめを見逃さず、早期発見のためのチェックリストを別に定める。
別紙2 チェックリスト
(2)未然防止及び早期発見のための指導計画
いじめ防止の観点から、学校教育活動全体を通じて、いじめの防止に資する多様な取り組みを体系的・計画的に行うため、包括的な取り組みの方針、いじめの防止のための取り組み、早期発見の在り方、いじめの対応に係る教職員の資質能力向上を図る校内研修など、年間の指導計画を別に定める。
別紙3 年間指導計画
(3)いじめ発生時の組織的対応
いじめと疑われる情報を把握した場合やいじめを認知した場合は、情報の収集と記録、情報の共有、いじめの事実確認を行い、迅速にいじめの解決に向けた組織的対応を別に定める。
別紙4 組織的対応
4 重大事態への対応
(1)重大事態とは
重大事態とは、「いじめにより生徒の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき」で、いじめを受ける生徒の状況で判断する。本校の場合、たとえば、身体に重大な障害を負った場合、金品等に重大な被害を被った場合などのケースが想定される。
また、「いじめにより生徒が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがある場合と認めるとき」であるが、「相当の期間」については、不登校の定義を踏まえ、年間30日を目安とする。ただし、生徒が一定期間、連続して欠席しているような場合には、適切に調査し、校長が判断する。
また、生徒や保護者からいじめられて重大事態に至ったという申し立てがあったときは、校長が判断し、適切に対応する。
(2)重大事態への対応
校長が重大事態と判断した場合、直ちに、県教育委員会に報告するとともに、校長がリーダーシップを発揮し、学校が主体となって、いじめ対策委員会に専門的知識及び経験を有する外部の専門家である保護司、及び人権擁護委員等を加えた組織で調査し、事態の解決に当たる。
なお、事案によっては、県教育委員会が設置する重大事態調査のための組織に協力し、事態の解決に向けて対応する。
5 その他の留意事項
地域から信頼される学校を目指している本校は、これまでも情報発信に努めてきた。いじめ防止等についても、地域とともに取り組む必要があるため、策定した学校の基本方針については、学校のホームページなどで公開するとともに、学校評議員会や育友会総会、三者面談、家庭訪問などあらゆる機会を利用して保護者や地域に情報発信に努める。
また、いじめ防止等に実効性の高い取り組みを実施するため、学校の基本方針が、実情に即して効果的に機能しているかについて、「いじめ対応チーム」を中心に点検し、必要に応じて見直す。学校の基本方針の見直すに際し、学校全体でいじめの防止に等に取り組む観点から生徒の意見を取り入れるなど、いじめの防止等について生徒の主体的かつ積極的な参加が確保できるよう留意する。また、地域を巻き込んだ学校の基本方針になるように、保護者等地域からの意見を積極的に聴取するように留意する。
|