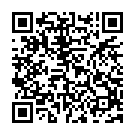学校長より
洲本高等学校 学校長
越田 佳孝
|
 |
今年も生活体験発表の季節がやってきました。6月11日の全校集会での「生活体験文」についての説明から、生活体験発表に向けての指導が始まりました。6月19日が「生活体験文」の提出締め切りです。原稿用紙で4枚以上書くことになっています。説明資料では、話題の見つからない人については、「学校生活について」「仕事について」「働きながら学ぶということについて」等のテーマ毎に、書くべき項目について懇切丁寧なポイントが示されています。さらには、昨年度からは生活体験発表県大会の録画ビデオを観賞して、生活体験発表会について、具体的なイメージを膨らませることができるようにもしています。6月24日はホームルームでの発表、クラス予選。そして、昨日(7月15日)の校内大会です。9月には東播磨・淡路地区大会、そして10月の県大会、さらには12月の全国大会へと続きます。
昨日の校内大会は洲本市市民交流センター(ビバホール)でありました。各クラス予選を通過した11名の生徒が、友だちや学校生活のこと、職場でのことなどの演題で、熱弁をふるいました。生活体験発表大会は、昭和26(1951)年11月、全国大会に先駆けること2年前、兵庫県で「定時制弁論大会」として始まりました。その後、全国大会が始まり、定時制・通信制高校に通う高校生が、学校生活を通して、感じ、学んだ貴重な体験を自らの「ことば」にして発表する長い歴史と伝統を持つ事業となったのです(『兵庫県教育史』374頁)。
開会のあいさつで、私は「生活体験発表会は定時制で学ぶ生徒の成長の物語です」と話しました。「成長」とは、昨日に比べて今日、昨年に比べて今年の「変化」をいいます。これまでの自分に比べて現在の自分の「変化」です。「成長」を実感するためには、まず、昨日の、昨年の、そしてこれまでの自分に向き合わなければなりません。それは決して楽しいことではありません。避けたいことかもしれません。しかし、それを避けている限り「成長」は実感できません。自分のものにならないからです。自分のことを作文にできるだけでも大きな成長です。しかも、クラス大会、校内大会であれ、人前で話すとなるとなおさらです。
今年の校内大会は出場者のレベルが格段に高くなっていました。私が洲本高校定時制に着任して3年、今回が3回目の校内大会ですが、これまでのどの大会よりも確実に発表者のレベルが高いのです。しかも、素晴らしかった。それぞれの発表者が、友だちなどの学校生活、仕事や将来のこと等、自分が「体験したり」「見たり」「聞いたり」「感じたこと」を、自分の「ことば」で話していたからです。そこに伝えたいという「明確な意志」を感じました。そのことが聞く者の姿勢も正したのでしょう。聞いている生徒たちの態度も文句なしによかった。私は、開会のあいさつでの「生活体験発表会は定時制で学ぶ生徒の成長の物語」と言ったのを訂正しなければならないと思いました。「生活体験発表会で教師も成長します」と。それを象徴するのが、教頭の講評の最後の言葉。「ありがとうございました」でした。
兵庫県立洲本高等学校長 越田 佳孝
平成27年度
平成26年度
平成25年度
|