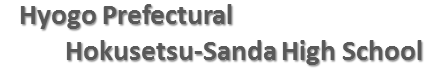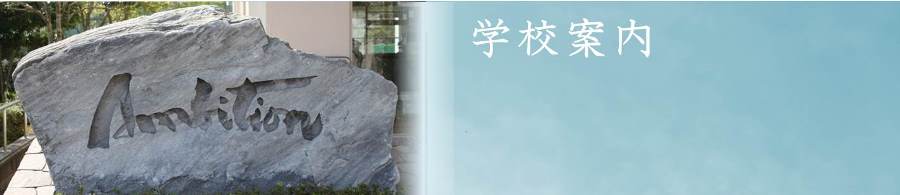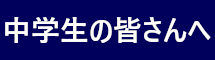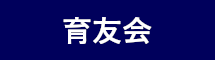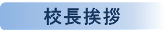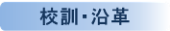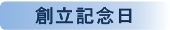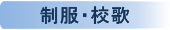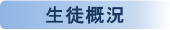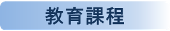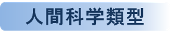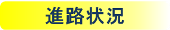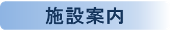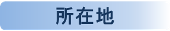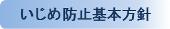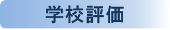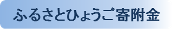進路状況
進路状況

あらゆる機会を通じて自己の生き方や進路に対する自覚を高め、 適性・進路希望に応じた選択学習で学力を向上させます。
※令和6年度は6クラス、令和5年度は5クラス、令和元年度~令和4年度卒業生は6クラス、
平成26年度~平成30年度卒業生は7クラス、平成24年度及び平成25年度は8クラスでした。
※合格者数は現役・浪人を含めた人数です。
※文部科学省所轄外大学校、および同短期大学校はそれぞれ国公立に含みます。
 合格体験記
合格体験記
【A大学(近畿地区私立大学) 総合政策学部】
受験期1年間を振り返ってみると、あまり成績が伸びず、苦労の連続でした。
特に苦労したのは現代文。模試での偏差値は悪く、文系の僕にとって本当に不安でした。問題を解きまくり、文章・設問の形式に慣れることで何とかしようと思い、3年の秋頃からは勉強時間のうち6~7割を国語に当てていました。何とか国語は人並みの点が取れるようになりましたが、その分、英語・世界史で点が思ったほど伸びませんでした。日頃から本や新聞を読むことを怠り、各教科のバランスを考えずに勉強した結果、こうなってしまったのだと後悔しました。
しかし、第一志望には手が届きました。その理由の1つに、1年の頃から予習と小テストを怠らなかったことがあると思います。3年になるまでに基礎力が身に付き、少し余裕を持って受験勉強に取り組むことができました。
【B大学(近畿地区国立大学) 医学部】
私の経験から言えることは、志望校は早めに決めておいた方がいいということと、模試なんて気にしない方がいいということです。判定が悪くても、志望校を変える必要はないと思います。模試なんかに振り回されずに秋ぐらいに過去問を解いて、合格最低点を越えるために作戦を立ててください。
苦手科目の成績を上げるためには、分からないところがでてきたらその都度解決することと、答えを見た問題は必ず自分で解きなおすことです。問題集をする中で、5分考えて分からない問題は答えを見て、次の日に自分で解くようにしていました。
【C大学(近畿地区国立大学) 総合人間学部】
時間を有効に使うことがとても大切です。スキマ時間に勉強する、ということだけではありません。睡眠時間をしっかり確保することもその1つです。睡眠はしっかりとらなければ疲れはとれませんし、記憶も整理されません。僕は最低でも毎日8時間は寝るようにしていました。
気分転換の時間を無駄だと思って削る人もいるかもしれませんが、ダラダラ2時間勉強するよりも、1時間気分転換をして、頭をスッキリさせた後に1時間勉強する方が、しっかり頭に入ることもあり得ます。体調が悪い時は丸1日休んだり、集中力が切れてきたら、休憩をとったりする方が良い結果を生むこともあります。
勉強は積み重ねです。様々な分野の知識が思わぬ形で役に立つことがあります。例えば、家庭科の知識が化学で役に立ったり、中学の理科の知識が地理で役に立ったりするのです。受験勉強は高3になる前から始まっています。