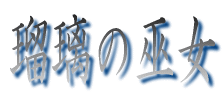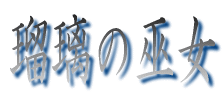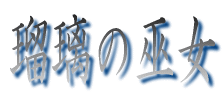

第5話
七 闇の宮 其の壱
中央都、大神殿。天日神の祭壇のさらに奥。ほとんど人の往き来がないそこに、氷付けの少女がいることを知る者は現在の大神殿にただ一人。神主衆の一人、邑辺。彼は、氷付けの少女を前にし、ひざまずいた。
「琉莉夜様、申し訳ございませんッ。老神主が・・・黄泉の手におちました。」
苦渋に満ちた声邑辺は言った。途端、サアッと風が吹き抜けたかと思うと、その風に乗り声が聞こえた。同時に、氷が瑠璃色の光に包まれる。
『邑辺殿、顔を上げてください。』
「いいえ、申し訳ございません。この大神殿は私が護ると豪語いたしましたのに・・・。」
『邑辺殿・・・。』
困ったような響きが声に含まれた。
『邑辺殿、もう止めようがなかったのです。邑辺殿の所為ではありません。それに、最も罪深いのは私です。』
「琉莉夜様?」
沈んだ声と、予想もしていなかった琉莉夜の言葉に、邑辺は顔を上げた。
『本当にこれでいいのか分からないのです。我が父が正しいのか分からなくなってしまいました。私は、皆を騙しているのです。自らの半身までも。』
「琉莉夜様・・・。」
邑辺は言うべき言葉を見つけられずうつむいてしまった。急に瑠璃色の光が弱まり、琉莉夜の声が苦しげになった。
『すみません、今、これ以上は・・・・。この身を拘束している氷に亀裂が生じてしまいます。』
「申し訳ございません、気付きませんでした。・・・失礼いたします。」
邑辺は慌てて立ち上がりその場を去った。
本殿に向かう邑辺の足は重かった。三ヶ月前、邑辺はいつの間にかあの場所へ導かれ、氷付けの少女に出逢った。そして、絶望的な『事実』を聞かされ、選択を迫られた。邑辺
は選んだ、『護る』ことを────。ふと、邑辺の歩みが止まった。
「時矢。何故逝ってしまった?お前なら・・・どちらを選んだのだろうな。」
うつむいた彼の表情は誰にも見えず、呟きが誰かに届くこともなかった。
シトシトと雨が静かに降っている日だった。私の十四の生まれ月。お父様が贈り物を下さった。お父様が贈り物をして下さるなんて初めてだったから、とても嬉しくて、いそいそと包みを開けたの。でも、そこにあったのは巫女装束。
「お父様?」
私が問うと、お父様は満面に笑みを浮かべおっしゃった。
「お前は明日から大神殿に仕えるのだ。そして、天日巫女となれ。」
翌日、私は天巫女になっていた。
「寧禰?寧禰!」
「うーん、莉央ぉ?」
寧禰はようやく目を開けた。目の前にあったのは、心配そうに見下ろす莉央の顔だった。
「寧禰、悪い夢でも見た?」
「えっ、なんで?」
身を起こしながら、寧禰はどきりとした。しかし、笑顔でごまかす。
「別に悪い夢なんて見てないよ。どうして?」
スッと莉央の指が寧禰の頬をなぞった。そして、ぽつり。
「涙のアト。」
寧禰は笑顔を強ばらせた。無意識に指を頬へ伸ばす。莉央は、優しい笑みを浮かべると、「さっきあっちに小川があるの見つけんだ。今のうちに顔洗ってきたら?セヤが心配するよ。」
一枚の布を寧禰へ差し出した。寧禰は、それを受け取ると少し頼りなげに立ち上がった。
「ありがとう、大丈夫だよ。」
少し強ばったままの笑顔で莉央にそう言い、小川の方へ駆けだした。莉央は、そんな寧禰の後ろ姿を心配そうに見送った。
あれから───セヤが一行に加わってから約二ヶ月と半分。闇の宮は、目前にあった。
途中、警戒していた闇の刺客の襲撃はなかったが、その静けさが逆に不気味だった。トキは、『嵐の前のなんとやら』などと言っている。それを思うのはトキだけではない。莉央ももちろんである。勾玉が奪われたことにより、莉央の不安は日に日に募っていた。そして寧禰も何か悩んでいるのか、沈んでいるときが多かった。加えて、寧禰の疲労はかなりのものだった。途中、どこかの里に泊めてもらうこともあったが、ほとんどが野宿の長旅。お嬢様育ちの寧禰にはかなり厳しい旅である。そんな中、ただ一人。セヤは皆をさり気なく気遣い笑顔を絶やさない。それが、唯一の救いであった。
「今日中に闇の宮にはいる。」
朝食の最中、突然言ったのはトキだった。
「えっ、今日?」
余りの突然さに莉央が驚いて聞き返した。確かに、かなり闇の宮に近い場所にいるのだが、いざ今日と言われると全く実感がない。寧禰はもちろん、セヤも少なからず戸惑っている。
「ああ、今日にも闇の宮がある里に入れる。たぶん、昼過ぎには着くだろう。・・・莉央、どうかしたか?」
うつむいている莉央に、トキが訝しげに声を掛けた。莉央は慌てて笑顔を作った。
「なんでもない。ちょっと突然だったから驚いただけで・・・。いよいよ闇の宮かと思うと。」
しん・・・。皆押し黙り、緊張した空気が流れる。
「あの、前から聞いておこうとは思っていたんですが・・・。」
セヤが口を開いた。真剣な面持ちのセヤに視線が集中する。
「旅の目的は何ですか?」
しーん。一瞬の沈黙の後────
「おまえっ、そんっな基本的なことも知らずに今までついてきてたのかっ!?」
トキの怒声が辺りに響き渡った。
「いえ、なんとなく聞きそびれて。それに、私の目的は寧禰を護ることですから、とりあえずはいいかな〜・・・なんて。」
しゅぼっ。これは寧禰が全身を朱に染めた音。
「あっそ。」
トキは思わず立ち上がっていたのだが、ドサッとその場に座った。もう何をいう気もないらしい。一つ深ーいため息を付くと一言言った。
「とにかく、そういうことだ。」
(いよいよ・・・。)
莉央は、指先が冷たくなるのを感じた。指先だけではなく、全身が不思議な寒気に包まれているようだ。一歩一歩が重く、考えずにはいられない。
(いよいよ・・・闇の宮に着く。天日鏡を取り返すことが出来たら、なにか分かるのかな。)
「莉央。ちょっといいですか?」
不意に、後ろから声を掛けられた。トキと前を歩いているはずのセヤだった。セヤが、ちらっと寧禰に視線を送る。寧禰は、ハッとすると、
「先行ってるね。」
そう言って駆けだした。
「なに?」
「歩きながら話しましょうか。」
歩を止めた莉央をセヤが促す。
「さっきトキから、だいたいの話は聞きました。それで、話そうか迷ったんですが・・・。」
セヤにしては珍しく歯切れが悪い。視線を宙に泳がせている。
「セヤ?」
「言うべきことではないかもしれない。でも、知っておくべきだと思うんです。」
「?」
セヤは、一つ深呼吸をすると、きっぱりと言った。
「伝えられている神話が、真実だとは限らない。」
「え?」
「私の里には、『語り絵』を描くために、各地からあらゆる神話の資料が集められているんですが、その中にたった一つだけ、一般に伝えられているものとはあきらかに異なるものがあったんです。それによると、『黄泉闇神は人間を支配しようとした天日神に逆らい、人間を救おうとして封印された。』らしいんです。」
莉央が目を見張った。
「そんな、まさか・・・。」
「もちろん、本当かどうかなんて分かりません。でも、一般に伝えられているものを鵜呑みにするのもどうかと思ったんで。火のないところの煙かもしれませんが・・・。」
莉央は、混乱して言葉が見つからない。今までの『常識』が根底から覆されたのだ、簡単に信じられるはずがない。
「それ・・・トキには言った?」
いいえ、とセヤは首を横に振る。
「一つの可能性として、心の隅に留めておいてください。」
セヤはそう言って微笑んだ。莉央もつられて笑みを浮かべる。ふと、思い出したようにセヤに問いかけた。
「セヤ。初めて会ったときに、『瑠璃色は神話上特別な色』って言ってたけど、どういう意味?」
セヤは、ああ、と笑みを浮かべた。
「天日神様の御道具は全て瑠璃に関係しているんですよ。御道具は三つあるんですが、みなさんが探している天日鏡と、御劔には瑠璃がはめ込まれているんです。もう一つの御道具を知っていますか?」
莉央は首を横に振った。
「もう一つの御道具は、瑠璃の勾玉です。」
「それって・・・。」
琉莉夜がくれた勾玉に違いない。莉央は直感した。
「それ故に、瑠璃色には神力を司る色だと言われています。」
「どうしよう・・・。」
セヤの言葉はもう莉央の耳に届いていなかった。ひやりと、冷たい物が背中に走る。
(どうしよう。そんな大切なものが二つも黄泉にわたってしまった。私のせいだ・・・。)
ぐっと手に力が入る。なにか、正体の分からないものに追われているような不安と危機感が莉央の中に生まれた。
「すっ、すみません。余計なことを言って・・・。」
そんな莉央の様子に気づき、セヤが慌てて謝った。
「ううん、教えてくれてありがとう。」
莉央は、笑みを浮かべたが、それは弱々しい物だった。
「遅れてるね、急ごう。」
莉央はそう言って歩を早めた。しかし、不安は消えない。一歩進むごとに大きくなっていく気がする。
「莉央。」
寧禰の声に、ハッと顔を上げた。いつの間にか、セヤと寧禰が入れ替わっていた。
「莉央、大丈夫だよ。」
「寧禰?」
「不安は誰にでもあるよ。でも、トキ君もセヤ君もいる。それに・・・」
「それに?」
寧禰は、自分を指さすとにっこり笑った。莉央は、一瞬虚をつかれたように目を見開いたが、すぐに笑顔になった。それは、心からの笑顔。
「そうだったね。ありがとう、寧禰。」
「『悩んでるだけじゃ、前へ進めない』って言ったのは莉央だよ。上手く言えないけど、私、その言葉で何かに気付きかけてるの。」
寧禰は、突然うつむくと笑みを陰らせた。
「あのね・・・。私が、莉央と一緒にきたのは」
「琉莉夜に頼まれたからでしょ?」
寧禰は顔を上げ、莉央の瑠璃色の瞳を真っ直ぐ見つめた。何か決心したように口を開く。
「本当は・・・」
「おーい!!村に入るぞ!早く来い!」
トキの声が遠くから響いた。二人は思わず声の方をみた。どうやらかなり遅れてしまったようだ。
「ごめーん!莉央、急ごう。」
「え・・・。」
そう言う寧禰の表情は、さっきまでとは打って変わって笑顔だった。莉央は、寧禰に腕を引っ張られ駆け出す。寧禰の言葉の続きが気になったが、なぜか聞けなかった。
祢の里(ねのさと)─────「闇の里」が転じて「祢の里」になったと言われている
この里には、黄泉闇神を封印した跡を祀った宮がある。それが闇の宮。しかし、闇の宮も言ってみればただの里の神殿である。伝説では、この地で黄泉闇神が封印されたとあるので、その復活を恐れた人々が宮を創り、黄泉闇神を祀ったのである。それにより『闇の宮』と呼ばれるようになったそうだ。そしてもう一つほかの里と違うのは、神殿を護る一族がいるということ。代々その一族の中から神主長が選ばれるらしい。
「意外に活気があるのね。」
里に入り最初に言ったのは莉央だった。
「どういうこと?」
「黄泉闇神が封印された土地とか聞いてたから、人もあんまり住んでいなくて活気のない里かと思ってた。」
莉央の予想に反して、里のあちこちに市が立っており、なかなか賑やかである。
「そんなわけないだろう。西の果てとか言われてるけど、そこに住む人間に変わりがあってたまるか。」
そう言ったのはトキ。
「そうですよ、どこの里もたいていは同じです。」
セヤもにっこりと笑みを浮かべた。
「ほら、さっきから若い女性がちらちらとトキの方を見て何かささやいてますよ。」
がくっ。これはトキが肩を落とした音。
「おまえにも視線が集まってるだろうが。」
「いえいえ、トキに比べれば大したことないですよ。あはははは。」
「はは・・・。」
トキが力無く笑う。美形の宿命として諦めてもらおう。がんばれ、トキ☆
「どうしたの、トキ?急に剣に手のばしちゃって。」
「いや・・・急に何か斬りたい衝動にかられて・・・。」
・・・スミマセンデシタ。
「ねえ、闇の宮ってあっちの大きな建物かな?」
不意に、寧禰が指さした。その指先を追うと、里の外れにそれらしき物が見えた。莉央が疑問の声を上げる。
「普通は里の真ん中にあるよね、神殿って。」
その時─────
「闇の宮だからじゃよ・・・。」
「え・・・?ぎゃあああああ!!!」
突如背後に現れた老婆を見て、莉央と寧禰は悲鳴を上げた。莉央は腰も抜かしている。セヤはすかさず寧禰を後ろへ庇い、トキは剣の柄に手をかける。
「失礼な。せっかく人が親切に教えてやろうというのに。」
そう言う老婆は、ぼさぼさの白髪、しわくちゃの顔(目がどこにあるかすでに分からない)、ぼろをまとったような服を着ており、腰は曲がって、小さい体に合わない長い杖をついていた。初めて見た人間は間違いなく悲鳴を上げるだろう・・・。
「闇の宮は黄泉闇神を封じた場所。それ故、人々は恐れ、離れたところに里をつくったんじゃ。」
「すみませんが、貴女は?」
さすがのセヤも、少しひきつった笑みを浮かべ老婆に問う。
「おぬしら、特別な物を背負うて闇の宮へ行くんじゃな。」
老婆は問いを無視した。が、その言葉に四人はピクッと反応した。
「どんな戦いも、悲しみしか生みはしない。たとえ、光ヶ原を守るという大義名分があってもな。」
「なっ!?」
莉央の叫びを無視して、老婆は続ける。
「何が正しいのか、己がなにをすべきなのか、見極めるのは己自身。強く心を持て、答は己が内にある。支え合える仲間もあるようじゃしな。」
「貴女は・・・?」
老婆はふっと笑みを浮かべ、
「ただの婆じゃ。」
そう言って老婆は去っていった。訳が分からないまま、四人は老婆を見送った。
「行くか・・・。」
トキの呟きで、四人は再び歩き出した。
ずっしりとした厳かな門を前にし、四人は息を呑んだ。今までにない緊張感が皆の間に広がった。みんな黙り込んでしまった。
「入ろう。」
言ったのは莉央。笑顔を浮かべてはいるが、どことなく頼りなげで指先も震えている。その指先が、突然暖かい何かに包まれた。
「寧禰・・・?」
寧禰は、莉央の手をしっかり握り笑顔で言った。
「大丈夫だよ、莉央。さっきのお婆さんも言ってたじゃない。『支えあえる仲間もいる』って。ね?」
その笑顔を見て莉央はほっとした。ずっとそうだった。大神殿に来てから、旅に出てから、何度この笑顔に励まされたか。
(大丈夫。)
莉央は、心の中でそう呟いた。
「よし、行くわよ!」
莉央は、一歩踏み出した。
(大丈夫だ。)
ささやくような小さい声を聞いたような気がして、莉央はハッと上を見上げた。なぜかこっちを見ていたトキと視線がぶつかる。トキの黒い瞳はなぜかとても優しく、莉央は心臓が跳ね上がるのを感じた。
(や・・・やだ。なんで・・・。)
顔が朱くなっていくような感じがして、莉央は慌てて視線を逸らした。
「どうかした、莉央?」
寧禰に訝しげにのぞき込まれて、莉央は慌てて笑顔を作った。
「な、何でもないよ。」
「そお?闇の宮はひっそりしてるんだね、誰かいないのかな?」
「裏の母屋の方じゃない?」
言いながら莉央は辺りを見回し、本殿の脇の大木の下に人影を見つけた。
「あ、あそこに誰かいるみた・・・い。」
莉央は硬直した。寧禰が慌てて莉央の視線を追う。が、寧禰も硬直してしまった。
「どうかしたんです・・・か?」
「なにかあるのか?・・・あ。」
続いてセヤとトキも同様に硬直した。四人の視線の先には─────
大木に身を預けて眠る一人の巫女がいた。透けるような白い肌、腰まで流れる黒髪が、その肌に美しく映える。伏せられた長いまつげ、形のよい唇、整った鼻梁。顔を構成する一つ一つの部分が整っている。時折吹く風が、ふわりとその少女の髪を遊ぶ。一言で言うならば『美』。四人とも、その少女に目を奪われた。空間を静寂が支配する。誰も動かない。否、動けない。が、
「にゃああああああ」
「いったー!!」
その静寂は、突然上から降ってきた小さな猫によってあっさりと破られた。次の瞬間、四人の目が点になった。なぜなら・・・
「ちょお、なにすんねんヒイロ!!痛いやんか!せっかく気持ちよお昼寝しとったのに、目え覚めてしもたわ。どないしてくれんねん。」
四人の思考は混乱していた。少女の言葉は、四人にとって未だかつて聞いたことのない言語だった。第一、華奢な少女の外見とその言語が結びつかない。と、
「あ〜あ、もっかい寝よか・・・あ。」
少女と四人の目があった。その瞬間、
「いらせられませ、大神殿の使者様でいらっしゃいますね。遠いところからようこそいらっしゃいました。」
少女の態度が一変した。言葉遣いから所作に至るまで、完璧な巫女である。が・・・四人がずっこけたのは言うまでもない・・・。
「な・・・なんだその態度の変わり様は!!」
トキのツッコミで少女の態度がまた変わる。
「あーあ、ばれてもたか。お客人には丁寧に応対せいて父さんから言われとったんやけど、ま、しゃーないわな。こらっ、ヒイロのせいやで。」
少女は、子猫の首をつまんで『めっ』をした。トキは言葉を失った。莉央がひきつり笑いを浮かべながら言う。
「あの、貴女は?」
「うちは佳椰。ここの娘で巫女や。で、あんたらの名前は?そやな、まずは綺麗な瑠璃色の目ぇしたお嬢さん。」
少女は人懐っこい笑みを浮かべ、莉央を見た。
「あ・・・莉央です。」
「ふわふわした髪のお嬢さんは?」
「寧禰です。」
「黒い目のかっこええにーちゃん。」
「トキ。」
「にーちゃん美形やけど愛想ないなぁ。んで、文字通り毛色の変わったあんたは?」
「セヤと申します。」
佳椰の勢いに乗せられ、四人は次々に自己紹介(?)をした。
「長旅で疲れたやろ。とりあえずゆっくり休み。っと、その前に・・・。」
佳椰は言葉を切って四人をじろじろと眺め回した。
「えっらい汚れとうな、四人とも。せっかくの美男美女が台無しやで。すぐに準備するから、まずは湯使いぃや。」
佳椰の言葉に、改めて自分たちを見てみると、なるほどかなり汚れている。山の中を通って来たせいか、服はもちろん顔も相当に汚れていた。と、突然佳椰が莉央と寧禰の手首を『がしっ』と掴んだ。
「え?」
莉央と寧禰はわけが分からず、佳椰の顔を凝視する。佳椰はにっこり笑って言った。
「お嬢さん方はこっちや。安心しい、うちが綺麗にしたるから。」
「はあ?」
「どーゆー・・・」
「ほな、行くでえええぇぇぇぇぇぇ〜〜〜〜〜〜〜〜〜!!」
二人の言葉が終わらないうちに、佳椰がいきなり駆けだした。
「ええっ!?ちょっ、ちょとお〜〜〜!!」
莉央と寧禰は引っ張られ(引きずられ)て消えて(?)行った。
「にーちゃんらはあっちな〜。」
キラン☆と三人が消えて(?)行った方向から微かに佳椰の声が聞こえた。
「あ・・・はは、やはり・・・女性は強いですね。」
「あっちてどこだよ。」
取り残されたセヤとトキは呆然となった。そこへ、
「ご案内いたします。」
鈴を転がしたような声音を耳にし、二人は声の方を振り返った。そして、
「え?」
そこに立つ少女を見た二人は、また硬直した───── 。
「思った通りや、やっぱりかわええわあv」
満足そうな声を上げたのは佳椰。佳椰の目の前にいるのは、佳椰と同じ巫女装束に身を包んだ莉央と寧禰であった。
「動きにくい。」
莉央はげんなりして言った。佳椰に連れ去られた(?)莉央と寧禰は裏の母屋とおぼしき建物に通されて、半ば強引に湯を使わされ、あれよあれよという間に巫女装束を着せられた。その時に、二人は、佳椰が闇の宮に仕える一族、白河氏の直系の氏族の娘であることを聞かされた。
「まあまあ、かわええ格好すんのはかわええもんの義務、綺麗な格好すんのは綺麗なもんの義務なんやから。」
「義務って・・・。」
莉央は呆れて言葉が見つからない。佳椰はそんな莉央にもお構いなしで、弾んだ声で、
「お腹空いてない?のど渇いとんちゃう?何か果物でも持ってくるわ。あのおっとこ前のにーちゃんらも着替えがすんだらここに来る手はずになっとうから。」
そう言い、部屋を出ていった。呆然と佳椰を見送った莉央と寧禰は顔を見合わせ、思わずクスッと笑った。
「佳椰って、なんだか外見と中身が一致しないよね。」
「うん。びっくりしちゃった。」
「でもいい子よね。」
「うん、すごくいい子だよ、きっと。」
と、そこへ、
「失礼します。果物をお持ちしました。」
鈴を転がしたような声音に、莉央と寧禰が顔を上げると、果物ののった盆を持って入ってきたのは佳椰だった。
「佳椰っ?」
「早っ!」
佳椰が部屋を出てからほんの少ししか経っていない。しかし、そこに立っていたのは佳椰だった。佳椰はにこっと笑って言葉を続ける。
「殿方ももうすぐいらっしゃると思います。先に召し上がっていて下さい。」
さっきの佳椰とは違う。莉央と寧禰はそう思った。まず第一に言葉遣い、それに雰囲気が違う。さっきまでの激しさがなく、なんだか穏やかだ。
「佳椰?ど、どうしたの?」
「今更言葉遣い直さなくっていいよ。」
戸惑ってそう言った莉央と寧禰に佳椰はにっこりと笑いかけ口を開いた。
「私は・・・。」
と。
「おまちどーさん。果物持ってったでぇ。」
「え?」
果物ののった盆を持って入ってきたのは佳椰だった。二人の少女が並ぶ。にこっと笑った二人の少女は同じ。
「え?え?ええ〜〜〜!?」
莉央と寧禰はわけが分からず二人の少女を交互に見た。透き通った白い肌、形のよい唇、整った鼻梁、長いまつげ。そして、腰まで流れる黒髪。どの部分をとっても同じだった。
「どっ、どーゆーことっ!?」
莉央も寧禰も全く以て理解できずに、口をパクパクさせた。そんな二人をおかしそうに見ながら、後から入ってきた佳椰が口を開く。
「そんなに驚かんでもえーやん。紹介するな、うちの自慢の妹、琥珀。」
ぺこりと琥珀が頭を下げた。
「い、妹!?」
「うちらは双子やねん。冷静に考えたら分かるやろ?」
「あ・・・そうか。」
佳椰に言われ、莉央はほけーとそう言った。確かに、冷静に考えれば分かることなのだが、佳椰も琥珀も稀に見る美少女。一人だけでも印象は強いのに、二人並ばれるとわけが分からなくなってしまう。
「初めまして、琥珀です。驚かせてしまって申し訳ありません。」
琥珀がにこりと微笑み言った。そう言われて改めて見ると、琥珀の瞳はその名が示すとおり美しい琥珀色をしていた。
「あっ、えっと、初めまして、莉央ですっ。」
「寧禰です。」
二人も慌てて自己紹介をする。
「あれ?琥珀は普通の言葉なのね・・・あっ、ごめん!別に佳椰の言葉が変だって言ってるんじゃなくてっ・・・えっと・・・そのぉ・・・」
慌てる寧禰に、佳椰はにっこりと優しい笑みを浮かべながら言う。
「ええって、ええって。初めての人は驚いて当然やから。うちは御祖母様っ子やったからな。御祖母様の言葉遣いを真似たんや。せやから、こんな言葉遣いすんのはうちだけやで。」
「そうなんだ。」
「姉さんは御祖母様が大好きだったものね。」
やんわりと言ったのは琥珀。改めて佳椰と琥珀を見比べると、二人の感じが明らかに違うことに気付く。
佳椰は火。紅く燃えさかる情熱の炎。どんなものでも飲み込んでしまいそうな激しさがあるように思われた。
琥珀は風。穏やかに草原を吹き抜ける一陣の風。その風に触れられた者の心に小さな波を立て、静かに去っていく。そんな不思議な雰囲気が琥珀にはあった。
「で、琥珀。にーちゃんらの着替えは終わったん?」
「うん。もうすぐいらっしゃると思う。トキ様だったかしら?なかなか服を着替えてくださらなかったの。」
そう言いながら果物ののった盆を置いた琥珀の袖口から白い包帯が覗いたのを莉央は見た。よく見ると、歩くときも左足を微かに引きずっている。
「ああ、あの黒い髪のにーちゃんか。どんな風にできあがるか楽しみやなあ♪」
「でもあの服を見た瞬間、トキ様すごく驚いて嫌そうな顔なさったのよ。セヤ様は気に入ってくださったみたいだったけど。」
「ね・・・ねえ、一体どんな服用意したの?」
二人の会話を聞いて、よからぬものを感じたらしい莉央が恐る恐る聞いた。佳椰はにっこり笑うと、ずずいっと莉央に顔を寄せた。
「実はな・・・」
そこへ────
「なんでこんな格好しなきゃならないんだ〜!!!」
・・・トキの絶叫が響き、思わず莉央は声のした方を見る。同時にセヤのなだめるような声が聞こえてきた。姿はまだ見えず、その二つの声が徐々に近づいてくる。
「まあまあ、よく似合ってますよ。」
「冗談じゃないッ!俺は着替える!!」
「旅衣は洗濯中ですよ。何を着るつもりですか?それに、大神殿では毎日着てたんでしょう?」
「それは・・・ッ」
「ほらほら、着きましたよ。観念してくださいね。」
「セヤ、お前楽しんでないかっ?」
「当たり前じゃないですか〜、こんな楽しいこと♪」
「お前ッ!」
「さ、到着!」
嬉しそうな声と共にまずセヤが顔を出す。
「お待たせしました。トキがぐずってしまって。」
「ちょっと待て、俺は子供かっ!」
トキの抗議の声をセヤはさらっと無視する。
「じゃーん、どーですかあ?」
ばばんっと現れたセヤは、『官衣』と呼ばれる神主の正装姿だった。後からセヤに引っ張られるようにして現れたトキも同様だった。白い上衣と薄い水色の袴が不思議と二人に似合っている。
「セヤ君似合ーう!」
まずいちばんに声を上げたのは寧禰だった。続いて、
「やっぱりよう似合っとるわ。うちが睨んだ通りや。さすがうち!二人とも男前が上がったでv」
佳椰が満足そうに言った。
「ありがとうございます。」
にっこりと言ったのはもちろんセヤである。トキはむっつりと黙り込んでいる。
「あかんなー、そんな愛想のない。せっかくの美形が台無しやで?」
「ふ・ざ・け・る・な!」
トキの声には怒気がこもっている。そんなトキを佳椰はキッと睨んだ。余りの鋭さに思わずトキは一歩退く。
「ふざけてなんかないで!さっき莉央と寧禰にも言うたけど、かわええ格好すんのはかわええもんの義務、綺麗な格好すんのは綺麗なもんの義務なんやー!!」
ザッパーン。何故か佳椰の背景に崖と波が見える。パチパチと琥珀が笑顔で拍手をした。
「・・・。」
トキがガックリと肩を落としたのはそれからすぐであった・・・。佳椰は、そんなトキを満足そうな笑みを浮かべた。
「まあ、とりあえずは休み。話はそれからや。」
「話?」
トキが怪訝そうに眉を寄せる。ふと、佳椰の表情が真剣になる。
「あんたらがここへ来た目的についてな。」
ハッと莉央と寧禰は顔を見合わせた。佳椰はその表情のまま言葉を続ける。
「うちははっきりしたしたことは知らんけど、あんたらが特別なもん背負うてここに来たんは何となく分かる。」
莉央、寧禰、トキ、セヤの四人の間に緊張した空気が流れた。しかし、佳椰がふっと微笑んだ瞬間、その空気は微かに和らいだ。佳椰の言葉の後を琥珀が引き継いだ。
「詳しい話は、今夜父からあるはずですから、それまではゆっくり休んでください。ここと隣の部屋は自由に使ってくださいね。」
「そうそう、ゆっくり休みや。」
「ゆっくり休めって言うんなら・・・」
トキの低い声。そして───
「この服なんとかしろー!!」
次の瞬間、絶叫になった・・・。
「トキ?」
トキは、『剣衣』と呼ばれる軽装に着替え、縁側からさっきから雨の降り始めた庭をぼんやりと眺めていた。
「なーんだ、やっぱり着替えちゃったんだ。」
明らかにからかいを含んだ莉央の声に、トキは顔をしかめて振り返った。
「当たり前だ。あんなの着てられるか。」
トキの不機嫌そうな声にくすくす笑いながら、莉央はトキの隣に座った。
あの後、佳椰と琥珀は本殿の方へ手伝いへ戻り、トキは『絶対に着替えてやる!』と二人の後を追って行ったのだ。莉央は寧禰とセヤと話していたのだが、いつまで経ってもトキが戻ってこないのが何故か気になり、トキを探しに来たのだった。
「でも、大神殿ではいつも着てたんでしょ?」
莉央の問いかけにトキは、いいや、と軽く首を横に振った。
「だいたいは剣衣で過ごしてた。官衣は動きにくくてしょうがないからな。着てた時も着崩してたし。」
「似合ってたのにな。」
「うるさい。」
トキがふいっと顔を背けた。照れている風に見えるな、と莉央は思ったが、さすがに口に出すのはやめたようだ。シトシトと雨の降る音だけが辺りに響き渡る。莉央は何も言わず庭を眺めていた。と、突然、トキが言った。
「官衣を着てると、どうしても父さんを思い出す。」
大神殿の神主だった父さんを────
莉央はハッとしてトキを見た。トキは、立てた膝に顔を伏していた。そして、重々しく口を開く。
「父さんは殺された。」
ザアアア─────
不意に雨脚が強くなる。
トウサンハコロサレタ
「・・・・・え?」
トウサンハコロサレタ
「え?」
莉央は、トキの言葉をすぐには理解出来なかった。何と言っていいか分からず、瑠璃の瞳を多く見開き、呆然とトキを見つめた。
「えっ、でも・・・お父さんは病で亡くなられたって・・・。」
長い沈黙の後、やっと莉央はこう言った。トキは顔を上げて遠い目で庭の方を見やった。つられて莉央も庭を見る。
「ああ。確かにそう聞かされた。俺は使いに出てて、七日ぶりに大神殿に帰った途端聞かされたんだ。でもッ!」
バンッ・・・と、トキの拳が板張りの床を叩いた。そして、吐き捨てるように言った言葉は、叫びに近かった。
「遺体も見せてもらえなかった!!すでに埋葬されていて、墓の場所だけ教えられてッ!!父さんはあんなに元気だったのにッ!笑顔で見送ってくれたのにッ!俺はまだ、父さんに何も返してなかったのにッ!!」
「トキ・・・。」
かけるべき言葉が見つけられず、ただ雨の降る庭を見ていた。そんな自分が情けなくて、知らず、握った拳に力が入る。
「俺は、父さんのために来た。」
「え?」
いきなりのトキの言葉に、莉央は思わずトキを見つめた。同時にこちらを見たトキの漆黒の瞳と莉央の瑠璃の瞳がぶつかる。
「この前言った事は本当だ。でも最初は行くつもりはなかった。」
莉央は黙ってトキの瞳を見つめ返す。
「でも、突然神の子が言った。父さんの死の真相を知りたくはないかってな。」
トキは、その時の事を思い出していた。
──── 『父の死は真に病と信じているのですか?』
何故か冷たく響く琉莉夜の声。トキは目を見開いた。
『どういうことだ?』
低い、押し殺した声で琉莉夜に問う。琉莉夜の声は変わらず冷たい響きを帯びている。
『答えを得たいなら、大神殿から発ち、乙女たちと共に西へ行きなさい。』
『どういうことなんだ?お前は何か知っているのかッ!?』
思わず声を荒げて問うトキに、琉莉夜は一言だけ言った。冷厳とした、しかしどこか悲しい声音で。
『西へ。』────
「だから。」
莉央もトキもお互いに視線を外さない。しっかりと視線を合わせ、トキは言の葉を紡ぐ。
「俺は父さんのために、俺自身のために来た。迷ったけど、きちんと伝えておくべきだと思ったから。」
莉央は、しばらく放心したようにトキを見つめていた。が、
「うん。」
ようやく微かに頷いた。トキから視線を外し、雨にけぶる庭へ視線を泳がせながら、自分の中の想いを言葉にしようと言の葉を探す。
「えっと・・・私も自分自身のために来たっていう方が正しいかもしれない。」
「あ?」
トキが莉央の横顔を見つめる。莉央は、庭の方を向いたままゆっくりと言葉を続ける。
「神の子の分身とか言われて、自分がナニモノか分からなくなって、ただ大神殿から逃げたいってだけで来たのかもしれない。ううん、そうなのよ。」
手持ち無沙汰に莉央は指先を玩ぶ。トキは黙って莉央の次の言葉を待っていた。
「そりゃ、春夏秋冬、天日神様に祈りを捧げて、感謝して十六年間生きてきたから、それなりに信仰心はあるけどね。少し・・・黄泉闇神のために命を捨てられるって言った闇の刺客が羨ましかったりして。」
あはは、と莉央は笑ったが、その笑いはどこか自嘲めいていた。
「いいんじゃないか?」
トキの言葉に莉央はハッとした。
「トキ?」
「自分のためでいいんじゃないか?『光ヶ原のため』とか、『誰かのため』とか変に気負うよりは。」
よいせっ、と立ち上がり、トキはポンっと莉央の頭を軽く叩いた。まるで、小さな子供をあやすように。莉央は、トキの手が触れた位置を押さえ、何故か顔が朱に染まるのを感じた。
「ありがとう。」
ポツリと呟いた莉央に、トキはふわりと微笑んだ。その優しい笑顔に莉央は心臓が跳ね上がったのを感じる。
「莉央。」
トキは莉央のそんな様子に気付く様子もない。
「確かに、理由は自分のためだけど、来たからにはちゃんと守るからな。」
「え・・・」
真剣なトキの瞳に見つめられ、莉央は顔がどんどん朱に染まっていく。さっきから、ドキドキと心臓も騒いでいる。
「何か・・今の台詞セヤっぽい。」
そんな自分を誤魔化そうとする莉央の茶化した言葉に、トキがあからさまに顔をしかめた。
「やめろ。あの歯の浮くような台詞にはいつまで経っても慣れん。」
莉央はくすくす笑いながら立ち上がった。そしてふと、庭を見る。
「あ、雨やんだみたい。」
莉央の声にトキは空を見上げた。雲間から、微かに陽の光が漏れていた。
「あれ?雨が降り始めましたね。」
セヤの声に、寧禰は顔を上げた。部屋の扉は閉められているが、耳を澄ますと微かに雨の降る音が聞こえた。
「雨か・・・。」
寧禰は無意識にため息をもらす。セヤは、そんな寧禰を心配そうに見つめた。
『トキを探してくる。』
莉央がそう言って部屋を出て行ってから、寧禰の表情に翳りが差した。セヤは、下手に声をかけるよりは、と沈黙していた。
「セヤ君。」
突然寧禰が言った。寧禰の薄茶色の瞳が、セヤの青い瞳を真っ直ぐ捉えた。
「私、自分で自分を守れるようになりたいの。」
「寧禰?」
セヤが瞳を見開き、珍しく戸惑いの表情を浮かべ寧禰を見た。
ザアアア───── 雨脚が強くなったのか、雨の降る音が大きく響く。
寧禰は、少しうつむき懸命に言葉を探す。
「この前も、その前もそうだった。私だけ足手まといで・・・。もう嫌なの。自分の身は自分で守りたい。」
息もつかずに一気に言う。その瞳の光から、寧禰がいかに本気であるか見て取れた。
「寧禰。」
しばらくの沈黙の後、セヤが穏やかな口調で切り出した。
「寧禰は私が護ります。」
「セヤ君!」
身を乗り出した寧禰をセヤは押しとどめた。そして、柔らかな笑みを浮かべた。
「寧禰、前にも言いましたが、私は寧禰を護るためにここにいるんです。その理由を奪わないでください。」
笑みを浮かべてはいるが、その瞳は真剣そのものである。寧禰は一瞬言葉に詰まりうつむいた。そして、ポツリと呟く。
「でも・・・私を守るためにセヤ君が危ない目に遭うのは嫌なの。」
「寧禰?」
セヤは目を見開いた。
「私のためにセヤ君が傷つくなんて辛い。」
うつむいた寧禰の瞳には、微かに雫が浮かんでいた。
「だから。」
寧禰は顔を上げ、真っ直ぐセヤを見る。
「自分の身は自分で守りたいと思ったんだよ。」
セヤの表情が驚きから微笑みに変わった。そして、寧禰の手を取り、初めてあったときのように手の甲に軽く口づけた。
「セっ、セヤ君!?」
寧禰の顔が一気に朱に染まる。セヤは、寧禰を見つめた。
「約束します。」
「セヤ君?」
「何があっても寧禰を護ります。そして、決して寧禰が悲しんだり、辛い思いをするようなことにはしません。」
セヤは一度言葉を切った。
「必ず」
真剣な瞳で寧禰を射抜く。寧禰は、顔を朱く染めながらも、目をそらせない。
「護ります。」
深く、落ち着いた力強い声がそう告げた。そっとセヤが寧禰の手を放した。それまで厳しかったセヤの表情が和らぐ。かああっと寧禰の顔が今まで以上に朱に染まっていった。
「でっ、でもねっ・・・」
寧禰は朱い顔でセヤを見つめ、必死に想いを言葉にする。
「セヤ君の気持ちは嬉しいけど、こんな風に私だけ誰かに頼るなんてやっぱりずるいよ。私、自分を甘やかしたくないの。」
セヤはまた柔らかく微笑むと、おもむろに自分の耳に手を伸ばした。そして、何かを外す仕草をする。
「?」
寧禰は不思議そうに一連の動作を見ていた。セヤは、その外した何かを寧禰の手に握らせ
た。そっと寧禰が手を開くと、そこには────
「石?」
寧禰は不思議そうにそれを見つめた。
「青い・・・。」
思わず感嘆の息をもらしてしまうような、印象的な青であった。遠い昔、大地が創られる前に在ったような、澄んだ深い海を思わせる、そんな青。
「それを持っていてください。」
「え?」
意味が分からず寧禰はセヤを見る。セヤが笑顔で説明した。
「お守りみたいなものですね。それを使えるかどうかはきっと寧禰次第です。祖父の形見なんですが、何か特別な力があるようなので寧禰の役に立つかもしれません。」
「そんな大切な物、貰えないよ!」
「寧禰。」
セヤは寧禰を仕草で制した。
「私が、寧禰に持っていて欲しいんです。」
優しい、けれど強い静夜の声に、寧禰はまた顔が朱くなるのを感じた。それを隠すように手の平の石に目を落とす。深い青色の石が、キラリと光った。
「きれい・・・。」
寧禰は小さく呟いた。そして、
「ありがとう、セヤ君。」
寧禰が顔を上げると、目の前にセヤの優しい笑顔があった。寧禰も、微かに朱い顔で微笑み返す。ふと、セヤは何かに気付き立ち上がると、カタン、と扉を開けた。
「雨、やんだみたいですね。」
寧禰も立ち上がり空を見上げた。雲間から、微かに陽の光が漏れていた。
──── この時が、四人にとっていちばん幸せな時間だったのかもしれない。