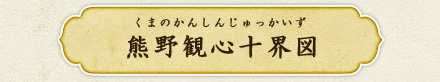この絵は、仏教の宇宙をえがいた曼荼羅(まんだら)で、輪廻(りんね)と悟りの世界を表現しています。
絵の基本は、中央の「心」字と、「老いの坂」、六道の各世界、および仏・菩薩(ぼさつ)・声聞(しょうもん)・縁覚(えんがく)の四つの世界(四聖界:しせいかい)です。この六道と四聖界とをあわせた十の世界を、十界(じっかい)と呼びます。
「心」字は、十界と赤い線によって結ばれ、十界や生死の区切りは鳥居(とりい)によって示されています。これは、人の心や行いによって死後の世界が決まることを暗示しています。
こうした絵画は、熊野比丘尼(くまのびくに)によって絵解きに用いられ、戦国時代から近世にかけて流行しました。

人道とは人間の世界のことで、汚れや苦しみ、無常であふれている、といわれます。恵心僧都(えしんそうず)・源信(げんしん:942~1017)による『往生要集』では、人道は不浄相(ふじょうそう)・苦相(くそう)・無常相(むじょうそう)の三項から説明されています。
この絵の人道は、家族とみられる侍・婦人・童子の三人で象徴されます。一方で、山を上り下りする老若男女によって人の一生を表した「老いの坂」には、生苦・老苦・死苦のほか、雲上の鬼と囚われの人によって病苦が示され、生老病死という四苦が人生に存在することを如実に表現しています(苦相)。さらに墓地で烏や犬に喰われる死体は、人は必ず死ぬということ(無常相)や、人の肉体は汚いものということ(不浄相)を暗示しているようです。
ストーリーでは、四苦八苦(しくはっく)という人道の苦相に注目しました。


畜生道とは、動物や鳥、虫たちの世界のことです。源信の『往生要集』には、畜生道について「強弱相害す(強いものも弱いものも互いに傷つけあう)」という特徴が述べられます。
この絵では、家畜や狩りの対象として身近な、牛や馬、蛇、犬、雄山羊、雄鹿、雄鶏により、畜生道を象徴しています。牛と馬が人間の顔をすることで、人道から畜生道に転生したことを暗示しているのかもしれません。
ストーリーでは、自然界の弱肉強食によって、畜生道の特徴を表現しました。
阿修羅道とは、たえず争いを好む阿修羅たちの世界のことです。『往生要集』は、「(阿修羅は)雷鳴を『天の鼓』(帝釈天が攻めてくる合図)だと思いこんで、怖がってふるえ、神経がとても憔悴する」と述べています。
この絵では、天の鼓を描き、殺し合う武将たちや切腹する侍により、阿修羅道を象徴しています。
ストーリーでは、阿修羅と帝釈天の戦いを、仏教よりも古い時代の神話として採用しました。


餓鬼道とは、つねにお腹をすかせ、のどの乾いた餓鬼たちの世界のことです。『往生要集』では、物惜(お)しみや嫉妬(しっと)する人が餓鬼道に堕ちると述べ、さまざまな種類の餓鬼を記述しています。
この絵では、飯椀(めしわん:ご飯を盛ったお椀)から火がでて食べられない餓鬼、川の水から炎が上がり飲めない餓鬼、果実が燃えて食べられない餓鬼の、3種類を描いています。いずれの餓鬼も、やせ細り、お腹だけつきでた裸の姿です。
ストーリーでは、水を飲めない餓鬼を採用しました。

日本では、十王という十人の冥府の王による裁きで、死後の行き先が決まると考えられました。これは、偽経『十王(じゅうおう)経』や『地蔵十王経』にもとづきます。
この絵では、十王の一人である閻魔王(えんまおう)とともに、生前の行いを映しだす浄玻璃鏡(じょうはりきょう)や、罪の重さをはかる業秤(ごうばかり)などが描かれています。
ストーリーでも、閻魔王が人頭杖(にんずじょう)や浄玻璃鏡とともに活躍します。
『往生要集』には、地中にあるという等活(とうかつ)・黒縄(こくじょう)・衆合(しゅうごう)・叫喚(きょうかん)・大叫喚・焦熱(しょうねつ)・大焦熱・阿鼻(あび)の八大地獄が詳述されています。
この絵では、刀葉林(とうようりん)や「(亡者を)鉄の臼(うす)に入れ鉄の杵(きね)を以て搗(つ)く」という衆合地獄での責め苦、釜ゆでの責め苦などが、火炎とともに描かれています。
ストーリーでは、調理方法とよく似た等活地獄の責め苦を採用しました。

『仏説盂蘭盆(うらぼん)経』には、モッガラーナ尊者(目連:もくれん)が餓鬼道に墜ちた母親を救うため、お釈迦さまから盂蘭盆を教わり、無事に救済する話が記されています。お伽草子(おとぎぞうし)「もくれんの草子」では、母親は黒縄地獄に墜ちて釜ゆでにされていた、と増長・改変されています。
この絵では、「もくれんの草子」とよく一致して、地獄の釜から引きあげられた母親と、涙をぬぐう尊者が描かれています。また、尊者がお釈迦さまに教えを請う場面や、盂蘭盆会もあり、六道(とくに悪道:あくどう)からの救済が大きな主題となっています。
ストーリーでは、まやちゃんが同情して閻魔王にかけあいに行こうとしますが、心配は無用だったようです。


賽の河原は、経典類にはなく、日本で成立した概念とみられます。というのは、『法華経』方便品(ほうべんぼん)に、「童子(どうじ)が戯れに沙(すな)を聚(あつ)め塔を造っても(その功徳は計り知れない)」と説かれており、これを日本で絵画化する場合には、子どもが河原辺で小石を積みあげる図像が多く採用されたため、こうしたイメージが賽の河原の原型となった可能性があるからです。
この絵にも、小石を積む子どもたちと、錫杖(しゃくじょう)を持つ地蔵菩薩(じぞうぼさつ)が描かれています。
ストーリーでは、『地蔵和讃(わさん)』などに登場する鬼も採用しました。

近年、「熊野観心十界図」は念仏(ねんぶつ)の功徳をすすめるとともに、絵解きされたと指摘されています。
この絵では、十界のうちの仏として、来迎(らいごう)する阿弥陀如来(あみだにょらい)を観音(かんのん)・勢至(せいし)などの四菩薩(ぼさつ)とともに描きます。モッガラーナ尊者と対面するお釈迦さまに比べ、阿弥陀来迎はいっそう華々しく描かれており、極楽往生(ごくらくおうじょう)への願いがより強く反映された表現といえます。
ストーリーでも、念仏を唱える尼のもとに阿弥陀如来の来迎する場面を採用しています。