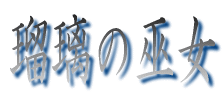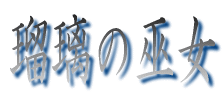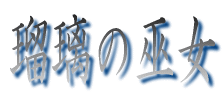

第4話
六 想い 其の壱
闇が全てを支配する黄泉原。その一層闇が深まったところにあるのが黄泉闇神の砦であ
る。その一室で一人の男──侑岐が、なにやらやっている。と、
「兄君!?何をなさってるんですかッ!?」
一人の少女(もちろん、春姫である)が、慌てた様子で部屋に入ってきた。侑岐は、その深紅の瞳に包帯を巻いているところだった。それは、上へ行くことを意味する。
「兄君!傷は癒えたとはいえ、上へ行くのは身体に負担がかかりすぎます!!無茶をしないでください!!お願いですから今しばらく・・・」
「春姫!」
春姫の必死の訴えを侑岐は厳しい声で制した。いつもの優しい諭し方ではない。その気は何とも言えないほどに、鋭い。いつにない兄の態度に春姫はたじろいた。
「春姫、あれから何日経ったと思う?こうしている間にも日の者は近づいている。分かるだろう?」
「ですがっ・・・。」
春姫は言葉を失いうつむいた。小さな手に力がこもる。侑岐は、ポンと春姫の頭を撫でる
と、何も言わずにその横を通り過ぎた。───が、
「お待ちください兄君!」
「春姫?」
「春が参ります。」
春姫の真剣な瞳が侑岐に向けられる。侑岐は言葉が見つからず押し黙る。緊張した空気が
二人の間に流れる。永遠に続くかと思われたその時間は───
しゅぽっ
「たっだいまさよー♪」
何となく間抜けな音と、なんともノーテンキな声によって終わりを告げた。その声の主は、一人の少年である。
「常和!?」
春姫と侑岐が同時に驚きの声を上げた。いつの間にか、部屋の中にもう一人少年がいた。覚えているだろうか?その少年は、日良哉の元に現れたあの少年だ。(最も、あの時の雰囲気とは多少違うようだが・・・)場の空気が分かっていないのか、ずかずかと二人の間に割って入ってくる。
「ただいまさよっ、ちー姫、侑岐兄!聞いてくれさ、成功したんさよ!!思ったより簡単だったさよ。ちょろいさね、権力に狂ったヒトなんて。ん?ちー姫、なんて顔してるさよ。そんなに俺に会いたかったさよ?俺も会いたかったさー!!」
少年は、ガバッと春姫を抱きしめた。瞬間、春姫の顔がひきつった。
「なっ、何をする!離れぬかー!!」
「照れなくてもいいさよ〜♪」
「照れてなどおらぬっ、放せっ!」
・・・言葉遣いが変わっているのにも、本人気付いていない。
「いい加減にせぬか、このチビ!!」
ピタ。
次の瞬間、常和は春姫からふらふらと離れると、座り込み何かブツブツ言い始めた。
「ひどい・・・ひどいさよ、チビなんて・・・。そりゃ、ちー姫より少し小さいさよ?でも、俺だってちー姫と同い年なのにさ・・・。チビ・・・チビ・・・。」
春姫と常和は同じ十四歳である。しかし身長は春姫の方が高く、さっきも常和は春姫を抱きしめていると言うよりは抱きついている感じだった。常和は結構それを気にしているらしく、侑岐と春姫に背を向け、なんとも典型的ないじけ方をしている。春姫はそれをあきれ顔で見る。見かねて侑岐が声をかけた。
「常和、成功したというのは本当か?」
「ああ、もっちろんさよ!」
常和は一気に顔を輝かせた。
「老神主は完全にこっちの手の内さよ。もちろん、これから監視を続けるさよ。でもその前に、一度報告に戻ってきたさよ。」
「そうか、よくやったな。」
侑岐は優しく笑うと、くしゃっと常和の髪を撫でた。常和は嬉しそうに笑う。この少年も春姫と同じに、兄を尊敬し慕っている。
春姫は、そんな二人を少し複雑な表情で見ていた。
「そーいえば二人は何してたさ?」
不意の常和の問いに、グッと春姫と侑岐が答えにつまる。先に口を開いたのは侑岐だった。
「いや、上へ行こうとしたんだが、春姫が行かせてくれなくてな。」
「なっ・・・だって、まだ完全ではないんですよ!いつもの兄君ならともかく、傷が癒えたばかりなんです。父君だってお許しになりません!」
侑岐の言葉に、春姫が声を荒げて言い返す。
「春姫、だから・・・。」
「だから春が参ります。」
「大丈夫だ、心配することはない。」
「春では頼りないというのですかっ?」
「そんなこと言っていないだろう。」
「いいえっ、そう聞こえますっ!」
「春、いい加減に・・・。」
「いいえ!」
「だから・・・」
「いいえ!」
「だから・・・」
「いい・・」
「だあああああ!二人ともいい加減にするさよっ!!!」
不毛な二人の言い合いに、ついに常和が大声を上げて止めた。さすがに春姫も侑岐も黙った。常和は、ただ大げさなだけなのかそれとも肺活量が少ないだけなのか、しばらく肩を上下させながらゼエゼエ言っていたが、落ち着くと言葉を紡いだ。
「俺も一緒に行くさよ。」
「なに?」
「嫌じゃッ!」
侑岐と春姫がほぼ同時に言った。常和はにっこり笑ってさらに言った。
「別にちー姫が頼りないなんて言ってないさよ。どうせ、大神殿に戻るからそのついでさよ。俺も日の者に会ってみたいと思ってたさよ。侑岐兄、大丈夫さ!無理しないでちゃんと身体を治すさ。父様もそうおっしゃると思うさよ?」
しん・・・沈黙が広がる。侑岐が、一つため息をついた。諦めたような、そんなため息だ。
「わかった。」
「えっ・・・。」
「二人で行ってくれるか?」
侑岐が春姫を見下ろした。気が優しくなっているのが分かった。春姫はしばらくうつむいていたが、やがてぎこちなくうなずいた。そして侑岐に背を向けると、
「いってまいります。」
静かにそれだけ言い、さっさと部屋を出ていった。
「ちー姫!待ってくれさよー!」
「常和!」
慌てて後を追おうとした常和を、侑岐は呼び止めた。そして、振り返った常和に長い布に包まれた何かを渡した。ずっしりと重みを持ったそれを見、常和は目を輝かせて侑岐を見た。
「侑岐兄、これって・・・。」
「常和なら、十分使いこなせるはずだ。」
常和は、満面に笑みを浮かべると、
「ありがとうさ、侑岐兄!行って来るさよ!」
しゅぽっ
あの間抜けな音とともに、常和の姿が消えた。と、
バンッ!!
突然侑岐はその拳を手近な壁にぶつけた。その表情は苦渋に満ちている。
「ふがい無いッ・・・」
侑岐の唇から微かにそんな言葉が漏れた。
「私一人役立たずではないかっ!」
強く握りしめた手から紅い雫が流れる。それに構わず、侑岐はさらに手に力を込めた。そ
して、思う。今の自分がいかに幸福かを───────帰る場所があり、待つ者がいる。
自分を『兄』と呼び慕い、必要としてくれる者がいる。日の生を承けていた頃からは考えられない幸福。すべて、闇に救われたから得られたものだ。だから、自分を救って下さった黄泉闇神の為ならば、この身体が朽ち果ててもいいと侑岐は思っていた。それだけに、自分一人が闘えないというのは、侑岐にとって何よりの苦痛である。
『侑岐。愛しい我が息子。』
「闇の御君!」
不意に、どこからともなく声がした。侑岐は咄嗟にひざまずく。
『侑岐、気にするな。それより、“来るべき時”のために、その身を十分に休めよ。』
「・・・闇の御君の御心のままに。」
『侑岐・・・何故我を“父”と呼んでくれないのだ?』
ぐっと、侑岐が答えにつまる。
「恐れ多い・・・。」
聞こえるか聞こえないかの微かな声で呟く。
『いつか、そなたに“父”と呼んでもらえることを願っておる。』
そうして声は消えた。うつむいた侑岐の顔は微かに朱に染まっている。侑岐は立とうともせず、ずっとそこにひざまずいていた。
しゅぽっ
「ちー姫、ちー姫!待ってくれさ〜!」
突然現れた常和が抱えているものを見、春姫は微かに眉をひそめた。その視線に気付き、笑みを浮かべ常和が言った。
「侑岐兄がくれたさよ!」
春姫は、一瞬何とも言えない複雑な表情をし、唇をかみしめた。
「ちー姫?どうしたさ?」
常和の言葉に春姫はハッとすると、扉の方へ身体を向けた。
「ちー姫?」
「なんでもない。それより、ちー姫と呼ぶな。そのふざけた言葉もやめよ。」
「上ではもっとカッコイイさ!」
「答えになってない!」
「まあまあ、ちー姫もホレ直すさよ。」
「もとより何とも思っておらぬわ!それより、ちー姫と呼ぶなというのがわからぬのか!!」
「わかってるよ、春姫。」
常和の口調が変わった。その急な変わり様に、おもわず春姫は一瞬退いてしまった。
「わ、わかっておるならいい。行くぞ。」
「よーし、ちー姫とお出掛けさよー!」
「わかっておらぬではないかー!!」
そんな叫びを残しつつ、二人は光ヶ原へ発ったのだった。
『リオ・・・リ・・オ・・・。』
名を呼ばれた。目の前に広がっていた白い靄の中に、誰かの影が浮かび上がった。
『リオ・・・』
「誰?」
靄は徐々に晴れていき、少女の姿が見えてきた。金糸銀糸に彩られた美しい巫女装束に身を包んだ自分と同じ顔の少女の姿が。莉央は、見覚えのあるその少女の名前を呟いた。
「琉莉夜?」
少女の瑠璃色の瞳には強い光がなく、潤むように揺れていた。何だか尋常ではない琉莉夜の様子に莉央は戸惑った。少女は、その形よい唇をすまなそうに歪めた。
『すみません、莉央。私は・・・貴女を──── ・・・。』
「何?聞こえな・・・っ」
急に風が吹いた。靄が再び濃くなり、視界が閉ざされていく。そして、さっきとは違う声が響いた。
『莉央。』
暖かさを含んだその声に、莉央は自分の耳を疑った。もう、二度と聞くことは無いだろうと思っていた、あの声。莉央は、震える声で呼びかけた。
「かあ・・・さん?」
靄が晴れ、また人の姿が浮かび上がる。間違いない、見間違うはずがない。いつも優しく
微笑んでいたあの顔を─────
「母さんっ!」
莉央は駆けだそうとしたが、何故か足が動かない。否、動けない。
「母さん!!」
莉央は必死に叫んだ。聞こえているのかいないのか、母── 小夜は微かに微笑んだ。と、
小夜の唇が動く。
『莉央、貴女の場所はここにあるの。いつでも帰ってらっしゃい。』
──それは、大神殿に旅立つ前夜、莉央の髪を撫でながら何度も何度も繰り返した言葉。
「母さん!!」
ふわあっ
小夜の足下から、無数の花びらが舞い上がった。小夜は、その花びらを見つめながらとても優しく微笑んでいる。その姿が、だんだんと幼くなっていく。
「母さん・・・?」
やがて、莉央と同じくらいの少女の姿になった。花は、いつの間にか消えていた。そして、上の方から瑠璃色の光が落ちてきた。
ふわり ふわり
ゆっくりと落ちてきたそれは、まるで吸い込まれるように小夜の腕の中に収まった。小夜は、それを愛しそうに抱きしめた。その姿がまた靄に隠されていく。
「母さん?母さん!嫌っ、母さんっ!母さーん!!!」
莉央はもうそれ以外の言葉を見つけられなかった。声を限りに叫んでも、周りにはただ靄
が広がるのみ───
「────── ッ!」
目の前には天井。戸の隙間からは朝の光が射し込んでいる。莉央は褥の上に身を起こすと、夢を見ていたことを悟り、一つため息をついた。
ここは、とある里。あれから三日。山は進むほど険しくなり、旅慣れない莉央と寧禰はもちろん、トキにとっても楽な道のりではなかった。結局、昨日の夕方遅くこの里に着いたのだった。旅人の礼儀に従って里の神殿を訪れると、三人は予想外の歓迎をうけた。もともと、大神殿の人間はどこの里でも歓迎されるものだが、この里は特に陽気な性質らしい。すぐさま歓迎の宴が用意され、飲めや歌えのすごいことになったのだが、疲れきっていた三人は食事もそこそこにすぐに眠ってしまったのだ。ふと莉央は、隣に寝ていたはずの寧禰がいないことに気が付いた。と、
ダダダダダダダダダッ
「莉央っ!起きてる?」
元気な足音とともに、寧禰が飛び込んできた。
「おはよう寧禰。寧禰がそんなに走るなんて珍しいね。なんかあった?」
莉央の問いに寧禰は頬を紅潮させた。
「聞いて、すごいの!今夜からお祭りがあるんだって!感動しちゃった!」
「・・・寧禰、落ち着いて説明して。」
「とにかくすごいの!!莉央も行けばわかるよ。とにかく早く来て!隣に朝餉の用意して下さってるから、食べててね。私、トキ君たたき起こしてくる!!
」
そう言って寧禰は部屋を駆けだしていった。そんな寧禰に呆然としながらも、思わず笑みがこぼれる。
(よかった。元気になったみたい・・・。)
莉央は、ホッと安堵の息をもらした。あの後、闇の刺客に襲われた後、寧禰はずっと沈んだ様子だった。が、この里に着いてからは、そんな様子はなくなった様だった。
莉央が、身支度を整え、朝餉を食していると、廊下から寧禰とトキの声が近づいてきた。
「トキ様、しっかり歩いて下さいませ。」
「だから、その口調は止めろ・・・ふぁ〜」
「トキ様!こんなところで寝てはいけません!」
「・・・。」
「トキ様!」
覚えて下さっているだろうか、(作者忘れかけ/オイ!)トキは寝起きが悪いのだ。寧禰に引っ張られつつ、朝餉の膳についた。
「おはよう、トキ。よく眠れた?」
「目覚めは最悪だったけどな。こんなに早く起こしてなんかあるのか?」
トキが恨みがましい目で寧禰を見た。
「今夜から里のお祭りがあるんだって♪」
寧禰がウキウキとした調子で切り出した。
「莉央、トキ君。この里の名前知ってる?」
「そう言えば、なんだっけ?」
「忘れた。」
「彩の里(あやのさと)だよ。この里で絵の具の原料がよく採れることから里の名がついたんだって。だから、この里では絵の技術が発達して、有名な絵師様も多くでてるらしいの。それでね、この里のお祭りでは里のあちこちに絵が飾られるらしいんだけど、いちばんすごいのは、里の中央に飾られる神話の語り絵なんですって!」
「語り絵ぇ?」
漬け物を食べながら胡散臭そうにトキが聞き返した。
「うん。何十枚もの大きな面が延々と連なってて、その一枚一枚に光ヶ原の創造から八百万の神々の神話まで描かれてるの!朝の散歩ついでに見てきたんだけど、もう、すごかったんだよ!早く二人に見てもらいたくて大急ぎで戻ってきたの!」
「へーえ、見てみたい。」
「でしょ!?早く行こう。トキ君も!」
寧禰は、目を輝かせて話した。その様子はまるで幼い少女のようだ。莉央はその姿を見て、また微笑んだ。が、トキは・・・
「俺はいい・・・・・った!!」
「トキ、行くわよね?」
「・・・っかったよ。」
莉央に脅され(?)トキも渋々うなずいた。
「うっわ〜、すごい・・・。」
「でしょー?」
『語り絵』を見て、思わず言葉を無くした莉央を見ると、寧禰は満足そうにそう言った。『語り絵』は、寧禰が言ったように、光ヶ原の創造から八百万の神々の神話までが描かれている。その線はとても繊細で、生き生きとしている風に見えた。色の使い方もとても美しく、どんな者でも一度は目を奪われるだろう。これだけの物を描くのに一体どれくらいの時間と労力が費やされたのか。ちなみに、この『語り絵』を描く絵師はその年里でいちばんの絵師と認められた者らしい。これだけのものを一人で描くと知り、また莉央と寧禰は驚いた。
「ここに描かれてるの、鏡じゃないか?」
突然、トキが一つの絵を指した。その絵には、一人の巫女が鏡を高く掲げている姿が描かれていた。
「『鏡巫女』の絵だね。」
「『鏡巫女』?」
寧禰の言葉に、莉央が問い返した。寧禰はうなずくと、『鏡巫女』の話を語り始めた。
遠き昔。まだ、神々と人間たちが共に暮らしていた時の話。
一人の娘が、ある神に愛された。やがて娘は身ごもり、女児を授かった。しかし、その子は神の力を強く受け継いでおり、まだ幼い故に力を押さえることが出来ず暴走してしまう。そこで、我らが父神天日神は、その子に一つの鏡を与えた。その鏡を受け取った瞬間、その子は力を収めた。やがてその子は美しい娘に成長し、自らの力を人々のために役立てた。
「で、その子は『鏡神子』って呼ばれるようになった。『神の子』と書いて『みこ』ね。この子は初代の天日巫女様になったの。その時、『神子』が転じて『巫女』になったって伝えられてるんだよ。」
「『神の子』か・・・。」
ぽつりと莉央が呟いた。今朝の夢を思い返す。あの瑠璃の光は自分なのだろうか?自分は何者なのか・・・。最近、そんなことばかり考えている自分がいることに莉央は気付いていた。
「莉央?莉央!」
「えっあっ、ごめん。」
寧禰に肩を揺すられ、莉央はハッとする。
「莉央、どうしたの?」
寧禰が心配そうにのぞき込んできた。莉央はなんでもないと首を振った。なおも心配そうな寧禰に、莉央は大丈夫だからと笑いかけた。寧禰は、まだ少し心配そうにしていたが、次の絵へと視線を移していった。
「本当にすごいよね・・・。」
「気に入っていただけましたか?」
不意に後ろから声をかけられた。弾かれるように後ろを振り返ると、一人の青年が立っていた。
(気配を感じなかった・・・。)
トキは密かに眉根を寄せた。その青年は、服装から見るに里の青年である。が、その瞳は青。そしてその髪は薄い碧に見えた。清潔そうな白の中衣と下衣に、その瞳より少し薄い青の上衣。そして、その青に朱色の帯がとても鮮やかに映える。青年は、トキにも劣らぬ端正な顔立ちで、大神殿へ行けば間違いなく巫女たちが騒ぎ立てるだろう。青年はにっこり笑いながら三人に近づいてきた。
「大神殿の方々ですね。『語り絵』をご覧になるのは初めてでいらっしゃいますか?」
「え・・・はい。貴方は?」
莉央が警戒しつつ答えた。青年はまたにっこりと笑みを浮かべ、寧禰に近づくと────
「初めまして。私は静夜(せや)と申します。以後お見知りおき下さい。」
そう言って寧禰の手を取り、手の甲に口づけた。寧禰はもちろん莉央もトキも目がテンになってしまった。しかし、当の本人である静夜は涼しい顔である。
「き・・・きゃっ。」
一瞬遅れて寧禰は短く叫ぶと手を引っ込めようとした。その顔は朱に染まっている。だが、静夜の力は強く、ふりほどけない。静夜は、寧禰の手を取ったまま言葉を続ける。
「気軽に『セヤ』もしくは『セーちゃん』と呼んでください。」
「あの・・・。」
寧禰は困り果てて、莉央の方を見た。その瞳は潤み、『莉央助けて!』と暗に語っている。一連のセヤの行動に呆然としていた莉央だったが、ハッと我に返ると素早く寧禰のもう片方の腕を引き寄せ背後へかばった。トキは一歩下がったところから傍観を決め込んでいた。
「初対面の女性に対して失礼なんじゃないの?」
莉央は、セヤをキッと睨み付けた。が、セヤは全く動じる様子もなく笑みを浮かべたまま言う。
「すみません、驚かせてしまいましたね。私の絵を気に入っていただいたようでしたので、つい嬉しくて。」
「私の絵って・・・、もしかして貴方が『語り絵』を描いたの!?」
莉央の後ろに隠れていた寧禰が思わず一歩出る。セヤは笑顔のまま頷いた。
「うそ・・・。」
莉央も寧禰も言葉を失ってしまった。セヤはどう見ても十七〜十八歳。『里いちばんの絵師』と聞いていたので、白髪頭(もしくは禿頭)の老人を想像していたのだ。
「驚かれましたか?まあ、無理もないですね。私は、まだ十六ですから。でも、通常でも四十歳前後の方が普通なんですよ。」
十六という年齢を聞き、また驚いた。特に、莉央は自分と同い年だというのが信じられず、何度も絵とセヤを交互に見た。セヤは、寧禰の方へ向き直った。
「自分の絵を気に入られるのは嬉しいですから。特に、貴女のような可愛らしいお嬢さんだと。」
「えっ・・・。」
セヤは寧禰に微笑みかける。寧禰の顔が見る見るうちに朱に染まっていった。セヤは、寧禰に近づくと、
「よろしければ、他の絵もご案内しますが。」
と、手を取った。寧禰の顔がさらに赤くなる。どうしていいか分からず、視線を泳がせる。
「あ・・・莉央!莉央も一緒よね!?」
寧禰が、礼の潤んだ瞳で莉央を見上げた。その表情はかなり必死である。
「うん、もちろん。」
莉央が慌てて頷いた。セヤは、苦笑を浮かべつつ寧禰を見下ろす。
「そうですね。できれば貴女と二人がよかったのですが・・・。」
「ええっ!?」
寧禰はもう全身を朱に染めている。
「そういえば、まだお名前をお聞きしてなかったですね。教えていただけますか?」
「寧禰・・です。」
寧禰の声はか細く消え入りそうだった。顔もうつむき加減になっている。
「可愛いお名前ですね。貴女にとても似合っていますよ。」
「あ・・・ありがとう・・・ございます。」
言いながら、寧禰は完全にうつむいてしまった。セヤはにこにこ笑いながら、今度は莉央へ視線を向けた。
「貴女のお名前も教えていただけますか?」
「莉央です。」
ふと、セヤの目が興味深そうに莉央を捉えた。
「あの・・・?」
「ああ、すみません。素敵な色の瞳ですね。」
「は?」
「知っていますか?瑠璃色というのは神話上特別な色なんですよ。」
ぴくっと、思わず莉央はセヤの言葉に反応した。『神話』──── 今の自分たちに最も
関わりのある物。莉央は聞き返そうとしたが、セヤはすでにトキへと視線を移していた。
「貴方は?」
「トキ。」
トキは興味ないように短く言った。セヤはにこにこ笑いながらトキに迫り始めた。
「もちろん貴方もご一緒されますよね?」
「いや、俺は遠慮しておく。」
「何故?」
「何故って・・・面倒くさい。」
「そう言わずに。絵はお嫌いですか?」
「そういうわけじゃないが。」
「だったら、是非。それとも・・・・・私が気に入らないんですか?」
「は?」
「そうなんですね・・・。」
セヤは伏し目がちにうつむいた。突然のことに、トキは戸惑った。
「べ、別にお前を気に入らないとかそんなんじゃない。」
「でも・・・。」
セヤは、うつむいたままである。青い瞳には涙まで浮かんでいる。トキはさらに戸惑った。
「あ・・・あのなぁ。」
「いいんです。そういうことなら・・・・」
セヤの長めのまつげが震え、雫がポタリ・・・。莉央と寧禰が『じとー』と、トキを見た。
「────── ッ!!分かった、分かったから。行ったらいいんだろ!!」
「決まりですね。」
トキが叫んだ瞬間、セヤが笑顔になった。その顔には涙の跡すらない。
「では、行きましょうか。」
にっこりと爽やかな笑顔で、皆を促す。
「おっ・・・おまえっ・・・なんっ・・・!!」
トキはあまりのことに言葉が見つからない。セヤは極上の笑みを浮かべている。寧禰は呆然とし、莉央は必死に笑いをこらえている。
「はめられたね、トキ。」
「笑うな!!」
トキの顔は怒りで赤くなっている。が、莉央は急にセヤに親しみを感じた。
「やるわね、トキをやりこめるなんて。えっと、セヤくんだっけ?」
「『セヤ』でいいですよ。私も、『寧禰』、『莉央』、『トキ』とお呼びしてもいいですか?」
「ええ、もちろん。それから、敬語もいらないよ。」
莉央は言ったが、セヤは、
「よかった。あ、でも、この言葉遣いは癖になってしまってるんで、気にしないで下さい。では、行きましょうか。」
と、三人を促した。
「あ・・・その前に・・・手を・・・。」
セヤが歩き出そうとしたとき、寧禰が慌てて言った。そう、セヤはさっきからずっと寧禰の手を取ったままだったのだ。
「ああ、このままでは駄目ですか?」
セヤの問いに寧禰は首を激しくを縦に振った。セヤは、少し残念そうに寧禰の手を放した。が、ホッとしている寧禰に、笑顔に戻ったセヤが、
「恋人はいますか?」
と、とんでもない質問をした。これには莉央もトキもギョッとする。質問をされた寧禰は、顔を真っ赤にしたまま何も言えないでいる。
「いないんですか?」
その問いに寧禰は微かに首を縦に振った。さらにセヤは質問する。
「好きな方は?」
「い・・・いません。」
「よかった。」
寧禰の答えに、セヤは柔らかい、安堵の笑みを浮かべた。その笑顔に、寧禰の心臓が跳ね上がる。セヤは、ひざまずくと恭しく寧禰の手を取り、自分の額へ当てた。サラリと碧い髪が揺れる。
「では、貴女に恋する者の名として、私の名前を覚えておいてください。」
「・・・・・。」
寧禰はもう言葉にならない。全身を真っ赤にして、立ちつくしてしまった。その様子を莉央とトキはただただ呆然と見ていた。トキはすでに諦めたような顔をしている。セヤは、もう一度寧禰に笑いかけ、立ち上がった。そして、莉央とトキの方へ向き直ると、
「さあ、行きましょう。」
と、意気揚々と歩き出した。それと寧禰が湯気を出してその場にへたり込んだのはほぼ同時であった。
「あ!セヤ!」
一人の少女がセヤを呼び止めた。
「セヤ、今夜の相手は決まったの?」
「いや、まだです。」
「だったら私と・・・。」
「すみません、誘いたい方がいるので。」
「え・・・そっか、じゃあしょうがないね。じゃ、後で!」
そして少女はセヤのすぐ横にいた莉央と寧禰を睨み付けて去っていった。
──── セヤに絵を案内してもらっている間、何度もあった光景である──────
セヤはやはりその容姿からか、里の少女たちに人気がある。いや、里の人間全てという方が正しいかもしれない。少女たちは、セヤの『今夜の相手』になるべく一世一代の勇気を振り絞って声をかけるのだが、セヤはそれを笑顔でかわしていた。
「ねえ、『今夜の相手』って何のこと?」
何人目かの少女が去っていったとき、莉央がセヤに尋ねた。
「今夜祭りがあるのはご存じですよね。その中に男女で踊る伝統の舞踊があるんですが、その時に恋う異性を誘うのが習いなんです。」
「へえ。もしかして、セヤの誘いたい相手って、寧禰?」
莉央の言葉にセヤがにっこりと頷いた。寧禰の顔がまた朱に染まっていく。
「祭りには参加されますよね?」
「できればそうしたいけど・・・。」
莉央は曖昧に答える。なにしろ、先を急ぐ旅路のだ。ゆっくり祭りなどに参加していられないだろう。が、
「いいんじゃないか。」
トキがそう言った。莉央と寧禰は驚いてトキを見た。
「近道通ってきたから、少しぐらいゆっくりしても大丈夫だ。」
「近道?」
「山の中通ってきただろ?普通の街道歩いてたら、この里まで十日はかかったはずだ。」
ピタ。莉央の動きと思考が一瞬止まった。そして、指を折って歩いてきた日数を数えてみた。
「トキ、確か四日かかったのよね?四日。普通十日かかる道程を四日で・・・。」
「ああ。」
「馬鹿あっ!!!!!」
「ぐはっ・・・。」
しれっと頷いたトキのみぞおちに莉央の拳が鮮やかに決まった。そして、うずくまったトキを見下ろしながら一気にまくし立てる。
「普通の街道があるなら早く言いなさいよ!!あんな険しい山通らなくてもよかったんじゃない!野宿だってしなくてすんだはずよ!?あんた一人ならともかく、旅慣れない私たちにあんなとこ歩かせるなあ!!」
「い・・・急ぐんだろ。」
トキは、ようよう立ち上がってみぞおちをさすりながら莉央を見た。と、
「仲がいいんですね。」
「は?」
セヤのほんわかとした呟きに莉央とトキが同時に聞き返した。セヤは笑みを浮かべさらに言った。
「仲がいいんですね。見ていてほのぼのします。」
「そうかな・・・?」
これは寧禰の呟き。
「『ほのぼの』・・・?」
「こういうのは普通『仲がいい』とは言わないだろう。」
莉央もトキも呆れ顔だ。が、セヤはにこにこと笑みを浮かべたまま言う。
「少なくとも私にはそう見えます。それに、美男美女でなかなかお似合いだと思うんですが・・・」
「はあっ!?」
これはトキと莉央の叫び。莉央の頬は微かに朱に染まっている風に見える。トキはもう呆れ返っている。
「祭りに参加されるのだったら、舞踊に参加するといいですよ。『語り絵』が飾ってあった広場に篝火が焚かれるんです。是非参加してください。みんなきっと喜びます。」
セヤはもう一度にっこり笑う。そしてさり気にその視線を寧禰へ向けた。その視線を感じた寧禰は慌ててうつむく。ふと、セヤが思い出したように言った。
「ああ、トキが参加するとなると、ちょっとした騒ぎになるかもしれないですね。女性は強いですから。」
「は?」
─── その日の夜、このセヤの言葉が現実となったりするのでアル。
其の弐へ急げ!!(><)