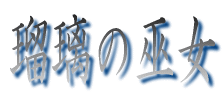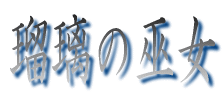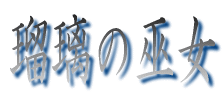

第3話
五 波紋
シャーン
「悪しき闇から我々を守り、新しき陽をお与えくださった天の父に祈りを────。」
夜が明けた。神聖な鐘の音が大神殿に響き渡った。同時刻、各村・里の神殿でも鐘が響いているはずだ。天原の天日神に感謝の祈りを捧げることから光ヶ原の一日は始まる。特に、今日のように新月の夜が明けた朝は、いつもより長く祈りを捧げるのだ。
「今日も尊き父の光の加護があらんことを。」
シャーン
もう一度鐘の音が響き、祈りの終わりを知らせる。各部屋から続々と人が出てきた。今日も、一日が始まる。
ピピピ・・・チチチ・・・
小鳥がさえずる爽やかな朝。早朝の空気は澄み切っていて、何とも心地よい。が、そんな爽やかな朝にそぐわない不穏な空気が、大神殿の一角に渦巻いていた。
「よろしいでしょうか?」
一気に空気が張りつめ、緊張が満ちる。
バサバサッ
木の梢でさえずっていた小鳥が数羽飛び立っていく。その空気を察したかのように──。
ここは、大神殿内にある『司政殿』と称される建物の一室だ。書いて字のごとく、政を司る建物である。朝の祈りが終わった後、老神主と神主衆たちは『朝議』と呼ばれる──
これまたその字の通り───朝の会議を行うために司政殿に集まる。現在の老神主と神主
衆は決して仲がいいとは言えない。はっきり言って仲が悪い。しかし、老神主も神主衆もさすがに酸いも甘いも噛み分けた老人・・・失礼。大人であるから、あからさまな事はしない。今までも、不気味ながらもまずまずの関係を保ってきた。が、この日の朝議で神主衆のトップである嵯峨が動きを見せた。
「では、他に何かありますかな?」
朝議の最後にそう言ったのは、現老神主日良哉。その表情は、穏やかだがどこか油断ならず、顔に刻まれた深いしわには何とも言えない貫禄がある。
「一つよろしいでしょうか?日良哉殿。」
いつもはここでは何も言わず、後でさり気なく嫌味を言うはずの嵯峨が口を開いた。
瞬間、一同の間に、えもいわれぬ緊張感が満ちあふれた。日良哉は、一瞬ピクッと眉をつり上げた。が、すぐに穏やかな表情に戻る。
「では、嵯峨殿。」
嵯峨は、チラッと日良哉の方を見ると、なんとも嫌味な口調で話し始めた。
「確か・・・一月ほど前に、天日巫女の命だとかおっしゃって、田舎から巫女を呼ばれましたなあ?」
「ええ。天日巫女様の託宣により、召した巫女のことですな。」
「そうでしたか。私はまた日良哉殿の独断かと・・・おっと失礼。失言でしたね。」
「いいえ、お気になさらず。いつもの事じゃないですか。」
「これはこれは、手厳しいですな。はっはっはっはっは。(このくそジジイがッ)」
「おや、失礼でしたかな?ふぉっふぉっふぉっふぉっふぉ。(この若造がッ)」
ビシビシビシッ───── 。
どこからともなくそんな音が聞こえてくる気がする。その場にいた全員が、二人の間に稲妻が走ったような錯覚を覚えた。ちなみにカッコ内はそれぞれの心の声である。ひとしきり笑い終わった後、一息ついて嵯峨が言葉を紡ぐ。
「それで、その巫女なんですが・・・、今朝から姿が見えないと騒いでいる者がいましてな。」
「ほう?」
日良哉の目が険しく光る。嵯峨は、心のなかでほくそ笑みながら続ける。
「その巫女・・・確か次代の天日巫女だと言っておられましたな、日良哉殿?」
「ええ。そうでしたな。」
緊張がさらに広がる。
「もし、その巫女が修行に耐えきれず逃げたとすれば─────」
『どう責任をとられるおつもりか。』
という、嵯峨の言葉を、やんわりと遮る者がいた。
「嵯峨殿。その巫女なら、闇の宮へ使いに行かせました。」
それは、邑辺という神主だった。嵯峨は、邑辺を鋭く睨み付けた。その目に宿っている光は、間違いなく憎悪。邑辺は、それに動じず笑顔で続ける。
「闇の宮への使いは、天日巫女になる者の義務。新月の夜に旅立つのが古よりの習い。昨晩、供をする巫女が出立を告げに来たじゃありませんか。お忘れですか?日良哉殿。」
そう言って、笑顔を日良哉へむけた。
「え・・・ええ、そうでしたな。昨夜は雑務に追われていた故、うっかりと忘れていました。すみませんな、嵯峨殿。」
日良哉は、多少動揺した様子だったが、すぐにいつもの調子に戻ると嵯峨に笑顔をむけた。
「それは、真でございましょうな。」
唇を噛みしめて嵯峨が問う。その問いには、邑辺が答えた。
「ええ、間違いありませんよ。私も一緒にいましたから。」
嵯峨は、さらにきつく唇を噛んだ。日良哉は、そんな嵯峨をチラッと見ると、勝ち誇った笑顔で問う。
「嵯峨殿、他には?」
「いいえ、ございませんッ。」
嵯峨の表情は、悔しさに満ちていた。日良哉は、それを満足そうに見、ゆっくりと言った。
「では、本日の朝議はこれまで。今日も尊き父の光の加護があらんことを。」
真っ先に立ち上がったのは嵯峨だった。
バンッ
嵯峨は、乱暴に扉を開け出て行こうとした。が、ふと止まると、出て行こうとした姿勢のまま日良哉に話しかけた。
「日良哉殿、噂をご存じですか?」
「噂?」
日良哉が、眉をつり上げる。嵯峨が言う噂なのだから、決していい噂でないことは察しがつく。
「ええ。最近、この大神殿にも不埒な輩がいるようで、『現天日巫女はすでに亡きに等しく、老神主の日良哉殿が思いのままに司政を執り行っている。』という噂を小耳にはさみましてな。」
「それは心外。天日巫女様あってこその大神殿ではないですか。わたしなど、一介の神主に過ぎませんよ。そうそう、私もつまらぬ噂を耳にしましたよ。」
今度は嵯峨が眉をつり上げる。空気がピリピリと震えているのが感じられる。
「『嵯峨殿は、天日神様への信仰をおろそかにしている。巫女たちのことも快く思っていない』と・・・。まあ、下らぬ噂ですな。お互いに。」
「そうですな・・・。失礼しますッ。」
嵯峨は、吐き捨てるようにそう言うと、部屋を出ていった。その後を、嵯峨派の神主衆、佐久路と豊衣が追う。後に残ったのは、日良哉、邑辺、そして神主衆の中でいちばん若い(と言っても四十歳だが)久貴。次に立ち上がったのは日良哉だった。邑辺の横を通る瞬間、相手にだけ聞こえる声量で呟く。
「借りを作ったな。」
「何の事だか分かりかねますな。」
「喰えない奴よ。」
トン トン トン
静かな足音と共に、日良哉は出て行った。
「ふー。今日はいつにもましてすごい緊張感でしたねぇ。」
さっきまでのピリピリした空気に息を詰まらせていた久貴が、大きなため息をつく。邑辺はそれに笑って答える。
「嵯峨殿は、日良哉殿を失脚させる絶好の機会と意気揚々だったからのう。嵯峨殿も日良哉殿も困ったものよ。己の利しか考えておらん。いつからそんな神主ばかりになったのやら。」
「邑辺殿・・・。」
邑辺は、嵯峨に次ぐ───もしかしたら嵯峨以上の───実力を持っていると言われてい
る。若い神主の中には、聡明な邑辺を慕う者も少なくはない。久貴もそんな一人だ。
「久貴殿。『神殿』とは何か?」
「は?」
突然の邑辺の問いに、久貴は戸惑った。
「え・・・ええと・・・『神殿』とは・・・」
上手く言葉が見つからず、久貴は余計に慌てる。そんな久貴を見て、邑辺は優しく笑った。
「難しいか?私もこの問いには上手く答える事ができなかった。」
「え?」
邑辺は、ふっ・・・と、遠い目をした。昔を懐かしむような、そんな目だった。
「神殿とは、すなわち『かみどの』。神の住まわるる神聖な殿。単純だろう?」
「『かみどの』・・・。」
「単純すぎて、人は見過ごしてしまうのか。神殿は、本来人の権力が動く場所ではない。それなのに・・・。どうなるのだろうな、これからの『かみどの』は。」
邑辺は、静かに目を伏せた。穏やかな沈黙が流れる。その沈黙に耐えきれず、久貴が口を開く。
「あの・・・邑辺殿に、その問いをされた方って・・・?」
邑辺は目を開けると、また、遠い目をした。そして、静かに言の葉を紡ぐ。
「時矢といって、とても優秀な神主だった。なにより、大神殿のことを考え、光ヶ原を思っていた。本当に・・・、すごい奴だったよ。」
そして、再び目を閉じた。久貴は、それ以上何も言えなかった。さっきとは全然違う心地よい穏やかな空気が流れる。
ピピピ・・・チチチ・・・
木の梢に小鳥が戻ってきた。
パチパチ パチパチ
あっという間に時は経ち、今は夜。とある山中で少し小さくなった焚き火を挟み、莉央とトキは座っていた。莉央の隣では、寧禰がスヤスヤと寝息を立てて眠っている。さっきまでざわめいていた風もやんでいた。ふと上を見上げ、夜空を仰ぎ見ながらトキはポツリと言った。
「俺は、戦火で焼け出されたところを、大神殿の神主をしていた父さんに拾われたんだ。」
「その前は?どこの村に住んでたの?」
莉央の問いに、トキはただ笑った。自嘲的に。そして、どこか寂しそうに。
「覚えてない。」
「え?」
「まあ、聞けって。俺の記憶は父さんに拾われた時から始まったんだ。」
トキは、静かに、そしてゆっくりと言葉を紡ぎ出す。自身の過去を思い出しながら。
気が付いたら、高い天井を見上げてた。見たこともない綺麗な所で、強い木の香りがした。俺は、白い清潔そうな褥の上に寝かされてた。
(ここは・・・?)
頭の中がぼんやりして、記憶がはっきりしない。まるで靄がかかったみたいに。
(僕・・・どうしたんだっけ?・・・喉、渇いた)
天井を見上げたまま、思い出そうとした。でも、記憶にかかる靄が邪魔をした。思い出そうとすればする程、分からなくなってきて、わけの分からない苦しさが胸にせり上がってきた。どこかで、思い出すことを拒否してるみたいだった。だからもう思い出そうとするのはやめた。そのまま、ぼーっと天井を眺めてたら、戸が開く音がして、誰か入って来た。
それが──── それが父さんだった。
トキは、一度言葉を切り目を伏せた。その時、莉央が驚きを含んだ声でポツリと呟いた。
「『僕』!?トキが・・・『僕』!?」
トキは目を開けると、呆れたように莉央を見た。
「お前・・・何聞いてたんだ?」
「えー?だって・・・つい。」
「話すのやめた。」
「えーーッ!・・・ととっ」
思わず大声をあげた莉央は、慌てて隣の寧禰を見た。寧禰は、相変わらずスヤスヤと眠っている。莉央はほっと安堵の息をもらすと、キッとトキに鋭い視線を向けた。
「今更やめたは通用しないわよ。もうフザケないから話してよ。」
トキは、ため息を一つつくと、小さくなった焚き火に木をくべながら言の葉を探し始めた。
「おお、気が付いたか。よかった。気分はどうかな?」
入ってきたのは、とても優しそうな人だった。ぼんやりとした意識の中で、その人に問お
うとした。でも────
『ここはどこ?』
開いた口から、声は出なかった。その人がふと顔をしかめる。
「口が渇いているのか?水を持ってきたから飲むといい。」
その人の手が、背中に回された。とても大きな、あったかい手だったのを今も覚えてる。
のどが酷く渇いてたから、急いで水が入った木の器に口を付けた。だが・・・
「ごほっ・・・ゴホッゴホッ!」
最初の一口を飲んだ途端、むせた。
「急ぐことはは無い。ゆっくり飲めばいい。」
その人は、背中を優しく撫でてくれた。今度は、ゆっくりのどを潤した。きっと、久しぶりに飲む水だったんだろうな。一滴残らず飲み干した。器から顔を上げ、礼を言うために口を開いた。でも、やはり。
『ありがとうございます。』
声は出なかった。
「・・・!?・・・!・・・!!」
何度口を動かしても同じ事だった。なんだかすごく怖くなって必死に声を出そうとしたけど、どうやっても出なかった。悔しくて、小さい拳を床に打ち付けた。それでも足りなく
て、もう一度手を振り上げた。でも──── 次の瞬間、
その人の腕の中にすっぽり収ま ってた。とても・・・とても暖かかった。
「可哀相に。よっぽど怖い目に遭ったのだろう。でも、もう大丈夫だよ。ここは大神殿だ。何も怖いことなど無い。」
背中をポンポンと優しく叩きながらその人は言った。でも俺は、『大神殿』と聞いた瞬間、思わずその腕から逃れたんだ。どうしてって・・・分からない。なんだかよく分からなかったけど、『大神殿』って言葉に畏怖の念を感じたんだ。それでも、その人は優しく笑ってくれた。よく見ると、その人は神主の服装をしていた。
「そう言えば肩を怪我しておったが、痛くはないか?」
「・・・?・・・!!」
言われた瞬間、痛みを自覚した。その人は、そんな俺を見てまた微笑んだ。
「さあ、包帯を代えてやろう。」
それから、薬を塗ったり、包帯を代えたりしてくれた。不安や、わけの分からない苦しさはあったけど、その人はとても暖かくて優しくて・・・落ち着いた。安心できたんだ。包帯を代え終わると、もう一度褥の上に寝かされた。
「もう少し眠りなさい。次に目覚めた時には、きっと声も戻っているだろう。」
横になるとすぐに睡魔が押し寄せてきた。なんだか怖くて、眠りたくなかった。でも、睡
魔には勝てなくていつの間にか寝てしまった。その眠りの中で────────────
夢を見た。緋色の夢を。地面、空気、天。全て緋色。燃え上がる炎、焼き払われる家々。
全身を緋色に染めて倒れている人々。
ココハドコ? コワイヨ
飛び交う矢、白銀にきらめく刃。人々の怒号、悲鳴、叫び。絶望した人々は、自らに刃をむける。
コワイ タスケテ
髪の長い女が俺を抱いている。だが、すぐにその女は倒れ、俺は放り出された。
『・・・なさい・・・、逃げなさい・・・』
ナニ? ナンテイッテルノ?
『・・・ッ、逃げなさい!』
誰かの名前が叫ばれた。それは俺の名前だったのか。断片的な場面が浮かんでは消えていく。これは夢か現か、もうそれすらも分からなかった。不意に、右肩に痛みを感じた。
イタイヨ コワイ タスケテ コワイ コワイ コワイ コワイ コワイ コワイ!!
「ッ!」
その時、誰かに強く揺すぶられた。そして、目が覚める─────────
目の前にいたのはあの人・・・ああ、分かり難いから『父さん』って呼ぶぞ。父さんは驚いた顔で俺を見下ろしていた。
「どうした?汗びっしょりじゃないか。ずいぶんうなされていたけれど、怖い夢でも見たのか?」
夢だったことが分かって安心したと同時に、両方の瞳から涙があふれた。・・・オイ、笑うなよっ。ガキの頃の話だろっ。ま、いいや。父さんは、涙を拭い、汗でぐっしょり濡れた服を着替えさせてくれた。そうして、とても優しく笑ってくれた。それがすごく嬉しくて、どうにかしてそれを伝えたかった。感謝の言葉を伝えたかった。だから、ダメもとで口を開いた。
「ありがとう。」
声が出た。少し掠れた、小さな声だったけど。父さんはまた笑って、俺の頭を撫でてくれた。
「よかったな。声が出るようになって。」
「はい。」
「儂の名は時矢。大神殿で神主をしている者だ。そなた名は何という?どこの村に住んでいた?」
その問いには答えることができなかった。記憶にかかる靄は消えていなかった。それどころか余計に濃くなっている気がした。だから、静かに首を左右に振った。
「覚えていないのか?」
今度は縦に首を振る。父さんは、何か考え込むようにうつむいた。俺はビクビクして父さんを見ていた。ここにいたいって思いながら。しばらくして父さんは顔を上げた。
「『トキ』というのはどうだ?儂の名前から取ったんだが・・・。」
一瞬、父さんが何の事を言ってるのか分からなかった。でも、それが俺の名前の事だとすぐに気付いた。
「嫌か?」
俺は大きく左右に首を振った。父さんは、更に信じられない事を言った。
「では、そなたは今日から『トキ』。そして我が息子だ。」
「え?」
「今日から儂がそなたの父だ。」
「ちち・・・?」
「嫌か?」
その問いに、俺はまた大きく左右に首を振った。嬉しくて嬉しくて嬉しくて、また涙があふれてきた。俺が泣きやむまで、父さんはずっと頭を撫でてくれた。大きなあったかい手で。
その日から、俺は『トキ』になった。
コトン
焚き火の木が崩れ落ちた。トキはそれを見つめながら、静かに言った。
「誰にも話すことはないと思ってたんだけどな。何でだろう・・・急に話したくなった。」
「トキ・・・。」
静かに沈黙が流れる。莉央は、こういう空気が苦手なので、何か話そうと言葉を探した。
「あっ!ねえ、今お父さんは?」
「俺が十五の時に病で亡くなった。」
「あっ、ごめっ・・・。」
そんな莉央を見てトキはフッと笑う。決してバカにしているのではない、優しい笑いだ。「謝んなって。ほら、もう寝ろ。明日は今日以上に歩くぞ。また闇の刺客が来るかもしれんし、早く寝て元気出せ。」
「うん・・・。わかった、おやすみ。」
まだまだ聞きたいことがある莉央だったが、何だか複雑そうなトキの顔を見ると聞けなかった。そして横になりながら、旅に出てからずっと疑問に思っていたけれど、考えること
を拒否していた事を思い出していた。それは─────
(母さん・・・)
母、小夜のことだった。
(私が・・・私が、本当に『神の子』だとしたら、どうして母さんは私を育ててくれたんだろう。母さんは知ってたのかな?)
考えれば考えるほど分からなくなる。それに何だか寂しくなったので、莉央は考えるのを止めた。そして硬く瞳を閉じ、朝を待つ。
同時刻。大神殿、神主寮。字からも分かる通り、神主たちの寮である。その中に、大きな寮から少し離れて建っている小さな庵がある。そこが老神主日良哉の生活する庵だ。その一室で、日良哉は一人酒を飲んでいた。
ジリッ
唯一の明かりであるロウソクの火が微かに揺らめく。日良哉はそれを見つめながら、朝の事を思い返していた。
「くっ、いまいましい。」
酒が入った器を持つ手に力がこもる。
(くそっ、嵯峨の奴めいまいましい。器以上の地位を望む身の程知らずがッ。儂は違う。儂にこそ光ヶ原を統べる力が与えられるべきだ。老神主などに甘んじている事はない!)
日良哉は、酒が入ったままの器を床に叩きつけた。
ガシャーン
と、派手な音を立ててそれは砕け散った。残っていた酒が床を濡らす。日良哉は、その一つの破片を拾うと、手のひらに力を込めた。手から血が滴り落ちる。ポツポツ・・・と、
それはこぼれた酒を紅く染める。
ジリッと、またロウソクの火が揺らめき、光が弱くなった。と───── 、
「『力が欲しい』?」
不意に、後ろから声がした。少し幼さの残るその声が言ったのは、今、血に濡れた手を見つめながら思ったことだった。
「何者だッ!?」
鋭い視線で後ろを振り返る。そこにいたのは、どう見ても十歳位の少年だった。黒い髪に黒い瞳。神主用の上衣と膝丈の袴という神主見習いの服装をした、どこにでもいそうな容姿の少年だ。が、少年が纏っている空気は彼が唯人で無いことを教えていた。少年はクスクスと笑いながら、もう一度日良哉に問う。
「そんなに力が欲しい?」
「答えろ、何者だ?」
日良哉は静かに言った。血に濡れていない方の手で護身用の短剣を探す。少年は、日良哉の言葉を無視して言葉を続ける。
「そんなに力が欲しいのなら、僕の手を取りなよ。」
そう言って少年は手を差し出した。日良哉は、油断無くそれを見据える。その瞳は険しい。
「どういう意味だ?」
「欲しいんでしょ?光ヶ原を統べる力が。」
ユラッ
それまで黒かった少年の瞳が、妖しく金に光る。そしてその髪も淡い金色の光を発する。
思わず日良哉は怯んだ。瞳の色が弱くなり、短剣を握りかけた手から力が抜けていく。
「お前は、神か?」
少し震えた声の日良哉の問いに、少年はニヤリと不敵な笑みを浮かべた。
「僕はただの使いだよ。」
一度言葉を切り、少年は金の瞳で日良哉を真っ直ぐ見る。
「黄泉闇神様のね。」
「なっ・・・!!」
日良哉は知らず、後じさる。
「さあ、力が欲しいんでしょ?」
少年は、もう一度ゆっくりそう言いながら、日良哉に近寄る。
ゴクッと日良哉は息を呑む。
「あ・・・。」
少年の金色の瞳に見つめられ、日良哉は熱に浮かされたように震える手をそろそろと差し出した。その目は、これ以上ないほど見開かれ、正気の色が無い。手が、ゆっくりと少年に近づく。少年は身じろぎ一つせず、ただそれを見つめる。そして、血に濡れる日良哉の
手と、少年の手が─────合わさった。
フッ・・・とロウソクの火が消えた。部屋中に闇が満ちる。その闇の中で。
「交渉成立。」
少年は静かに呟いた。
シャーン
光ヶ原に日が昇る。そして、『かみどの』に祈りの鐘が響き渡った。天日神に捧げる祈りの鐘が。