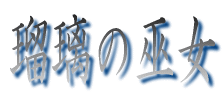

第2話
四 出逢い
闇。新月の夜を、闇を、人々は恐れる。古に父なる神が葬った悪しき神が、新月の夜だけ力を吹き返す。人々はそう信じていた。父なる神の力を以てそれは人々に及ぶことはない。しかし、心迷い一時でも闇に心を傾けた者は、その邪悪な闇の力によって自身を滅する。だから、決して闇に心迷ってはならないと人々は言い合った。闇を忌み、光を尊んだ。
────── 闇があるから、光があるとも知らず。
トキは美貌の青年だった。長身だが、ひょろっとした印象はない。整った顔立ちで、どこか品がある。その美麗な面を縁取る髪は、闇を思わせる黒。同じく黒い瞳には、冷たい光があるように思われた。耳に黒い石が冷たく光っている。彼の周りの空気は張りつめた感じで、鋭利な刃物を思わせる。知り合って数時間というのもあるのだろうか、トキは寡黙で必要以上のことは喋らない。ただ歩き続ける。時々振り返っては、後方の莉央たちを待った。
西へ続く街道は、決して険しいわけではない平坦な道だが、旅慣れない者には厳しい。おまけに、トキは結構な速さで歩く。数ヶ月前まで里で畑仕事やらをこなしていた莉央でさえ、トキの速さに着いていくのは難しかった。まして、生まれてからずっとお嬢様育ちで、巫女になってからも神殿から滅多に出たことのない寧禰などは、ほとんど小走り状態。しかも、日頃持ち慣れない荷物も持っているので、寧禰は莉央から更に後れをとっている。見かねて莉央は言った。
「ねえ、そろそろ休まない?もう、足が棒みたい。」
トキは立ち止まりもせず、素っ気ない口調で言った。
「もう少し我慢しろ。」
莉央は、ムッとして立ち止まった。その表情が見る見るうちに曇り出す。莉央は非常に分かりやすい性格だ。知り合って数ヶ月しかたってない寧禰でさえ、そのことはよく知っている。特に、今のように腕を組み、眉間にしわをよせ、文字通り口をへの字に曲げているときの莉央は不機嫌極まりなく、何をするか誰にも分からないのだ。
「あー、莉央!待っててくれたの?・・・あ゛っ!」
ようやく追いついた寧禰は、莉央の様子に気付き驚いた。
(どうしよう・・・。大丈夫・・・じゃないよねえ。でもぉ・・・。)
こういう時はただ見守るしかない。何を言っても逆効果にしかならないことを、寧禰は経験から学んでいた。寧禰がハラハラと見守っているのにも気付かず、莉央は先行くトキの背中を睨みつけていた。と、手近にあった石を拾った莉央は、しばらくそれを見つめてい
たが、次の瞬間─────
ヒュンッ
莉央の手を離れたそれは、気持ちいい音を立てながらトキの背中目指して一直線に飛んでいく。
「危ないッ!」
寧禰は思わず目を伏せ、さらに手で覆った。が、いつまでたってもトキのうめき声も、莉央の勝利の雄叫びも聞こえない。唯一聞こえたのは、『ぽと』という何とも情けない音だった。恐る恐る目から手を離し、伏せていた瞳を開けると、トキは相変わらず先を歩いていた。莉央はというと、何故か立ち惚けている。その顔をのぞき込んだ寧禰は、
(空気の抜けた紙風船みたい。)
などと、呑気に考えた。
「嘘・・・あいつ・・・よけた・・・。」
莉央は悔しげに口をキュッと結ぶと、次から次に石を拾って投げ拾っては投げる。そのたびにトキは難なくよけるので、余計に莉央はムキになってしまう。なぜなら、阿瑚の里では、悪ガキはもちろん、働き盛りの若者でさえこれをよけるのは至難の業だったのだ。トキはとうとう立ち止まると、ちょうど飛んできた石を片手で受け止め、呆れたように言った。
「おい、こんなガキみたいな事する元気がある位なら歩け。」
莉央は、肩で大きく息をしながら、その瑠璃の瞳で鋭くトキを睨みつけ、叫んだ。
「何よ、その言い方!えっらそーに!そりゃ、あんたはいいかもしれないけど私たちの事も考えなさいよねー!!!」
「じゃあ、勝手に休め。賊や獣に襲われていいならな。」
トキは冷たく言い返した。『賊』や『獣』など物騒な言葉に、莉央と寧禰はビクッと震え顔を見合わせた。トキは、それを冷たい漆黒の瞳で一瞥すると、
「嫌ならもう少し歩け。この先に小屋がある。」
と言って、また一人ですたすたと歩き始めてしまった。
「よかったあ。ちゃんと考えててくれたんだね。・・・莉央?」
寧禰がほんわかと呟いた。が、莉央は顔を真っ赤にし、うつむいている。
「そっ、それなら早く言いなさいよねーッ!!」
怒りの矛先を失った莉央の叫びが、空しく夜空に吸い込まれた。
それからしばらく歩くと、トキが言ったとおり伸びた草の中に古びた小屋があるのが分かった。
「うわー、何これ・・・。ひどい・・・・・。」
莉央は絶句した。小屋の周りは荒れ放題で、いかにも雑草と言った風情の草が思いのままに伸びている。両手で草をかき分け、かき分け進むしかないようだ。見ると、トキはすでに入り口近くまで行っていた。
「ちょっ・・・!。」
「莉央っ!」
また、何か言おうとした莉央だったが、寧禰に袖を引っ張られた。寧禰は、少し潤みかけた瞳で莉央を見上げている。莉央は、それを見ると何も言えなくなってしまうのだ。
(もちろん、例外もあるけれど・・・。)
「行こっか。」
莉央は、諦めたようにため息をつくと、両手で勢いよく草をかき分けた。
トキが待っている入り口に着いたとき、二人(特に莉央)は疲れきっていた。近いように見えたが、かなり険しかった。かき分けてもかき分けても草が体にからみついてきたし、時々、伸びきった草がチクチクと足を刺した。それに莉央は、寧禰が少しでも歩きやすいようにと気を配っていたので、疲れも倍だった。おかげで、寧禰は少し楽に歩いてこれたようだった。
(それでも、かなり疲労していたが・・・。)
寧禰は、改めて小屋を見ると、ごくっと息をのんでしまった。何だか気味が悪い。心なしか空気がひんやりしているように感じられる。季節はもう夏近いというのに・・・。
トキは二人が来たのを確かめると、戸に手をかけた。結構古い小屋らしく、なかなか開かず、二、三度ガタガタッといわすとやっと開いた。スッと戸が開いた瞬間、寧禰は何故かドキッとした。中はひっそりとしていて、炉の他は特に何も見あたらない。トキ、莉央、寧禰の順番で中に入った。一歩足を踏み入れると、莉央と寧禰は不思議な寒気に襲われた。思わずしっかりと手を握りあう。トキはというと、さっさと一人で寝る支度を整えていた。その背中に、寧禰が恐る恐る声をかけた。
「ね、寒くない?火、点けてもいいかなあ・・・?」
「駄目だ。無人のはずの小屋に灯りがついてたら変に思われるだろ。」
(ま、近くに人家はないはずだけどな。)
トキは密かに付け加えた。が、莉央と寧禰がそれに気付くはずもない。
「莉央ぉ・・・。」
例の潤んだ薄茶の瞳で寧禰が莉央を見上げた・・・切なげに。莉央は、小さな子をあやすようにポンポンと寧禰の頭を撫でると、優しく言った。
「あいつの言うことも一理ある・・・と思うし、一緒に寝るから大丈夫だよ。」
寧禰は、少し安心したように微笑んだ。
二人は、持ってきていていた(薄い)簡易毛布を敷き、とりあえず寝る場所を用意した。入り口に近いところにトキが、奥の方に莉央と寧禰が寝る形となった。トキはもうすでに寝ているように見えた。相変わらず二人に背を向けているが。
「じゃ、オヤスミ。」
「おやすみ。」
横になると、床の冷たさが体に伝わってくる。ぎゅっと二人は身を寄せ合った。寧禰は、しっかりと莉央の手を掴み、
「莉央、私が寝るまで絶対に絶対に手、離さないでね!」
と、何度も何度も念を押していたが、あっという間に寝てしまった。その寝顔を見ながら、莉央は苦笑してしまう。最初の寧禰の印象は、しっかりしたというか、どこか母親を思わせる所があったが、今ではすっかり妹のような存在になっている。ふと、莉央はトキの方へ目を向けた。トキは、規則正しい寝息を立てて眠っているように見えた。莉央は身を起こすと、そろそろとトキに近づき声をかけた。
「ねえ、起きてる?」
「何だ。夜這いか?」
「違うわよッ!」
あくまで小声で莉央は叫んだ。トキは、背を向けたままの格好で応じている。莉央の顔は、少し朱に染まっていた。少しためらってから、莉央がポツッと言った。少し聞き取りにくいくぐもった声で。
「・・・ごめん。」
「え?」
今度はトキも身を起こし莉央と向き合った。初めて正面からちゃんと見るトキの顔はやはり美しく、赤かった莉央の顔が更に赤くなる。莉央は一気にまくし立てた。
「さっきはごめん。その・・・石投げたこと。確かにガキっぽかった。・・・それだけっ、オヤスミっ。」
「へえ、意外に素直なんだな。」
トキが少しからかい口調で言うと、莉央の顔がまた赤くなった。寝床に戻りかけていた莉央だったが、もう一度トキを振り返ると極力小声で叫んだ。
「なっ、なによ悪いっ!?」
「いや。明日に備えてゆっくり休め。」
トキはすでに横になっていた。莉央は、何か言おうとしたがうまく言葉が見つからず、一つため息をついて寝床に戻った。莉央も疲れていたので、横になると、すぐうとうとしてきた。その微睡む意識の中で、以前『トキ』という名を聞いたことがあるのを思い出した。そう、確かあれは、他の巫女のくだらない世間話を聞いていた時・・・・
寧禰はちょうど使いか何かに出ていて、莉央は巫女たちの輪から一人だけ外れてぼんやりしていた。と、そこへ一人の巫女がはしゃいだ様子でやって来た。
「聞いてくださいまし、さっきトキ様に声をかけられましたのよ!」
一斉に周りの巫女たちが色めき立った―もちろん、莉央をのぞいてだが―
「本当?信じられませんわ」
「ええ、あのトキ様が巫女に声をかけるだなんて・・・。」
「でしょう?私も信じられませんでしたわ。『巫女長様はどこか?』って、聞かれましたの!素敵なお声でしたわ。あのお美しいお顔を間近に見られる日が来ようとは・・・。あー、幸せ。」
巫女の興奮はなかなか収まらないようだ。莉央はというと、興味なさそうにあくびをしている。もっとも、噂の主のことも知らないのだから、無理もない。巫女たちは、莉央の方など見もせず話を続けている。
「素敵よねー、トキ様。」
周りの巫女がうなずきあった。
「容姿端麗で、しかもとても優秀でいらっしゃるものね。」
「ええ、確か、十二の折りに神主見習いになられたんですって。」
「十二?神主見習いになれるのは十三からだったわよね?」
「特例なんですって!すごいわよねー!」
光ヶ原では、男子は十三歳から、神主見習いになる試験を受ける権利が得られる。もっとも、かなりの難関試験なので、毎年受かるのはごくわずかな少年たちだ。女子の場合は天巫女である。こちらの方は試験の他に、父親などの政治的権力闘争が背景にあることが多い。ただ、修行が辛いので、耐えきれず辞める巫女も少なくはない。
とにかく、『トキ』という人物は大神殿の巫女や侍女たちの憧れの的だった。しかし、本人は全く関心がないようだ。「そこがいいの。」などという巫女も多数いるらしい。だが、莉央はその気持ちが分からない。トキをちらっと見かけたことはあったが別に何にも思わなかったし、他の巫女たちのように騒ぐ気も起こらない。いつも、そういう巫女たちを冷めた目で見ていた。
翌朝。莉央は、不思議な光を感じた。
「ん〜・・・」
昨日、かなり疲労していたので、頭はなんとなく起きているのだが、体が起きようとしない。しかし、重たいまぶたをうっすら開く。
「う・・・ん?ここ・・・どこだっけ?」
莉央は一瞬、自分がどこにいるのかわからなくなった。まあ、よくある(?)ことだ。大神殿に来てしばらく感じた感覚でもあった。
「え・・・っと・・・?」
はっきりしない意識のまま、莉央は一回寝返りをうった。と、向こうの方に黒い何かが見える。
(黒・・・?あ・・・、髪の毛だ。髪?・・・人・・・ああっ!思い出した!!)
莉央は、ガバッと体を起こした。トキも寧禰もまだ眠っている。ふと、胸元の光に気がつく。例の勾玉だった。莉央は勾玉に紐を通して首飾りのようにしていた。
「琉莉夜・・・?」
莉央が呟くと、勾玉は光を増した。
『莉央、聞こえますか?』
心に響いてくる声。
「うん。聞こえる。ねえ、琉莉夜、どうして寧禰まで?それにトキって一体・・・。だいたい、西って言ったってどこへ行けばいいの?」
『寧禰は、きっと貴女を支えてくれるでしょう。トキは、とても剣術に長けています。貴女たちを守ってくれるはずです。それに、もしかしたら彼は・・・。』
「彼は?」
琉莉夜は何かを言い淀んだ。しかし、すぐに明るい声に戻ると言った。
『今は言うべき時ではありません。それより、莉央。これから闇の宮に向かってください。』
「闇の宮?」
「天日神が黄泉闇神を封印したとされるところ祀った宮だな。黄泉への入り口とも言われてる・・・。」
「トキ!?起きてたの?」
いきなり後ろからトキが現れた。なんだかボーっとしている。昨日感じたような張りつめた雰囲気が今はない。トキは、不機嫌そうな声で言った。
「起こされた。おまえの声がでかいんだ。ふぁ〜あ・・・」
どうやらトキは朝が苦手らしい。
「へー、闇の宮なんてよく知ってるね。」
「神義で教わったはずだろ。」
莉央の感嘆の声に、トキが呆れたように言った。『神義』とは神代の時代、つまり、光ヶ原の創造から八百万の神々の神話、黄泉闇神の封印までの時代の講義のことである。神主見習いも、天巫女も、神義は必修科目であるから、当然莉央も習っているはずなのだが・・・。
「あれ?そうだったっけ?」
この調子である。実は、神義の時間、莉央は、寝ているかサボっているかどちらかだったのだ。
『莉央、黄泉闇神の邪力の源は恐らくそこでしょう。十中八九天日鏡もそこにあるはずです。』
「琉莉夜。天日鏡は今も無事なの?」
莉央が問いかけると、勾玉の光が少し弱まった。
『・・・もう時間がありません。恐らく、天日鏡は無事です。ただ、早くしないと・・・かも・・・しれま・・・・』
「琉莉夜っ!?」
声が途切れると同時に、勾玉が光を失った。
「なるほど、それで神の子と話せるってわけだ・・・。じゃ、もう少し寝ようかな・・・。」
トキは、まだ寝ぼけ眼だ。昨日の雰囲気がまだ戻っていない。
「う〜・・・ん。あれ?ここどこだっけぇ?」
寧禰が目を覚ましたらしい。ゆるく波打った薄茶の髪がほつれている。
「おはよう、寧禰。」
「莉央ぉ?あっ、そうか!思い出した。」
寧禰は結構寝起きがいいのだ。にっこりと莉央に笑いかけた。
「おはよう。莉央。ね、今日はどうするの?」
莉央は、寧禰にさっきの事を説明した。
「闇の宮か・・・。かなり西だね。」
「寧禰も、闇の宮知ってたの?」
「神義で教わったでしょ?」
ガックリ。莉央は肩を落とした。
「じゃあ、早く出発したほうがいいな。準備しろ。」
そういったトキは、すでに旅衣を整え、準備を終えている風だった。すっかり目が覚めたようだ。昨日の雰囲気が完全に戻っている。昨日は気付かなかったが、その腰に剣を提げている。莉央と寧禰も、急いで準備をする。
(といっても、旅衣はもう着ているし、荷物も毛布をたたむだけだが・・・)
準備を終えると、持ってきていた木の実などで簡単に食事を済まし、いよいよ出発しようとした。が、その時、
「あー!そうだっ☆」
すっとんきょうな声をあげたのは、寧禰だった。
「どうしたの、寧禰?」
「自己紹介しよう!」
「はあ!?」
寧禰の予想外の言葉に、莉央とトキは同時に聞き返した。
「自己紹介?」
寧禰は、目をきらきらと輝かせて言う。
「うん。だって、まだちゃんとしてなかったでしょ?トキ君の名前は聞いたけど、私と莉央はまだだし。ね。」
こうなると、莉央は寧禰に逆らえない。
「そ、それもそうね。じゃ、私から。名前は莉央。歳は十六よ。よろしくね、トキ。」
「じゃ、次は私。名前は寧禰。一年前から大神殿に仕えてるの。歳は十五歳。よろしくね、トキ君。次はトキ君ね。」
トキは、呆れたように寧禰を一瞥し、
「必要ない。」
と言って歩き出だそうとする。その背中に寧禰が呼びかけた。
「お待ちくださいませ、トキ様!」
途端にトキの動きが止まり、振り返る。
「その呼び方はやめろ。くだらない巫女連中を思い出す。」
不機嫌絶頂といった感じの声だ。寧禰はにっこりと笑顔のまま、さらに言った。
「自己紹介していただけないのなら、ずっとこう呼びますわ。トキ様。」
「・・・ッ、わかったッ。名はトキ、歳は十八。よろしく。これでいいなッ、行くぞッ!」
トキは、不機嫌な声のまま一気に言うと、さっさと歩き出した。
「はーい。」
その後を機嫌良く追って行く寧禰。
(実は寧禰ってけっこうやり手・・・?)
そう思った莉央だった。
ゴオォォォ・・・ゴオォォォ・・・
気味の悪い音が響いている。ここは地の底、黄泉原。古に天日神に封じられて以来、黄泉闇神はこの地に眠っていた。しかし永き時流の中で、黄泉闇神は力を取り戻しつつあった。その自らの力で、黄泉原に砦を創り、光ヶ原への扉を開こうとした。時流が経つにつれて、光ヶ原に残っていた神の力が薄れていくのがわかった。そして今。あらゆる人間の想いや野心が交錯している光ヶ原には、微かながら歪みが生じつつあった。黄泉闇神は、それを見逃さなかった。
― とうとう、黄泉闇神は光ヶ原への扉を開いたのだった
―
黄泉原の中央。光ヶ原の闇の宮にあたる場所に創られた黄泉闇神の砦。その中央にある間に、一人の若い男がやって来た。歳の頃は二十歳前後。整った容貌をしている。ただ、その瞳は包帯で覆われていた。腰まで伸びている髪は白銀に近い色だ。彼は、奥にある空洞を見つめている風だった。
オォォォ・・・・キ・・・ユ・・・キ
あの気味の悪い音が少し変わって、しゃがれた声のように聞こえてきた。男は、慌ててひざまずいた。白銀の髪が暗い床を這う。
『侑岐・・・我が子よ・・・日の者が・・・近づいている・・・・我の復活まで・・・今少し・・・は・・・鏡は・・・渡すな・・・・・・』
「御意。」
男は静かにうなずいた。声は続ける。
『だ・・・が・・・て・・・決して・・・無茶はするな・・・愛しい我が子よ・・・』
その言葉に、男の顔が朱に染まった。男は、頭を深く下げ言った。
「はっ。・・・闇の御君の御心のままに・・・」
ゴオォォォ・・・ゴオォォォ・・・
声は、またあの音に戻った。男は立ち上がると、光ヶ原への扉へと歩を進めた。
 「兄君!」
「兄君!」
扉の前に、一人の少女がいた。十三〜四歳くらいのとても愛らしい少女だ。少女は、男を見上げ言った。
「兄君、春も参ります。」
それまで硬かった男の表情が和らいだ。
「春、おまえは大神殿から戻ったばかりだろう?休んでいなさい。」
「でも・・・!」
男は、また何か言おうとした少女を抱き上げて優しく制す。
「春姫。無理をしては、闇の御君がご心配される。ゆっくり休んだら、また手伝ってくれればいい。」
少女は、しばらくうつむいていたが、顔を上げると言った。
「わかりました。兄君、兄君こそ無理をなさらないで下さいね!」
男は、はっきりとは答えず微笑み、少女を下へ降ろすと、優しく少女の頭を撫で、扉へと手をかけた。
ばあっ 視界いっぱいに黒が広がり、一瞬何も見えなくなった。次の瞬間、そこに男の姿はなかった。
「許せ、春・・・。」
男が呟いたことを、少女は知らない。
「ねえ、闇の宮までどれくらいかかる?」
「三ヶ月ってところだな。」
莉央の問いにサラッとトキが答える。莉央は驚いた。
「三ヶ月!?そんなにかかるの?」
「ああ。闇の宮は西の果てとも言われてるしな。」
莉央はガックリと肩を落とした。闇の宮とは、さっきトキも言ったように、古の時代、天日神が黄泉闇神を封印した跡を、後の人々が祀った宮だ。やはり、大神殿の管轄下で、神主と巫女が数人いるらしい。三ヶ月と聞いただけで莉央はうんざりしてしまった。中央都から離れれば離れるほど、道は整備されておらず、険しくなっていく。莉央たちは今、山にいる。山に入ってからあまり時間は経っていないが、道と言うにはあまりにもひどい道になってきた。最初は元気よく話しながら歩いていた莉央と寧禰も、自然と無口になってくる。トキは相変わらず黙々と歩いていた。が、急にその歩みを止めた。
「トキ?どうした・・・・」
問いかけた莉央を、トキは仕草で制した。鋭い目つきがさらに鋭くなり、辺りを見据える。莉央と寧禰の間にも緊張が広がっていく。
「いいか、俺が『行け!』って言ったら全速力で走れるところまで走れ。」
「え?」
トキは、そう言うと剣の柄に手をかけた。莉央も寧禰も状況を理解できない。トキは注意深く辺りを見、そして、
「行けッ!」
と叫ぶと同時に剣を抜いた。莉央と寧禰も、ワケがわからないままとにかく走り出す。後ろを振り向くと、数人の武器を持った男たちがトキを囲んでいるのが見えた。
「あ!!」
莉央は思わず立ち止まりそうになった。しかし、意外なほどの力で寧禰に腕を引っ張られた。
「莉央、私たちがいても足手まといになるだけだよ。さっき、あっちにおっきな岩が見えたの。とりあえず、そこの陰に隠れとこう!」
「で・・・でもっ・・・。」
「莉央ッ!」
莉央は、いつにない寧禰の厳しい態度に驚き、何も言えなくなってしまった。
(確かに、寧禰の言う通りだけど・・・でも・・・)
莉央は、何度も後ろを振り返る。剣と剣とがぶつかるような音が途切れ途切れに聞こえてくる。寧禰が言っていた岩は、案外近くにあった。その陰に二人は身を潜めた。全速力で走ってきたので、二人ともしばらくは喋ることができなかった。
かなりの時間が経ったように感じたが、トキはなかなかにやって来ない。莉央も寧禰も不安がだんだん大きくなっていく。
(遅いね、トキ君・・・。)
(大丈夫!きっともうすぐ来るよ。それに、トキは剣術に長けてるって琉莉夜が言ってたし・・・。)
そんな会話をしていると、ふと、こっちに誰か来る気配を感じた。
(トキ君っ!?)
寧禰が飛び出しかけたのを、莉央は咄嗟に止めた。
(待って寧禰!さっきの賊かもしれない。油断できないよ。)
(そうだね。もし賊だったら・・・トキ君は・・・?)
(大丈夫よ!・・・きっと。しっ、静かに!)
二人の間に緊張が走る。莉央は、手近にあった石をぎゅっと握った。気配がどんどん近づいてくる。
「おい・・・」
「キャーキャーキャー!!!」
「くらえ!くらえ!くらえー!」
寧禰は叫び、莉央は石を必死で投げる・・・が、
「おい、落ち着け!俺だ。」
そこに立っていたのはトキだった。呆れたように二人を見ている。
「あ。」
「ほんとだ・・・トキ君だ・・・。」
二人は一気に体の力が抜けた。莉央は、放心したように地面を見つめている。寧禰が、トキに問いかける。
「だ、大丈夫だったの?」
「大丈夫に決まってるだろ。ほら、いつまでも座り込んでないで立て。」
トキが手を差し出した。それまで黙っていた莉央だったが、その手をむんずと掴むと、
「なんっで一人でやっちゃうのッ!?」
そう叫び、思いっきりトキを引き倒した。
「い・・・てっ、何するんだよ。」
莉央は立ち上がると、草の中に倒れたトキを睨み付けまくし立てる。
「そりゃ、私たちは何にもできないよッ!だけどっ、何の説明もしないでいきなり走らされて、気が付いたら、あんたは囲まれてるしッ・・・っ」
「おい、落ち付けって。ああ〜〜それから泣くなっ!」
莉央の頬を伝った雫に、トキが多少たじろぐ。
「あーあ、トキ君が泣かしたぁ。」
さらに寧禰が追い打ちをかけたりして☆
「お〜ま〜え〜な〜ッ!!」
トキは軽く寧禰を睨むと、立ち上がり、服や体に付いた草をはらった。そして、腰の紐の所から布を取ると、莉央に差し出した。 「ほら、これで顔拭け。・・・悪かったよ。今度からは気をつける。」
「約束だからね。・・・私もごめん、急に泣いたりして。」
「全くだな。」
瞬間、莉央の涙が止まった。
「トーキー!!こういうときにそういうコト言う!?なんであんたはそーなのよ!!」
「莉央、落ち着いて!そ、そう言えばトキ君、あの賊はどうしたの?」
再び怒り爆発しそうな莉央を押しとどめて、寧禰が話題をかえた。
「ああ、人数だけの野郎どもだったから、適当に気絶させて、里まで戻って警備団に引き渡しといた。」
「トキ君、剣が得意なんだって?」
「一応な。剣技は好きだったし、父さんが教えてくれ・・・」
ふいに、トキはハッとした様子で言葉を止めた。
「トキ君?どうかした?」
「いや、何でもない。時間くったな、急ごう。」
そう言ってトキはさっさと歩き出した。その表情は暗い。莉央と寧禰は顔を見合わせた。
「何だったのかな?」
「さあ・・・?」
「おーい!野宿したくなきゃ、今日中に山越えるぞー!」
遠くからトキの声がした。もうかなり先に行っている。
「あ、待ってよ!」
少し気になったが、二人は急いでトキを追いかけた。
日は、とっくに真上を越し、西に傾いていた。三人はまだ山の中だった。相変わらず険しい道で、莉央と寧禰もだんだん慣れてきたようだが、かなり疲労した様子だ。だいぶ前から会話がない。見た感じ、トキに疲労の色はなかった。相変わらず先を歩き、時々後方の莉央たちに手を貸した。その表情からは、さっきの暗い感じが消えているように莉央は思った。そのうちに、日がだいぶ沈み、暗くなってきた。トキは立ち止まると、莉央と寧禰に言った。
「おい、今日はこの辺りで野宿するぞ。」
「えー!?野宿う?」
二人は、同時に声を上げた。
「しょうがないだろ、日が暮れたんだから。まだ半分くらいしか来てない。これ以上歩く方が危険だ。火を焚いてれば獣は寄ってこない。」
「わかった・・・。」
二人は渋々うなずいた。
「じゃ、あの辺にするか。」
三人は、適当な場所を決めると、火を焚くために枯れ枝を集めだした。しばらく経った時だった、トキは急に持っていた枯れ枝を落とし、周りを睨んだ。それに気付いた二人は、慌ててトキに駆け寄る。
「トキ?どうかした?」
「なにかいる。」
静かにトキは言った。
「何かって?」
「ただの賊や獣じゃないな・・・。分からないか?空気が震える感じがする。」
緊張が一帯に広がった。莉央と寧禰はしっかりと手を握りあっている。
ザワザワ ザワザワ
風が急に強くなり、周りの木や草が騒ぎ出す。ふいに―
「・・・っ!」
寧禰が、ガクッと膝をついた。その表情が苦痛に歪み、青白くなっていく。
「寧禰っ!?」
「・・・ッ?くるっしッ・・・」
「寧禰!?どうし・・・!?」
ザアアアアッ
風が強くなった。莉央は、必死に寧禰に駆け寄り、抱き起こす。また風が強くなる。目を開けていられない。
「ちっ、誰だっ!?闇の手の者かっ?」
トキがそう叫ぶと、風が少し弱まり、目の前に一人の男が現れた。
「ご名答。我が名は侑岐、闇の御君より命じられた。小賢しい日の者たち、これ以上は行かせぬ。生かしもしない。」
冷たい声。白く長い髪、白い服、耳に光る赤い石。そして、瞳を覆う包帯。とにかく、全てが印象的な男だった。その体から、ただならぬ気を感じる。
「寧禰に・・・寧禰に何をしたのっ!?」
微かに震える声で、莉央は叫んだ。
「ほんの少し息吹を奪っただけだ。もろいな、日から承けた命など。こうもたやすく絶えるのか・・・。」
「なっ・・・!」
莉央は怒りで言葉にならない。トキが、剣に手をかけた。男― 侑岐は、トキの方をむくと、静かな、冷たい声で言った。
「その娘の息吹が絶えていいのか?私にはたやすいこと・・・。」
「ちっ。見えるのか、その目。」
トキがいまいましそうに言い捨てた。
「闇の御君のお力だ。見えこそしないが、貴様らの動きなど手に取るように分かる。残念だったな。」
「っくも寧禰を・・・っ!」
莉央は、手近にあった石を男に投げた。が、
「おっと。こんな小石で何ができると?」
侑岐は、あっさりとそれを受け止め、握りつぶした。
「お前が神の子か?何のことはない、ただの非力な子供か・・・。」
「何ですってッ!」
「くっ。ではできるか?二人を助けることが。」
そう言い、スッとトキに指をむけた。瞬間!
「ぐッ・・・貴・・・様ッ!」
トキが、その場に膝をついた。鋭い、憎悪をこめた目で侑岐を睨んでいたが、すぐにその場に倒れてしまった。侑岐は、それをおもしろそうに眺め、笑った。嘲笑の笑い声が暮れた空に響く。それに呼応するように闇がざわめいた。
「くっ、くくくくくっ、はははははっ!こんなに簡単に握りつぶせてしまう命とは何だ?なあ、神の子。さあ、何ができる?無力なお前に。何もできぬだろう。所詮お前は非力な子供でしかない。」
莉央は、呆然とした。知らず、瑠璃の瞳から雫がこぼれ落ちる。
「寧・・・禰・・・・トキ・・・。琉莉夜ぁ!どうしたらいいのッ?」
その莉央の叫びに応えるように、胸に下げていた瑠璃の勾玉から光があふれた。そして、心に響く声。
『莉央、しっかりして下さい。前に言ったことを覚えていますか?』
「え?」
『貴女は、その身に神力を秘めています。』
そう。初めて莉央と琉莉夜が出会ったとき、琉莉夜が告げた言葉だった。
「でもっ、どうすればいいか分からないッ!それに・・・本当に、本当に私にできるの?」
莉央がそう叫んだときだった。ふと、自分の手を包む手に気が付いた。
 「莉・・・央・・・。」
「莉・・・央・・・。」
「寧禰!?」
莉央の腕の中でぐったりとしていた寧禰が、莉央の手を弱々しく握ったのだ。薄茶の瞳も開かれていた。そして、微笑えんだ。
「だい・・・じょぶ。莉央なら・・・できるよ・・・。ね?が・・・ん・・・ばって!」
「寧禰っ!」
寧禰は再び苦しげに目を伏せた。と、隣からも声がした。
「大丈夫だ・・・お前なら・・・莉央、自分を信じろ!」
「トキ!」
トキは、体を半分くらい起こし、剣で体を支えていた。その表情は、苦しそうではあったが、気迫に満ちていた。莉央は一度目を伏せ再び開くと、寧禰を優しく草の上に寝かせ、意を決したように立ち上がった。そして、勾玉に語りかける。
「琉莉夜、教えて!どうすればいいの?」
勾玉の光が少し増した。
『勾玉をかざしてください。』
「こう?」
莉央は、首から勾玉をはずし、空にかざした。侑岐は、それをただ面白そうに見ている。
『そうです。そして、勾玉を中心に印を切るのです。』
「印?」
『ええ。大神殿の紋様を思い出して。あの形に印を切って下さい。』
「分かった。やってみる。」
莉央は、大神殿の紋様を思い出しながら、指を動かす。
(ええっと、天原の象徴、天草(あまつそう)の輪。それに交差する日矢草(ひのやそう)は裁きを示す。そして、真ん中を貫く天日神様の御劔!)
莉央の指先から不思議な瑠璃色の光があふれ、印を創る。印を切り終えると、勾玉はふわりと宙に浮いた。途端、琉莉夜の声の調子が変わった。
『莉央、気をできる限りそこへ集中させて、早く!』
「えっ、うん・・・。」
「ほう、面白い。しかし、そんなもので私に対せると?」
「うるっさい!」
侑岐の言葉に思わず莉央が叫んだ時だった、勾玉から瑠璃の光が飛び出し、真っ直ぐ侑岐に向かっていく。しかし、どこか頼りない。
「くくくっ、おいおい、どこを狙って・・・何ッ!?」
その光は、大きくそれた。が、侑岐の瞳を覆う包帯にかすり、ハラリと包帯が取れた。
「赤い目!?」
莉央は思わず驚きの声を上げた。そう。包帯の下から現れたのは、血のような紅だった。
「・・・なッ・・・見るなァ!!」
侑岐は、その紅の瞳を覆い叫んだ。瞬間、
「げほっ・・・げほっ、げほっ!」
「・・・っは、かはっ」
「寧禰!トキ!」
二人が息を吹き返した。莉央は、寧禰に駆け寄り、抱き起こす。トキは剣を支えに立ち上がるが早いか、侑岐に斬りかかっていく。
「貴様ッ、よくもやってくれたな・・・だああああっ!」
ザクッ─────
「・・・ッ!」
剣は、侑岐の左肩を割いた。鮮血がキラキラと辺りに散る。トキの顔や髪にも。斬りつけられた瞬間、侑岐の目は、紅く紅く燃え上がる炎のように揺らめいた。目を覆っていた手を下ろすと、憎悪と怒りのこもったその瞳ををカッと見開いた。
「・・・のっ、ガキがァァァァ。」
叫んだ瞬間、侑岐の身体から黒い気が放たれた。それは、闇なる者の証────身に宿る
闇。
「トキっ!!」
トキはその気にはじかれ、宙を舞った。そして、後方の木に背中を思いっきり打ち付け、気を失った。
「日の者がッ・・・!貴様らなど、我が君が手を下すまでもないッ。私が消してやろう。」
侑岐はそう呟くと、一歩一歩莉央たちに近づく。その目は、狂気に満ちている風に見えた。
「や・・・だ・・・ッ、来ないでッ!」
莉央は、身を硬くし、寧禰を抱いている手に力を込めた。勾玉の光は、いつの間にか消えていた。莉央は、固く瞳を閉じる。侑岐の気配がすぐ近くなのが分かった。
(やだ・・・もうここで終わりなの!?)
そう思ったときだった。
「兄君!もう、やめて!」
どこからか、少女の声が聞こえた。気が付くと、侑岐の横にとても愛らしい少女がいた。少女は、侑岐に向かって何か話している。
「兄君、無理をなさらないでって言ったじゃないですか。こんなケガで・・・無茶です。一度戻って傷を癒しましょう。」
莉央は、心なしか侑岐の表情が和らいだ気がした。目に宿っていた狂気が消えている。しかし、声は厳しい。
「春姫。大丈夫だ、これくらい。所詮日の者と思って油断していただけ。すぐに始末をつけてくれよう。」
少女も食い下がる。その表情は必死だ。
「駄目です!兄君、これは父君からの伝言です。『無理をするな、一度戻れ。日の者など、いつでも始末できる。今、無理してお前が壊れる必要は無い。』と。」
「だがっ!」
侑岐が、また何か言おうとした時だった。例えようのない重圧が、辺りに満ちた。闇が、一層深まった気がした。少女と侑岐がハッとする。莉央は、もうどういう状況なのか理解できないでいた。
ゴオォォォ・・・ゴオォォォ・・・
奇妙な響きが聞こえ、やがて声になった。地の底から響くような。
『侑岐・・・愛しい我が息子よ、帰ってこい。心配なのだ・・・お前が。』
侑岐の頬が朱に染まる。うつむき、言葉を紡ごうとした。が、声に遮られた。
『我に逆らうか?侑岐よ・・。』
その言葉に、侑岐はハッと顔を上げる。意を決したように、闇の一点に向かいひざまずく。
「・・・分かりました。一度・・・戻ります。」
侑岐は、唇をギュッと噛むとそう言った。そして、立ち上がり、莉央たちの方を向き、
「覚えていろ。お前らは必ず私が消すッ!」
そう言い捨てた。少女が、侑岐の手を握ると、徐々に二人の姿が薄れていった。後に残っ
たのは、風。そして──── 闇。
パチパチ パチパチ
トキは、木のはぜる音で目を覚ました。頭がまだぼんやりしていて記憶がハッキリしない。目の前でチラチラと炎が揺れている。
「ッ・・・!」
起きあがろうとした瞬間、背中に激痛が走った。その痛みが、記憶を呼び覚ます。闇の刺
客に斬りかかっていき、黒い気ではじき飛ばされたことを────。瞬間、痛みにかまわ
ずガバッと身を起こした。火が焚いてあり、その向こうに、莉央と寧禰がいるのが分かった。寧禰は、すやすやと寝息を立てているようだ。一方莉央は、立てた膝に顔を伏せている。
「莉央、あいつはッ!?」
トキが声をかけると、莉央はビクッとして顔を上げた。その表情は硬い。それでも、努めて明るい声で言う。
「トキ、気が付いたの?よかった。」
「そんなことより、あいつはどうしたんだッ!?」
莉央の表情が暗くなり、ギュッと身を硬くする。
「・・・迎えが来てどこかへ消えた。あいつ、言ってた。『お前らは、必ず私が消す。』って。」
「ッ・・・畜生ッ!」
トキは、地面に拳を立てた。莉央は、そのトキの悔しい気持ちが手に取るように分かる。莉央も、大したことができなかった自分が悔しい。同時に、初めて『怖い』と思った。自分たちがしようとしていることの重大さが分かり、『怖く』なったのだ。しかし、莉央はそんな思いを振り切ると、精一杯の明るい声でトキに話しかけた。
「背中、大丈夫?」
「あ?ああ。そう言えば、火。莉央が焚いたのか?」
「うん。火を焚いてれば獣は寄ってこないって言ってたから。」
「そっか・・・。」
沈黙が流れる。莉央は突然立ち上がり言った。
「服、脱いで。」
「は?」
余りにも唐突なその言葉に、さすがのトキも驚いた。しかし、次のトキの言葉に莉央も驚いた。
「莉央・・・襲う気か?」
「違うッ!打ち身の薬があるから、塗ってあげる。」
「いい。」
いい加減トキの素っ気ない言い方に慣れてもいいのだが、やはり莉央はムッとした。そして、一つ深呼吸をすると、
バシッ!!
と、思いっきりトキの背中を叩いた。
「いてー!!!」
たまらず声を上げるトキ。かなり痛そうだ。
(目に薄く涙がにじんでいたが、莉央は気付かなかった。)
 「ほら、痛いんじゃない。さっさと服脱ぐ!」
「ほら、痛いんじゃない。さっさと服脱ぐ!」
「お前なぁ・・・。」
トキは半分呆れて、半分諦めて服を脱ぎ始めた。が、ふっと手を止めた。
「やっぱりいい。」
「なんで?もしかして、恥ずかしいとか?んなわけないわよね。もう、早く脱ぎなさいッ!」
莉央は、そう言って無理矢理脱がそうとした。が、トキもかなり真剣に抵抗する。
「やめろって!こら、変な脱がし方するな。やめろっ!・・・ぷっ。」
とうとうトキは服を剥がれてしまった☆ さすがにちょっと顔が赤い。照れた様子でそっぽを向いている。そして、なぜか右肩を隠している。
「なに恥じらいでるの?薬塗るから手、のけて。」
「・・・驚くなよ?」
トキは、そう前置きしてから、肩を隠していた手を下ろした。そこには─────
「!!」
莉央は、思わず顔を背けてしまった。そこには、決して新しくはないが、生々しい傷跡があった。刃物か何かでできたのか、火傷跡の様にも見えた。トキは、ふっと笑って言った。
「ごめん。驚かせた。」
莉央は、ハッとすると、慌てて首を振った。
「ううん、こっちこそごめん。ほら、薬塗るから、背中・・・。」
また、沈黙。パチパチと木のはぜる音だけが暗闇に響いている。トキの背中に薬を塗りながら、莉央が口を開いた。
「ねえ。その右肩の傷、どうしてできたか聞いてもいい?」
「ああ。これは・・・戦乱の時にできた傷だ。まだ俺が大神殿に来る前。正確には、父さんに拾われる前に。」
「え?」
莉央の手が止まった。前を向いたままトキが続ける。
「俺、養子なんだ。」
そう言ってトキは、自分の過去について語り始めた。
ここは、地の底、黄泉原。黄泉闇神が目覚めかけた自らの力で築いた砦。その一室に、一人の男― 侑岐がうずくまっている。そこへ、一人の少女が入ってきた。
「兄君、傷の具合はどうですか?」
暗かった侑岐の表情が少し明るくなったようだった。
「だいぶいい。春のおかげだ。ありがとう、春姫。」
そう言って、少女の髪を撫でる。少女、春姫は、嬉しそうに笑うと、甘えるように侑岐の胸に飛び込んだ。侑岐は、それを優しく抱きとめる。
「そういえば、常和(ときわ)は?姿が見えないようだが。」
「常和なら、大神殿に向かいました。あちらでも、そろそろ動きがあるようです。」
「そうか・・・。」
侑岐は、何か考え込むように黙った。その侑岐に、春姫が遠慮がちに話しかける。
「兄君・・・。」
「なんだ?」
「今日のような無茶は、もうしないで下さいね!」
少し強い口調でそう言った。侑岐は、優しい微笑みを浮かべ、春姫の髪を撫でながら静かに言った。
「気を付けるよ。」
と。春姫は、それが自分の言葉を肯定するものではないと知っていた。しかし、少女はもう何も言わず、大好きな兄の胸に顔をうずめた。
サワサワ サワサワ
風に、木の葉が揺れている。静まりかえった闇にそれだけが音────大神殿、神主寮。
その中庭の一番高い木の枝に一人の少年がいた。そこからは、大神殿を一望することができる。少年は、しばらくかがり火で浮かび上がった大神殿を眺めていた。やがて、その面に不敵な笑みを浮かべ、夜の大神殿へと降り立って行った。
風がやんだ。後に残るは──── 漆黒の闇。
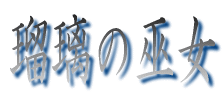

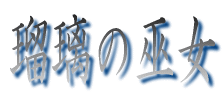

 「兄君!」
「兄君!」 「莉・・・央・・・。」
「莉・・・央・・・。」 「ほら、痛いんじゃない。さっさと服脱ぐ!」
「ほら、痛いんじゃない。さっさと服脱ぐ!」