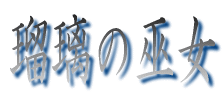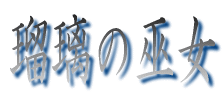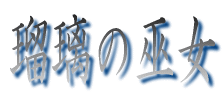

第1話
序
時は古代。人は、自分たちの住まう土地を光ヶ原と呼んだ。そこに住む人々は、天の天原(あまつはら)におわす天日神(あまつひのかみ)を信仰し、天日巫女(あまつひのみこ)と呼ばれる巫女が、天日神の御声を聞き、それによって大神殿の神主たちが光ヶ原の政治を執り行っていた。平和な時流(とき)が流れていた。しかし、長き時流の中で神主たちの中には、自らの利ばかりを欲する者も現れた。そして平和な光ヶ原の水面下で、だんだんと歪みが生じ始めた。そして、その歪みは、中央都から遠く離れた辺境の地にも、小さな波を広げたのだった。
壱
莉央は、中央都から遠く離れた辺境の村、阿瑚の里に住む普通の少女。際だって美人と言うわけではないが、すっきりとした目鼻立ちで、里の娘にしては珍しい瑠璃色の瞳は人を惹きつける力があった。長い黒髪を後ろで一つに結っている。早くに父親を亡くし、母親と二人で仲良く暮らしていた。
ある日、大神殿からの使者が里にやってきた。使者は言った。
「この里に住む瑠璃色の瞳の乙女を、天日巫女候補の天巫女(あまつみこ)として大神殿に仕えさせよ!」
それは、間違いなく莉央のことだった。しかし普通天日巫女は、天巫女と呼ばれる巫女の中から選ばれるので村の神殿の天巫女でもない莉央は困惑する。母親も、莉央を手放そうとはしない。しかし、大神殿からの命は絶対。逆らうわけにもいかず、出発の日は明後日に迫った。
「あと三日・・・か。あと三日で、母さんともこの里ともお別れ・・・。」
村の端を流れる川の河原で、莉央は一人で立っている。と、そこへ里の娘たちが洗濯にやってきた。
「莉央?どうしたの、こんなところで・・・。」
「そうよ、未来の天日巫女様!」
「神殿に行かなくていいの?中央都で恥かかないように、巫女として最低限の儀礼を出発までに身につけるんでしょ?」
「いいなあ、中央都へ行けるなんて!」
娘たちは口々に言う。莉央は、思わず叫んだ。
「ちっともよくない!中央都になんか行きたくないっ!!」
「莉央?」
莉央は泣いていた。
「行きたくない・・・。わたし、この里が大好きなの。この里の人もみんな・・・。春の雪解けの喜びも、夏の太陽の厳しさと優しさも、秋の実りも、冬の寒さも、教えてくれたのは、この里だった。これからの長い時間、この里以外で時流を過ごすなんて信じられない・・・。大神殿の天巫女になったら、きっと、二度とここへは戻ってこれないわっ。」
そう言って莉央は駆けだした。
そして、出発の日。里のみんなが見送りに集まった。莉央は、立派な巫女装束を着て、大神殿の輿に乗っていた。いよいよ出発というその時、
「莉央!」
数人の娘たちが輿の前に走り出て、花の首飾りを差し出した。
「莉央っ!これ、朝摘みの翡翠草で作ったの!辛いことあると思うけど、辛かったら、私たち思い出して頑張って!!」
「みんな・・・ありがとう・・・。」
それ以上、言葉を続けることはできなかった。輿はゆっくりと動き出し、みんなの顔が離れていく。翡翠草の首飾りに、莉央の涙が落ちた。それはまるで、朝露のようだった。
弐
七日輿に揺られたあと、二日間舟に乗って海を渡り、さらに輿で五日。やっと、中央都の大神殿にたどり着いた。莉央は、かなり疲労していたが、休む間もなく禊ぎをさせられた。そして、天巫女の装束に着替え、他の天巫女たちに紹介された。
「みなさん、今日から天巫女として仕えることになった莉央さんです。不慣れで戸惑うことも多いでしょうが助けてあげて下さいな。」
年長者らしき巫女が言った。が、他の巫女の反応は冷たい。ひそひそと何か話している。そのあと、部屋に案内されて、やっと休むことができた。と、隣から話し声が聞こえた。
「聞きました?新しい巫女のこと。」
「ええ。なんでも、普通の娘だったんですって?それも、田舎の!」
「そうそう!天巫女でもなかった娘がいきなり大神殿の巫女だなんて・・・。」
「噂だと、天日巫女候補なんですって。」
「ええ?まさか。」
「神主衆が話しているのを聞いた方がいらっしゃるの。」
「まあ、生意気。ますます気に入らないわ。」
莉央は、大きな衝撃を受けた。望んできたんじゃないのに、こんな風に言われるなんて、悔しくて、涙が出そうだった。疲労も重なってか、その夜莉央は熱を出した。翌朝、目覚めた莉央の横には、巫女姿の少女が一人いた。
「あ、おはようございます。熱は・・・もうほとんどひいたみたいですけど、気分はどうですか?」
「貴女は・・・?」
「寧禰です。困ったことがあったら何でも言って下さいね。私にできることなら何でもします!」
寧禰は、自分の胸をドンと叩いて言った。莉央は、気持ちが軽くなった気がした。
「貴女は、私のこと嫌いじゃないの?」
「え!?どうしてですか?」
寧禰は、心底驚いた様子だ。莉央は、少し自虐的に言った。
「昨日聞いちゃった。他の巫女様たちは、私のこと気に入らないみたい。当たり前よね。天巫女でもなかった奴がいきなり大神殿に仕えるなんて・・・。」
「そんなことないっ!!」
寧禰が叫んだ。
「そんなことない。私、一目で貴女が好きになったもの。貴女の瞳、すごく綺麗。みんな、悔しいからちょっと意地悪言ってみただけで・・・だから、そんな風に言わないで・・・下さい。」
顔を真っ赤にして寧禰は一気に言った。
「ありがとう。敬語使わないでいいよ。よかった、貴女がいてくれて・・・。」
莉央は、そう言うと、また眠ってしまった。二日後、莉央は全快し、寧禰ともすっかり仲良くなった。しかし、他の巫女は相変わらず莉央に冷たかった。莉央は、なるべく気にしないようにして、巫女の修行に精を出していたが、それがますます反感を買った。最初の頃は、陰口だけだったが、そのうち嫌がらせまでしてくる巫女も出てきた。特にあからさまだったのが、莉央より三つ年上の咲妃という巫女だった。ある日、莉央は天日神の祭壇に聖水を供える役を言いつけられた。井戸から聖水を汲み上げて、祭壇へ運んでいた莉央を見た咲妃は、足をかけて莉央を転ばせた。
「まあっ、なんて事!大切な聖水をこぼすなんて!!それに、私の着物まで濡れてしまったじゃないの!まったく、水運びなら田舎でやってたから、得意だと思ってたのに!」
「なっ・・・!貴女が転ばせたくせに!」
莉央は思わず叫んで、後悔した。これこそ相手の思うつぼだ。ちょうどそこへ神主衆の一人が通りかかった。神主衆とは、大神殿のみの役職で、大神殿の長、老神主の下に就く者のことをいう。
「おや?何かあったのか?」
途端に咲妃は猫なで声で訴えた。
「嵯峨様!聞いて下さいまし。この新入りの巫女が聖水をこぼしてしまったんですの。それを、私のせいだと言うんですのよ。私は、何もしていませんのに・・・。」
神主衆の一人、嵯峨は、莉央を一瞥すると、少し厳しい口調で言った。
「本当かね?自分の失態を人のせいにするのは、大神殿に仕える者として恥ずべき行為だ。ちゃんと謝罪しなさい。」
「ですがっ・・・。」
「いいから、謝罪しなさい!」
見ると、咲妃が勝ち誇ったような顔で見下ろしていた。そして、
「いいんです、嵯峨様。まだ、こちらでの日が浅いので不慣れなんでしょう。今度から気をつけなさいな。では、失礼。」
と、言って去っていった。嵯峨も、
「聖水を汲み直しておくように。」
とだけ言って、去った。残された莉央は悔しくてたまらない。転がった桶を拾うと、思い足を引きずって、聖水を汲み直し、祭壇に供えた。天日神の祭壇は、天日神が、邪神、黄泉闇神(よみつねのかみ)を死の世界、黄泉原(よみつはら)に封印している所を描いている。手には、御劔を持っていて、これを象った紋様は、大神殿の象徴である。莉央は、泣くまいと思っていたけれど、とうとう泣き出してしまった。故郷の里が懐かしく思い出される。出発の日友から貰った翡翠草の首飾りは、不思議なことにまだ枯れていない。泣き顔を見られないように、莉央は、祭壇のある庭園の奥へと入っていた。
『莉央』
誰かに呼ばれたような気がした。庭園のさらに奥から聞こえてくるようだ。莉央は、どんどん奥へと入っていった。
「何・・・これ?」
莉央がそこで見つけた物は、巫女姿をした、氷付けの少女だった。
参
その少女は、莉央にそっくりだった。瞳は閉じられているが、きっと瑠璃色なのだろう。ぱあっ。一瞬、氷が光ったような気がした。莉央は、恐る恐る氷に触れてみた。途端、
「きゃあっっ!」
一瞬、体の感覚を失って、気がつくと、不思議な空間にいた。そして、目の前には、あの少女がいた。少女は目を開いていた。やはり、瞳は瑠璃色だった。
『莉央・・・。私の声が聞こえますか?』
唇は開いていないのに、少女の声が聞こえた。
「貴女は・・・誰?」
少女はにっこり笑っていった。
『私は貴女、貴女は私。』
「え?」
少女は続けて話す。
『私の名は琉莉夜(るりや)。現天日巫女にして天日神が創りし神の子。そして、貴女も。』
「何を言ってるの?」
莉央は戸惑いを隠せない。
『我らが父神、天日神は遠き昔、世界を三つに分けた。神々が住まう天原、人々が栄える光ヶ原。そして、邪神黄泉闇神を封印した黄泉原。しかし、今、人々の光ヶ原に歪みが生じ始めているのです。封印したはずの邪神黄泉闇神が、復活しようとしています。普通、死者は天日神の導きを受け、新しい生を受けます。しかし、黄泉闇神は心迷った死者を黄泉原へと導き、自らの下僕とし、光ヶ原に影響を及ぼしているのです。天日神は、完全に黄泉闇神を消滅させるために、私を創ろうとした。しかし、神の力は強大で私ひとりの身には収まらず、二つに分けました。それが莉央、貴女です。貴女は、その身に神力を秘めているのですよ。』 「嘘よっ。」
『いいえ、聞いて下さい。それでも神の力は強かった。そこで、私は、神の力を制御する御道具、天日鏡(あまつひのかがみ)を賜りました。しかし、それを黄泉闇神の下僕と化した者に奪われてしまったのです。そのため、力を制御できなくなった私は氷にこの身を拘束されているのです。』
「やめてっ!じゃあなに?私は創られた者なの?今までの記憶も、母さんも、全部?」
莉央が叫ぶと、空間が少し歪んだ。
『莉央!落ち着いて聞いて下さい。ここは亜空間なのです。うっかり神力を解放するとどうなるか分かりませんよ。認めたくない気持ちは分かります。けれど、事実です。お願いです。天日鏡を探し出して下さい!光ヶ原の人々のためにも。黄泉闇神の邪力は、老神主にまで及ばんとしています。』
「聞きたくないわ!!」
莉央は、耳をきつくふさいだ。しかし、声は聞こえてくる。そう、心に語りかけられていたのだ。
『莉央、確かに私は全てを創られた者です。でも、貴女は違う。基を創ったのは神です。しかし、今まで貴女が過ごした時流は、貴女自身で創った時流なのです。お願い、貴女を育んだ時流を、場所を、人を守るために、天日鏡を探して下さい。私はここから動けない。神殿にいる天日巫女も、虚像なのです。だから、貴女を呼び寄せたのです。お願い。』
莉央は、自分が育った里を思い出していた。さらさらと流れる小川、生い茂る木々、季節ごとにみのる畑。秋の田。そして、人々。自分が神力を秘めているなんて信じることはできないけれど、これらを無くすのは嫌だと思った。顔を上げると、まっすぐ琉莉夜を見て言った。
「わかった・・・。全部、信じた訳じゃない。認めた訳じゃない・・・けど、無くしたくないモノがあるから・・・。それに・・・、このままここにいるのも窮屈だし。」
『莉央・・・!ありがとう。では、これを。』
琉莉夜は、嬉しそうな顔をすると、瑠璃色の勾玉を差し出した。
『これを通じて、私と話すことができます。今度の新月の夜、西に向かって出発して下さい。』
「西へ?」
琉莉夜はにっこり微笑むと、また目を閉じた。すると───
「あれ?元の場所だ。」
目の前には氷付けの少女がいた。そして、莉央の手の中には瑠璃色の勾玉があった。そして、新月の夜。密かに旅支度を終えた莉央は、いよいよ出発しようと部屋を抜け出してギョッとした。
「寧禰!?なにその格好・・・。」
目の前に、旅支度をした寧禰がいたのだ。
「私も行くわ。」
「行くって・・・?」
「全部知ってる。琉莉夜様に頼まれたのよ。莉央を助けてやって・・・って。」
寧禰は、にっこり笑って、困惑している莉央の手を引いた。
「こっちに抜け道があるの。」
「寧禰!いいの?」
寧禰は、笑って頷いた。莉央は、初めて寧禰に会ったときのように、ホッとした気持ちになった。寧禰の言っていた抜け道を抜けて、外へ出た瞬間、
「おい。」
と、声をかけられた。二人は、思わず身をすくめた。そこに立っていたのは、何度か顔を見たことのある神主見習いの少年だった。年は十七〜十八といったところ。
「俺はトキ。神の子に命じられた。俺も行く。」
「ええ!?」
二人の困惑をよそに、トキはすたすたと歩き始めた。
「ちょっと、ちょっと待ってよー!!」
かくして、天日鏡を探す、三人の旅が始まった。