 |
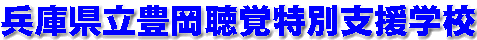 |
![]()
学校経営の重点
兵庫が育む こころ豊かで自立した人づくり
―学び、育て、支えるひょうごの教育ー
![]()
校 訓
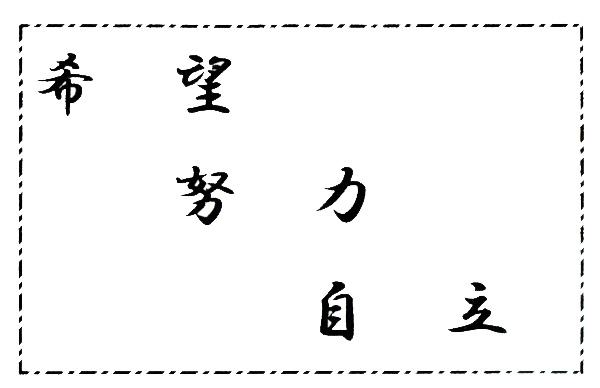 |
教育目標
「自分らしく成長し、協働しながら、学び、生活の質を向上する」
幼児児童生徒が希望や目標を持ち、その達成に向けて、人間関係を形成し、支援環境を整えながら努力を続けることで、内面の成長を遂げ、障害による学習上又は生活上の困難を改善・克服し、学校・家庭・地域生活の自立、将来の社会的自立及び社会参加するために必要な意欲・態度・能力を育む。
豊聴『かがやき』ビジョン
豊聴『かがやき』ビジョンへのリンク
豊聴『かがやき』ビジョン(ポイント) へのリンク
豊聴カリキュラムマネジメント
豊聴カリキュラムマネジメントへのリンク
豊聴の特色ある教育
豊聴の特色ある教育へのリンク
5つの視点・5つの基礎モデル
5つの視点・5つの基礎モデルへのリンク
学校経営の重点項目
ア 「社会に開かれた教育課程」の編成及び幼稚部から中学部まで系統的・継続的なキャリア教育の視点を取り入れ
た授業計画を作成する等のカリキュラムマネジメントを進める。
イ 研修テーマや教育課題に基づいて、教職員の特別支援教育の専門性を高め、学び合い高め合う学習文化を
培い、主体的・対話的・深い学びの視点を取り入れた授業改善を進める。
ウ 居住地校との交流及び共同学習の充実に向けた調査研究を推進し、地域との関係を深め、社会で自立できる力
を育むとともに、交流校等において障害についての理解を深め、心のバリアフリーを育み、相互理解を深める機
会とする。
エ 地域の特別支援教育のセンター的機能及び「但馬地区特別支援学校ネットワーク
オ 各学部、寄宿舎との連携や活性化された組織運営により、教職員の協働体制を築き、教育目標の達成や教育課
題に取り組む。
カ 教職員の勤務時間の適正化を図り、子どもに向き合える環境づくりに努めるとともに、相互支援による同僚性を
高める等風通しのよい職場づくりに努める。
キ 家庭・地域・関係機関との積極的な連携や情報共有を図りながら、協働関係を構築し、チーム学校づくりを推進
する。
ク 学校評議員等と連携した学校評価等を通したP(計画)−D(実行)−C(評価)−A(改善)サイクルマネジメントに
より学校改善を進める。
教科指導及び生徒指導の重点
(1)教科指導
ア 幼児児童生徒が、社会の変化に対応して主体的・創造的に生きる力を育てるため、自ら学び、考え、行動する
力を育成する。
イ 個の実態に応じた学習内容や学習形態等を工夫し、幼児児童生徒それぞれに達成感や成就感を味わわせる。
(ア) 各教科の基礎・基本の定着を図り、主体的に生きる力を高める。
(イ) 障害の状態や発達の段階、特性等を的確に把握し、個に応じた指導の充実を図り、一人一人の可能性
やよさを伸ばす。
(2)生徒指導
ア 心のふれあいに基づく好ましい人間関係を育成し、幼児児童生徒の心身の調和のとれた発達を支援し、楽しい
学校生活を体験させる。
イ 学校行事、児童会・生徒会活動等、集団活動を通して、個性を伸ばし幼児児童生徒の自主性・主体性を育成す
る。
ウ 幼児児童生徒の人権に十分配慮し内面的な理解に努めるとともに、生きる力の基盤となる基本的生活習慣を
確立する。
エ 学校、寄宿舎、家庭及び地域社会が、それぞれの持つ教育機能を生かすよう連携を密にし、ゆとりある環境の
中で幼児児童生徒の社会性を育成する。
(3)総合的な学習の時間
ア 体験的な学習を積極的に取り入れ、学び方やものの考え方が身につくような特色ある教育活動を展開する。
イ 情報機器を有効に活用し、教科や学年の枠を越えた横断的・総合的な学習を進め児童生徒が主体的・創造的
に取り組む態度を育てる。
健康管理に関する指導の重点
(1)健康・安全教育の重点
ア 震災の教訓を生かし、語り継ぐ防災教育を推進する。
イ 体育、自立活動、課外活動の時間の他、学校教育の全領域のなかで体力及び健康の増進を図るとともに、危
機管理に対する意識を高める。
ウ 各種の行事等を通して、身体を動かし運動することの楽しさや喜びを味わわせる。
エ 定期健康診断などの結果に基づいて、個々の幼児児童生徒に適した運動、栄養、休養等を設定し、健康の保
持増進を図る。
オ 保健指導、給食指導を通じて、健康な生活を営むために必要な知識や技能を身につけさせる。
(2)健康・安全の管理
ア 学校内・外から災害や事故の発生を未然に防止する日常点検を一層強化する。
イ 緊急時の対処の仕方について、避難訓練等を通して防災安全教育を徹底する。
ウ 次の行事を実施して、施設・設備の安全を確保し、幼児児童生徒が安全に行動できる能力や態度を育てる。
(ア)学校施設設備等の安全点検〈学期に1回〉・教室等の安全点検(月に1回)
(校内の危険箇所の発見と補修等、安全への意識啓発)
(イ) 避難訓練〈年間3回〉〈寄宿舎は年間4回〉
(火災や地震における多様な場面を想定して、安全に避難する方法の習得)
(ウ) 交通訓練や朝の通学指導(交通安全意識の向上)
エ 全教職員が心肺蘇生法等の応急処置ができるよう、消防署と連携し研修会を実施する。また、保護者を対象と
した心肺蘇生法の研修会を実施する。
オ 家庭、医療機関、警察、消防署等関係機関との連携を密にし、日頃からの協力体制を確保する。
人権尊重の教育
ア 一人一人のよさや可能性を十分に伸ばし、社会生活における自立・向上の精神を培い、自己の判断と責任で主
体的に行動できる力を育成する。
イ 教職員自らが思いやりと人権尊重の意識を高め、幼児児童生徒たちの思いやりの心を一層育み、お互いの個
性を認め、尊重し合う好ましい人間関係と態度を育成する。
ウ 地域社会への啓発活動を通して、人権意識を高め、障害児(者)に対する正しい理解を広め、豊かな人間関係
を築く中で、共に生きる社会の実現を目指す。
自立活動の指導
(1)幼児児童生徒一人一人の障害の状態や発達の程度に応じた指導を推進する。
(2)自己の障害を受容し、自己を認識する力を育成する。
(3)聴覚の活用や発語への意欲を高め、基礎的な言語力、表現力を向上させる。
(4)手話や身振りなどの個に応じた適切なコミュニケーション手段の選択・活用に努め、指導内容・方法を工夫する。
(5)障害に基づく困難を改善・克服する意欲と、知識・技能・態度を身につけさせる。
研究テーマ
(1)学 校:子どもたちが主体的に活動できるための支援や指導の工夫
(2)寄宿舎:生活自立・社会自立をめざして〜卒業後の姿を見据えて〜
地域の特別支援教育のセンター的機能
(1)但馬地域を対象にした通級指導教室を充実させる。
(2)但馬・丹波地域を対象にした教育相談活動を推進する。
(3)地域の特別支援教育担当者に向けた研修講座を企画し実施する。
(4)但馬・丹波地域の教育・医療・福祉・保健機関等との連携・協働を充実させる。
(5)但馬地区特別支援学校ネットワーク会議による連携のもとで各学校の専門性を生かして、但馬地域の特別支援教
育を支援する。
(6)但馬・丹波地域の、特別支援学校ネットワーク連絡会議による連携のもとで、あらゆる障害種に対応する広域支援
体制の構築を推進する。
キャリア教育・就労支援
(1)進路指導
ア 個別の教育支援計画に基づいた長期的な展望の下に、校内・校外関係機関との密接な連携を図り、一人一人
に応じた進路指導を行う。
イ 保護者との連携を密にして、進路の懇談の内容をふまえてきめ細かな進路指導を行う。高等部進学に対しては
関係する学校との緊密な連携を通して、多様な進路情報を収集し、学校見学や体験入学等による情報提供に
努める。
(2)キャリア教育・就労支援
ア 個々の課題やニーズに応じた個別の教育支援計画を活かして、将来の自己実現を図ることを目指した
キャリア教育を推進する。
イ 外部人材等の活用により、学校卒業後の就労や生活についての幼・小・中学部段階に合った情報収集に努め
、将来の主体的生活と社会参加に向けたキャリア教育を推進する。
幼児児童生徒数
| 幼稚部 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | 計 | |||
| 1名 | 1名 | 2名 | |||||
| 小学部 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | 4年生 | 5年生 | 6年生 | |
| 1名 | 4名 | 3名 | 3名 | 2名 | 2名 | 15名 | |
| 中学部 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | ||||
| 1名 | 2名 | 5名 | 8名 | ||||
| 合計 | |||||||
| 25名 |