総合健康類型の授業報告です
1年生総合健康類型特別授業「チームビルディング」
令和4年12月13日(火)
大阪人間科学大学 心理学部 心理学科 准教授 村上雅彦 様
日常のさまざまな場面でチームワークの必要性を実感している人は多い。この授業で簡単なレクリエーションを通してチームワークを高める方法について学びました。
1 アイスブレイク(緊張をほぐすゲーム)
二人組から始まって人数が増えていきました。
はじめは黙って取り組んでいましたが、課題が少し難しくなり会話が増えました。
2 イニシアチブ(課題解決のゲーム)
紙コップキャッチ 2人から4人へ、バンダナ・リフティング3人から4人、ヘリウム・スティック7,8人あやとり、人間イス
設定された精神的・肉体的課題に対してメンバー一人一人の持ち味や能力を出し合い、グループで協力して課題を解決するプログラムでした。
コミュニケーションが促進される(実際に活発な目的遂行のための会話が充実していました。)
チームワークが高まる(来年から一緒になるみんなは今回の講義と実習で問題解決のためのコミュニケーションが次第に取れて、一体感が表れていました。)
先生からも「これだけ一体感のある反応されたので、説明の時間を少なくして体験していただいた。生徒さんが真剣に取り組んでくれて、こちらも大変楽しく授業をすることができました。」と言っていただきました。)
最後に、実際にゲームをやって一体感が高まり、そこから心理学を学ぶ意義についてそれぞれの経験に基づいた原因(なぜだろう?)と対策(どのようにすればいいの?)の究明
心理学を学ぶことで、自分の経験とは異なる視点で原因と対策を考えることができることを学びました。



左からトン・トン・キャッチ、ヘリウム・スティック、人間イス
1・2年生総合健康類型「神戸マラソンボランティア」生徒会より2年生参加
令和4年11月20日(日)
3年ぶりに開催された神戸マラソン大会に、3年ぶりに参加しました。2万人が全国から集まって、震災復興をきっかけに開催されるようになって今年で10回目を迎えます。感謝がスローガンの大会でその趣旨も事前学習として取り組んできました。
当日の朝は暗い中に集合し、特にリーダー担当の2年生は6時に阪急三宮から30分ほどかかる場所に小雨交じりの空模様の中、集合しました。
ボランティアスタッフのウインドブレーカを着て、ヒマワリをイメージした黄色の手袋を着用して集合しました。
広い公園の中で周囲をトラックが配車されていました。ランナーの方の荷物をお預かりして、トラックに積み込みました。ランナーの方から「ありがとう」の声をかけていただきました。
荷物の積み込みが終わると、ゴール付近に移動します。移動中にスタート直前の大勢のランナーを見ながら移動しました。2万人のランナーの方の荷物の一部をお預かりし、ボランティアのすばらしさを実感しました。
ゴール付近でのトラックからの荷物の積み下ろし作業は、番号順に素早く荷物を置いて行きました。いったん終了したかと思ってもまだ作業の済んでいないトラックの荷物を並べるために別会場へ移動。「もうひと頑張りしよう」と声をかけて励ましあいながら一心に取り組んでいました。ランナーの皆さんの感謝の言葉を思い出し、神戸マラソンの趣旨をみんなで共感しながら、最後までやり切ってくれました。
ボランティアの経験をしたことで、自分ができる社会とのつながりを感じていたように思います。神戸マラソンの実行委員会の方からもねぎらいの言葉をかけていただきました。



左からスタート地点の荷物預かり、トラックに積み込み、荷物積み下ろしと整理
2年生 講義⑨「幼児期に大切な遊びをしよう 」
令和4年11月18日(金)
講師:園田学園女子大学短期大学部 久保田 智裕 様
久保田先生が園長をされていた幼稚園での様子を見ながら、幼稚園で身に着ける内容について講義をしていただきました。講義に続いて、実習を通して幼児期の子どもたちへの接し方について学習しました。卒業後は保育士として勤務される本校の卒業生2名も一緒に参加して分かりやすく実習ができました。
保育園児の生活の様子について映像を見ながらお話をしていただきました。園長室へ招待、お弁当タイムや泥団子づくり、園長先生への手紙、似顔絵など園長先生との交流の様子や縄跳び遊びや泥遊びでの先生や園児同士とのかかわりについても園児はよく覚えていて、幼稚園の先生は大切に聴き取っておられました。人間性や社会性を身につけさせる上で、とても大事な時期だと改めて感じることができました。後半は手遊び歌から始まり、園児の気持ちになって実習ができました。先輩のお手本や実技もあって、少人数の手遊びから、だんだんかかわる人数が増えてクラスのみんなも大変仲良くなって実習ができていました。人とかかわって生まれる楽しい気持ちが今回の授業で実感できました。
今度は保育園児のみなさんを迎えて交流会を実施します。それまでに、会の流れやそれぞれの準備物や説明方法や詳細についても検討、準備を進めてもらえたらと思います。



左から講義の様子、実習の様子
2年生 健康総合Ⅰ⑧「幼児への遊びについて」
令和4年11月4日(金)
講師:わかばの森保育園 主任 龍 千恵
本日はわかばの森保育園より龍 千恵先生にお越しいただき、講義と実習を通して幼児期の子どもたちへの接し方について学習しました。
はじめに「幼児期の終わりまでに育って欲しい姿」についての講義では、先生の経験談も踏まえてお話をしていただきました。その中でも印象に残っていることは、遊びを1つ行うのにも、“何のためにこの遊びをやるのか”“この遊びを通して、子どもたちに何を学んでほしいのか”をしっかりと考えたうえで行っているということです。この時期の子どもたちは、とにかく自分中心で物事を考えるというお話もあったように、そんな子どもたちに対 して人間性や社会性を身につけさせる上で、とても大事な時期なのだと改めて感じることができました。
実際に交流する5歳児の皆さんの体育大会、運動遊びや外遊びの様子や身体計測時の年長さんの年下の子たちに対しての協力の様子等の映像を紹介していただきました。保育園の年長さんの成長ぶりを見せていただき、幼児教育の素晴らしさと難しさを実感できました。
12月20日には、実際にわかばの森保育園より園児のみなさんに来校してもらい、体育館でいっしょに触れあう授業を行う予定です。それまでに、 少しでも幼児期の発達の特性を理解した上でお互いに楽しい時間を過ごすことができるよう、しっかりと学習を積んでもらえたらと思います。


2年生 講義⑦「臓器移植について」令和4年10月21日(金)
3年生 講義⑪「臓器移植について」令和4年11月17日(木)
講師:急性重症患者看護専門看護師
兵庫県臓器移植コーディネーター 杉江 英里子様
昨年度は新型コロナ感染症の影響で実施できなかった3年生にも講義を実施できました。
まず初めに、臓器移植コーディネーターは臓器提供を勧める立場ではありません。あくまでも臓器提供を勧める勧めないのいずれでもなく中立な立場である専門職としてお話を聞きました。
1 臓器医療について
臓器移植は、病気や事故で臓器が機能しなくなった場合に、健康な臓器を移植して、機能を回復させる医療。
提供方法の種類と違い
生体臓器移植 提供者の安全が優先
死体臓器移植 脳死後の提供と心停止後の提供
心停止と脳死の違い
心停止は呼吸の停止、心拍の停止、瞳孔の散大・対光反射の消失でこれを死の3兆候
脳死は脳の機能全てが消失している状態。脳死のほうが提供できる臓器は多い。
2臓器医療の歴史と現状
日本と世界の臓器移植医療について。臓器移植法について本人の書面による意思表示と家族の承諾が必要。15歳未満は提供できないけれど改正臓器移植法は家族の承諾で15歳未満でも提供できる。移植を待っている人。2パーセントの奇跡。日本と諸外国の違い。
3臓器提供の実際
海外と日本のドナー提供数を見たときに、海外のほうが圧倒的に多い。考えられる要因は意思表示方法の違いや死の定義の違い、他にも法律・制度の違いがある。
臓器提供意思表示カードは何回でも書き直せる。意思表示は「したくない」ひとのため。
摘出手術、臓器提供後。臓器提供者に対して感謝状やサンクスレターが送られている。移植手術を受けた方々のスポーツ大会が実施されている。
今回の講義を受講して命の大切さを改めて知ることができ、とても良い時間になりました。
2年生の様子

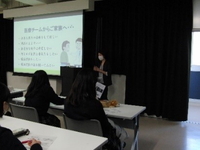

臓器移植医療について
3年生の様子


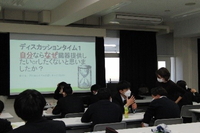
臓器移植医療について
2年生 健康総合Ⅰ 「HUG避難所運営ゲーム」
令和4年10月8日(火)11日(火)
本校は兵庫県防災ジュニアリーダーの活動に継続して参加しています。今年度は校内で避難所運営ゲームを実施して、防災に関する意識を高めていこうとするアクションプランを計画しました。
最初は既成のゲームを利用して実施予定でしたがお借りすることができず、ゲームの手作りを計画しました。避難してくる人たちを想像した個人カード作成をクラスに説明して、カードが完成しました。他にもイベントカード、体育館の見取り図、教室の見取り図など1時間で作成。実施時間も1時間と限られた時間の中でリーダーシップを生徒が務め、当日のゲームに臨みました。
次々と避難所にやってくる方の振り分け、また次々と起こってくるイベントに対応していきました。電気が完全に止まった、本校の体育館をどうやって活用していくか、2つのグループに分けて実施していきました。避難所に支給されたおにぎりの数が避難所にいる人より少ない、使い捨てカイロが20個届きました。着替えるスペースを作ってほしいなどと次々やってくるイベント出来事に、各グループで答えを出して運営をしていきました。終了後は2つのグループで意見交換しました。
【感想】避難者が絶え間なく来て、体育館の通路の確保ができなかったり、対応しきれないことが課題だと思いました。実際にはもっとたくさんの方がこられたりパニックになると思ったので、このゲームでどれだけスムーズに進められるかがポイントになってくると考えました。
カードに書かれている人の特徴をよく見て、どこに置いたらいいか考えて即座に判断するのが難しかった。他のグループでは通路をうまく使っていてそういう考え方もあると思いました。災害への備えや冷静な判断がとても大切だと思いました。



左から避難所運営ゲーム説明、個人カード作成、避難者が体育館に
3年生 健康総合Ⅱ 講義⑦「手話講座」
日時:9月08日(木)5,6時間目
9月15日(木)5,6時間目
10月13日(木)5,6時間目
10月27日(木)5,6時間目
11月05日(木)5,6時間目 計10時間
講師:宝塚市 加藤めぐみ 様 手話通訳橋本ちよ様
宝塚ろうあ協会から講師の先生にお越しいただき、手話の授業を行いました。授業を通して日常生活における様々な場面で使える手話を教えていただき、和気あいあいとした雰囲気の中で、みんな一生懸命に手話を覚える姿が印象的でした。 全10時間実施された授業の終盤には、手話で自己紹介をすること、そして加藤先生が表す手話を読みとることができるようになりました。 最後に加藤先生から『手話を覚えてできるようになることも大事だが、耳の不自由な方に寄り添い、自分ができる方法でコミュニケーションを取ろうとすることが大切だ。』というお話をしていただきました。 今回学んだことを、今後の日常生活に活かしてほしいと思います。



1〜2枚目は自己紹介練習、3枚目は自己紹介発表の様子です。
2年生 講義⑥「人の体を治す−鍼灸師(しんきゅうし)・柔道整復師の話(体験型)」
日時:令和4年9月9日(金)
講師:大阪テクノロジー専門学校 専任教員 山下 浩平 様
- 鍼灸師は…人の体を治療することができる医療従事者です。
頭と目、顔の症状、首・肩・腕・背中の疲れ、足と腰の疲れ、内臓の疲れ、婦人科系の症状、心の疲れなどのWHO(世界保健機関)が認めた鍼灸適応疾患の治療 - 日本スポーツ協会公認アスレティックトレーナー(AT)は…人々の健康をサポートするスポーツ指導者です。運動愛好家から競技選手まで様々なアスリートを医科学的にサポート。
- スポーツ現場での鍼灸師・ATの役割
(障害発生前)健康管理+トレーニング+コンディショニング【予防的鍼灸】
障害発生
(障害発生後)応急処置+アスレティックリハビリテーション+競技復帰【治療的鍼灸】 - スポーツ現場での鍼灸師・ATの役割
鍼灸治療例 - 実習



2年生 講義⑤「スポーツの仕事」
日時:令和4年9月5日(火)
講師:大阪成蹊大学 経営学部 スポーツマネージメント学科 教授 村田正夫 様
スポーツ産業は将来性のある領域
スポーツ産業規模を3倍にすることが目指されている(スポーツ市場を拡大し、その収益をスポーツ環境の改善に還元し、スポーツ参画人口の拡大につなげるという好循環を生み出すことにより、スポーツ市場規模を5.5兆円から2025年までに15兆円に拡大することを目指す)2015年5.5兆円〜2020年10.9兆円〜2025年15.2兆円(スポーツ庁より)
Question1:(スポーツを活用して何ができますか)スポーツが社会活性化等に寄与する価値
スポーツを通じた「地域活性化」、「健康増進に関する健康長寿社会の実現」、「経済発展」、「国際理解の促進」等
Question2:スポーツに関連する仕事にはどんなものがあるでしょうか…
スポーツ用具製造・販売・営業、スポーツ施設建設、スポーツの報道(TV新聞メディア)、スポーツスクールのサポートコーチ、スポーツ行政・競技団体、スポーツチーム・クラブ運営、スポーツをする人をサポートするプロ選手・指導者のエージェント、スポーツボランティア
Question3:スポーツはなぜ、「産業としての商品になり得るのか」・・・
①「スポーツ」は、そもそも「商品」として生まれたものではない
スポーツというものは元々、人々が「Play(遊び)するもの」として誕生したため、「商品」ではなかった。
②メデイアの発達によって、スポーツを「みる(watch)」ということが一般化し、次々と生産されるスポーツの試合が「消費」されることによってスポーツビジネスが発展していった。
講義後の生徒の感想より
スポーツというのは最初、競技というイメージがあって、勝負するというイメージだったから嫌いでした。今回の授業で、スポーツの持つ本質を知り、遊びというのを心がけてスポーツすることで楽しめると思ったので、これからは、遊ぶイメージで楽しんで、スポーツにかかわっていきたいと感じました。
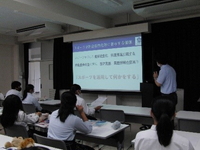


3年生 講義⑤「防災・減災」
日時:令和4年6月13日(月)
講師:神戸学院大学 現代社会学部社会防災学科 安富 信 様
- 「災害について」災害において、大切なのは危機管理
- 新型コロナ感染症と災害について
- 日本の梅雨 線状降水帯による被害
- 日本の台風 1年に来る台風の数は
毎年のように起こる水害に人はなぜ逃げないのか - 防災教育の大切さ 阪神淡路大震災 東日本大震災
- 今後の防災・減災について
南海トラフ巨大地震、首都直下型地震は大阪や近畿にも発生する可能性は高い。今からでも遅くない。対策を練り、人々の意識を変える。コロナの失敗を教訓に。
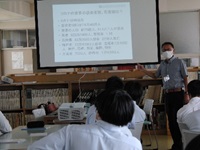

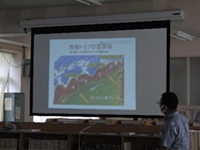
2年生 講義④「パラダイムシフトで自己コントロール感を高めて主体的に生きる」日々の高校生活を充実させて夢や目標の実現を手にする
日時:令和4年6月3日(金)13時15分〜15時05分
講師:神戸流通科学大学 心理学部心理学科教授 様
- パラダイムとは「ものの見方,捉え方」という意味、パラダイムシフトとは「ものの見方,捉え方を変えること」。
ものの見方捉え方を変える方法を、美点凝視という。ルビンの壺をはじめ錯覚や物の見え方を写真や映像を使って体験しました。 - 自己コントロール感を高めて主体的に生きる」とは自己コントロール感=自己選択感→自分で選択しているという実感を持ち、その結果も人のせいにしないで、遭遇した状況で最善の対処をすること
主体的に生きる=①人の指示がなくても主体的に進んで動く
=②周囲に振り回されないで生きる
→自分のHAPPY,UNHAPPYは自分が決めるもの。
講義後はたいへん前向きな表情で講義を受けたことや学習したことを主体的に受け止めてHAPPYに学習の成果が表れていたようです。



3年生 講義④「運動・スポーツの効果的な栄養の取り方」
日時:令和4年6月2日(木)13時15分〜15時5分
講師:園田学園女子大学 スポーツ栄養学部 松本 範子 様
- 「You are what you eat あなたは、あなたの食べたものでできている」
- 一日に必要な摂取カロリーについて
- 「傾聴」とは何か。PTSDと阪神大震災
- 朝食の役割・必要性について
- フードピラミッドについて



3年生 講義③「対人援助職における心のケアについて」
日時:令和4年5月26日(木)13時15分〜15時5分
講師:甲子園大学 心理学部現代応用心理学科 安村 直己 教授
- 対人援助職について・・・「心のケア」が必要な対人援助職とは
- ケア(CARE)とは何か
- 「傾聴」とは何か。PTSDと阪神大震災
- カウンセラーの三条件について
- 「同情」と「共感」の違いについて



2年生 講義③「高校生アスリートと食事〜競技力向上と食事について」
日時:令和4年5月13日(金)13時15分〜15時05分
講師:甲子園大学 栄養学部栄養学科専任講師 浅野 真理子 様
- なぜ食事をするのか?
- スポーツ選手における栄養の役割
- 5大栄養素について
- 競技力向上と食事の関係
戦略、技術、体(基礎体力・運動能力)コンディショニング(休養・食事) - 食事管理の基本的な考え方
- 食べる力を身に付けるために大切な4つの習慣
①知識 何を食べるべきか ②実行できるか ③消化吸収力 - 基本の食事の形
主食・副菜・副菜(汁物)・主菜(肉、魚介類、卵、大豆類)・牛乳・乳製品・果物 - ビタミンの重要性
糖質、脂質、タンパク質⇒ビタミンB群(豚肉・玄米・大豆)葉酸(ほうれん草・小松菜) - スポーツ選手の目指す食事とは??
日に必要なエネルギー量の目安 - 糖質、炭水化物 糖質とグリコーゲン量の回復
- タンパク質と運動量の関係 練習後の食事の摂り方 捕食(間食)のポイント
- お弁当のポイントは主食3主菜1副菜2
- 魔法の食品はない
- 様々な栄養素をまんべんなく摂取する必要がある
- 日々の食事は必ず自分の体に返ってくる継続することが重要
- 「強くなるうまくなるためにしっかりした食事からしっかりした体づくりをサポートすることが栄養士の役割です。」と、資料を交えてわかりやすく説明していただきました。

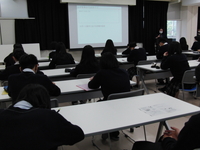
2年生 講義②「身体のしくみ〜構造と機能〜」
日時:令和4年5月6日(金)13時15分〜15時5分
講師:履正社国際医療スポーツ専門学校 理学療法学科教員 木下 拓真 様
- リハビリとは、ケガや病気になった人を 元の人間らしい生活に戻すことをいう。
- 筋肉は関節をまたいでついている。部位の重さについて。
- 理学療法士はPT、日常生活までを目指す。仕事の内容は動作の回復・改善し、トレーナーは日常生活から競技復帰までを目指します。実際の映像を見ながら仕事について理解を深めました。
- 実際の動きを見ながら分かり易く説明していただきました。


3年生 講義②「姿勢は劇的に人を変える・鍼灸師の仕事について」
日時:令和4年4月21日(木)13時15分〜15時5分
講師:履正社国際医療スポーツ専門学校 鍼灸学科 日開 美月 様
- 正しい姿勢について
姿勢をよくすると 呼吸が深くなり、自律神経が整い、不調や痛みの緩和に - 猫背のタイプについて(4種類)良い姿勢とは耳の穴、肩、股関節、くるぶしが一直線
- 鍼灸師について
- 鍼(はり)実習 実際に使用した針は、注射針よりも細い。ゆっくりたたくと意外と痛い。
- 部活を頑張る君のツボハンドブック〜セルフケア編〜
2年生 講義①「コーチング・ティーチング」
日時:令和4年4月15日(金)12時55分〜14時35分
講師:履正社国際医療スポーツ専門学校 柔道整復学科教員 篠浦 達智 様
- スポーツの語源から今日ではゲームや運動に参加するなど、娯楽の総称を意味している。
- スポーツとの関りについては、3つに分類することができる。
①行う(選手)、②見る(観客)、③支える(指導者など)の3つ。 - ティーチングとは
①答えは教える側が持っている。②知っている人が知らない人に教える。③できている人ができていない人に教える方法。 - コーチングとは
①相手自身から様々な考え方や行動の選択肢を引き出す方法。②答えは受ける人の中にある。
スポーツ指導の原理・原則を実習を交えて、わかりやすく教えていただきました。
3年生 講義①「医療の連携とは〜柔道整復師の仕事について〜」
日時:令和4年4月14日(木)12時55分〜14時35分
講師:履正社国際医療スポーツ専門学校 柔道整復学科 辻井 宏昭 様
- チーム医療について
- 柔道整復師の仕事について
- 医療という職業の将来性について
- 実習(包帯の基礎、包帯による腕の固定)
大きな包帯を実際の患者さんにするように実習していました。


 兵庫県立宝塚東高等学校
兵庫県立宝塚東高等学校