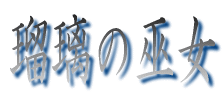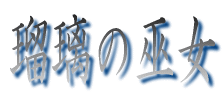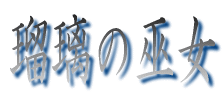

冬休み特別企画 静夜青年主役特別短編
青の瞳
静かな夜。青年は、祖父の笑顔を思い出す。いつも、優しく微笑んでいた祖父の笑顔を。自分を何より慈しんでくれた祖父。他人とは違う力を疎ましく思ったときも、その笑顔に救われた。
「じーさま、どうしてぼくにはこんな力があるの?こんな力いらない。」
少年は、その青い瞳いっぱいに涙を溢れさせながら祖父に訴えた。
「静夜、そんなことを言ってはいけない。」
「だって、ぼくがかいた犬がサンジをかんだんだ。サンジ、いたそうだった。」
祖父は、少年を抱き上げて溢れる涙を拭う。
「静夜は、サンジに怪我させようと思って犬を描いたのか?」
祖父の問いに、少年は大きく首を左右に振った。しゃくり上げながら言う。
「サンジ、犬がすきだってゆったから。」
「ほら。静夜はサンジを喜ばせようと思ってしたんだろう?だったら、静夜は悪くない。」
「でもっ、サンジがけがしたのはぼくのせいだ。ぼくに、こんな力があるからっ!もう絵なんてかかない。」
少年の青い瞳に、再び涙が浮かんでくる。
「ふえっ・・・。」
「静夜。」
祖父は、少年の名前をゆっくり呼んだ。そして、涙を拭ってやりながら、諭すような優しい声音で言葉を紡ぐ。
「今は、まだ力を上手く使えないだけだ。そのうちに、静夜の力は誰かを守る素晴らしい力になる。それに、絵が動き出すのはそれに対する想いが強いときだけ。静夜は、それだけ強くサンジを思っていたってことだ。」
「でも・・・。」
「サンジは怒っていたか?」
少年は再び大きく首を左右に振る。
「それなら大丈夫だ。」
「でも、サンジないてた・・・。」
「じゃあ、今からじーさまと一緒にもう一度サンジに謝りに行こうか。」
少年は、潤んだ青い瞳で同じく青い祖父の目を見上げた。そして、ぐすっと一回鼻をすすり、小さく頷いた。
友人の家への道々、祖父は少年の手を引きながら優しく言った。
「静夜、いつか静夜の前に護るべき人が現れる。」
「『まもるべきひと』?」
「そうだ。出会った瞬間にすぐ分かる。いいか、静夜。その人を見つけたら、何があってもその人を護るんだ。決して迷ったり、その人を見失ったりしてはいけない。」
「どうして?」
少年の問いに、祖父は笑みを浮かべて言った。
「後悔するからだ。」
そして、一瞬の逡巡の後に付け加えた。ほとんど聞き取れないような小さな声で。
「じーさまの様にな。」
微笑んでいるのは同じなのに、何か違う。少年はそう感じた。
「じーさま?」
いつもとはどこか違う、祖父の少し悲しそうな笑顔。自分と同じ青い瞳に宿る光も悲しい。その祖父の笑顔は、その日祖父が語った言葉とともに少年の心に深く刻み込まれた。
「セヤ君?」
寧禰の薄茶色の瞳にのぞき込まれ、セヤはハッとした。例によって野宿をすることになった一行。セヤは焚き火の番をしていたのだが、いつの間にか眠っていたらしい。、焚き火の火が弱くなっている。寧禰は、セヤの隣にそっと座った。莉央とトキは眠っているようだ。
「すみません、寒いですか?」
セヤは慌てて火を熾そうとした。が、寧禰はその手を押しとどめた。
「あっ、いいよ、大丈夫。それよりね・・・。」
寧禰はうつむいた。焚き火の灯りが弱く、表情はよく見えない。セヤは、黙って寧禰の次の言葉を待った。
「ちゃんと聞いておきたかったの。セヤ君言ったよね、『私は寧禰を護るためにいる。』って。どういう意味?」
「そのままですよ。私は、寧禰を護るためにいるんです。なにがあっても、護ります。」
かあっと、寧禰の頬が赤く染まる。
「でもっ、会ってから間もないのに、なんでそんなことが分かるの?」
「分かりました。初めて寧禰を見た瞬間から。」
「それって、『語り絵』の前?」
寧禰の問いに、セヤはゆるく首を左右に振った。
「あの日の朝、『語り絵』に掛けてある布を取りに行った帰り、一人の女性とすれ違いました。その方は、少しうつむき加減で悲しい瞳をしていました。とても綺麗な薄茶色の瞳でした。」
セヤは、笑顔を寧禰に向けた。寧禰は、セヤが言っている女性が自分だとしばらくして気が付き、あっと声を上げた。セヤは、視線を焚き火へ移し、言葉を続ける。
「はっきり顔が見えたわけではありませんが、その女性の瞳が私の心に深く焼き付いたのです。とても悲しい、でも強い。そう思いました。失礼だとは思いましたが、その方の後を追っていったんです。やがてその方は『語り絵』の前で歩みを止めました。正直、どきどきしました。私の絵をどう思われるかと。その方は、『語り絵』を見上げ、ふわりと花の様な笑みを浮かべたんです。」
寧禰の顔がまた赤く染まる。
「『護りたい。』その時、そう思いました。あんなに強い感情は初めてでした。わかったんです、『私は、この方を護るためにいるんだ。』って。」
寧禰は、ぎゅっと唇を噛んだ。セヤと同じに、小さく揺れる火を見つめながら、グッと手に力を込める。そして、決心したように口を引き結ぶと、短く吐き捨てるように言った。
「私は・・・誰かに護ってもらえるような・・・そんな立派な人間じゃないっ!」
「寧禰?」
セヤが怪訝そうに寧禰の横顔を見つめた。その表情は苦しそうだ。
「私は、いろんな苦しいことに耐えられなくて・・・莉央を理由に逃げ出してきたずるくて情けない人間なの!誰かに・・・セヤ君に護ってもらう価値なんてないんだよっ。」
寧禰の薄茶色の瞳には、薄く涙がにじんでいる。たまらなくなったのか、寧禰は顔を伏せた。セヤは、焚き火を見つめたまま何も言わない。が、しばらくして口を開いたのはセヤだった。
「それでも、私は寧禰を護ります。」
寧禰は驚いて顔を上げた。大きく目を見開き、セヤを凝視した。セヤは、優しい青の瞳で寧禰を見つめ返した。
「寧禰、少なくとも私にとって寧禰は護る価値のある人です。今の私は、『寧禰を護る』ことが生きている理由と言っても過言ではありません。」
「だからっ、そんな風に言わないで!」
寧禰は耳をふさいだ。セヤは、寧禰から視線を外さず続ける。
「昔、祖父に言われたんです。『いつか、護るべき人が現れる。その人を何があっても護れ。決して迷ったり見失ったりしてはいけない』と。その時の祖父の笑顔がとても優しくて悲しくて・・・。この言葉を忘れたことはありませんでした。」
「お祖父様?」
「とても優しい人でした。私は、祖父が大好きでした。私に絵を教えてくれたのも祖父だったんです。」
セヤは一度言葉を切り、消えかけた焚き火に木をくべた。その火を見つめながら、続ける。
「ずっと後になって聞いた話なんですが、祖父は、祖父の『護るべき人』を色々な事情から護ることが叶わなかったんです。割り切ったと本人は言っていたらしいんですが、本当はずっと後悔していたんでしょうね。」
セヤは悲しそうに目を伏せた。そしてゆっくり目を開けると、その青い瞳で真っ直ぐ寧禰を射抜いた。
「私は、祖父のような後悔をしたくありません。いきなりで驚く気持ちは分かります。でも、寧禰が負担に感じることはありません。、私は自分で望んでやっているんですから。ただ、ひとつだけ。寧禰を護りたいという気持ちにも、寧禰を愛しいと思っている気持ちにも偽りはありません。それだけは信じて下さい。」
寧禰は、全身を朱に染めうつむいてしまった。そして、しばらくしてやっと掠れたか細い声で言った。
「でも・・・私はよく分からない。セヤ君のことどう思ってるとか・・・。」
「いいですよ。」
セヤの優しい声が耳をかすめる。
「あせらなくていいんです。私は、これからもずっと寧禰と歩いていくつもりですから。ゆっくり、答えを探してください。」
顔を上げると、セヤの優しい視線とぶつかった。セヤの笑顔に、寧禰はまたうつむいてしまう。セヤは、温かな光を宿した青の瞳で寧禰を見つめる。
優しい夜の空気が二人を包み込んでいた。それは穏やかな、優しい時間であった。
「うん・・・。」
寧禰が静かに呟いたのは、その夜、セヤが眠ってしまってからであった。
「じーさま。」
少年は祖父に問いかけた。
「じーさまは、こうかいしてるの?」
少年の問いに、祖父はゆっくり首を左右に振った。そして立ち止まり、少年の目の高さに視線を合わせる。
「今はしていない。静夜に逢えたからな。」
「ぼくに?」
少年は不思議そうに祖父の青い瞳に問い返した。
「ああ、じーさまは静夜が大好きだ。」
「ほんとう!?ぼくもじーさまが大すき!!」
少年は満面に笑みをたたえ、自分と同じ祖父の青い瞳を見返した。その瞳には、さっきの悲しい光が無く、少年は余計に嬉しくなった。再び歩き出しながら、少年は無邪気に言う。
「ぼくね、かーさまもとーさまもすき!サンジも、ロクタも!えっとね、それから・・・おばあさまもすきだったよ。それから・・・それからね・・・。」
少年の笑顔を見ながら、祖父は願った。この少年の笑顔が永遠に続くことを──── 。
静かな夜。青年は、祖父のことを思い出す。いつも、優しく微笑んでいた祖父の笑顔を。
『静夜』───── この名を付けてくれたのは祖父だったこと、この名が祖父の『護る
べき人』の名だったということを知ったのは、祖父が遠くへ旅立った夜だった。それは、とても静かな夜だった。
END