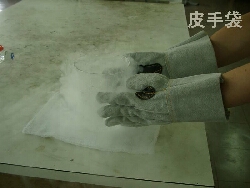| 1) | 液体窒素をビーカーに入れる。 |
| | ☆ | 沸騰している。 |
| | ★ | 沸点より気温が高いから。 |  |
| 2) | 液体窒素を机の上に少しだけこぼす。 |
| | ☆ | 玉になって転がる。 |
| | ★ | 加熱したフライパンに水を入れたのと同じ現象。表面張力で丸くなって、常に蒸発しているので動く。 |
| 3) | ゴム管を液体窒素に入れる。 |
| | ☆ | ゴム管から液体窒素が噴出してくる。 |
| | ★ | 沸騰したやかんの口から湯が噴出すのと
同じ理由。容器中で液体窒素が沸騰して
いるから。 |  |
| 4) | 指を一瞬入れてみる。 |
| | ☆ | 冷たく感じるが、何ともない。 |
| | ★ | 一瞬ならば、指と液体窒素の間に窒素の
気体があるので凍傷にならない。 |
| 5) | 花や葉を入れて取り出しつかんでみる。 |
| | ☆ | バリバリに凍り、つかむとこなごなになる。 |
| | ★ | 水分が凍るから。 |
| 6) | バナナを凍らせ、釘を打ってみる。 |
| | ☆ | 釘が打てる。 |
| | ★ | 水分が凍ってかたくなる。 |
| 7) | 乾いた紙を入れる。 |
| | ☆ | 液体窒素がしみこみ濡れるが凍らない。 |
| | ★ | 水分がないものは凍らない。 |
| 8) | ゴムボールを入れて凍らせ、床に落としてみる。 |
| | ☆ | カチカチになり、落とすとわれる。 |
| | ★ | ゴムの弾性がなくなる。内部が空気なので大きく変形し割れる。 |
| 9) | スーパーボールを入れて取り出し床に落としてみる。 |
| | ☆ | 石のように硬くなりよく跳ね返るがしばらくすると弾まなくなる。常温に戻ると元どおりよく弾む。 |
| | ★ | 中が詰まっているので割れにくい。表面が少し溶けて中が凍ったままでは弾まない。 |
| 10) | 輪ゴムを半分だけ入れて取り出し引っ張ってみる。 |
| | ☆ | いびつに伸びる。 |
| | ★ | ゴムの弾性がなくなり、凍った部分だけ伸びない。 |
| 11) | 膨らませた風船を出し入れしてみる。 |
| | ☆ | しぼんで小さくなり、取り出すと元に戻る。 |
| | ★ | 温度が下がると空気の体積は減る。(シャルルの法則)薄いゴムは割れにくい。 |
| 12) | ふたをした空のペットボトルを入れる。 |
| | ☆ | しばらくしてから急にへこむ。外へ出すと元に戻る。 |
| | ★ | 温度が下がると空気の体積は減る。 |
| 13) | サラダオイルを入れる。 |
| | ☆ | 白くなり固まる。 |
| | ★ | 低温になれば固体になる。 |
| 14) | 試験管に水銀を入れ、液体窒素の中に入れる。 |
| | ☆ | 真中がへこんで固体になる。 |
| | ★ | 低温になれば固体になる。 |
| 15) | 酸素を詰めたポリ袋を入れてみる。できた液体にネオジウム磁石を近づけてみる。 |
| | ☆ | 淡い青色をした液体酸素が出来る。磁石に引き寄せられる。 |
| | ★ | 液体酸素は、液体窒素より沸点が高いので、液体窒素を使って液化できる。酸素は磁性
を持つ。 |
| 16) | 二酸化炭素を詰めたポリ袋を入れてみる。 |  |
| | ☆ | ドライアイスができる。 |
| | ★ | 二酸化炭素は1気圧では液体にならずに
固体になる。 |
| 17) | 液体窒素をしみこませたティッシュをフィ
ルムケースに入れふたを閉める。 |
| | ☆ | 大きな音と共にふたが天井まで飛ぶ。 |
| | ★ | 気体になると体積が約650倍に膨張し、
圧力が大きくなる。 |
| 18) | 液体窒素の中でシャープペンシルの芯に15Vの電圧をかけて電気を流す。 |
| | ☆ | 長い間光っている。 |
| | ★ | 黒鉛は電気をとおすが電気抵抗があるため発熱する。空気中では高温のため燃焼して切れる。液体窒素中でも芯は千数百℃に発熱する。酸素がないので燃え尽きることはない。このとき、液体窒素の沸騰は盛んになる。 |
| 19) | 電池に豆電球を取り付け、点灯させながら電池を液体窒素に入れてみる。 |
| | ☆ | 徐々に暗くなって消える。 |
| | ★ | 温度が下がると化学反応の速さが遅くなり、起電力が小さくなる。 |
| 20) | 電池に5mのエナメル線で作ったコイルと豆電球を直列に取り付けるとかすかに光る。このコイルを冷やしてみる。 |
| | ☆ | 明るくなる。 |
| | ★ | 金属の電気抵抗は低温にすると小さくなる。 |
| 21) | 氷を入れてみる。 |
| | ☆ | 泡が出て沈む。 |
| | ★ | 氷の密度のほうが大きい。 |
| 22) | マシュマロを凍らせ食べてみる。 |
| | ☆ | アイスクリームのような感触。 |
| | ★ | マシュマロは空気を多く含んでいる。空気は熱を伝えにくいから表面だけ凍り内部は凍らない。冷たく甘いのでアイスのような感触がする。 |
| 23) | 凍らせた超伝導物質に、冷やした強力磁石を近づけてみる。 |
| | ☆ | 磁石が浮く。 |
| | ★ | マイスナー効果による。 |
| [留意点・工夫点] |
| ・ | 液体窒素は10リットルあたり \8000前後である。専
用の容器(ジュワービン)が必要である。 |  |
| ・ | 液体窒素の入っている容器は絶対に密閉しない。 |
| ・ | 実験に使う容器は、ビーカーやペットボトルで作った
ものを使うとよい。演示用には、ガラス製のジュワー
ビンを使うと結露が少なくて中が見やすい。 |
| ・ | 取り扱い時、軍手の使用は染み込むと危険なので皮手袋を使用するのがよい。濡れた手で扱わない。また、竹製の大型ピンセットを利用するとよい。 |
| ・ | 液体窒素を入れたガラス容器は発泡スチロールか雑巾の上に置く。 |
| ・ | 液体窒素を取り出す時は、専用のポンプもあるがペットボトルを利用したロートなどを使ってもよい。 |
| ・ | 液体窒素を容器に入れたときは沸騰するが、温度が下がると平衡状態になって泡立たなくなる。 | 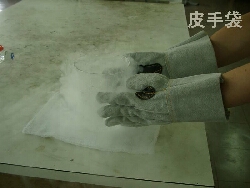 |
| ・ | 容器の外壁につくのは空気中の二酸化炭素と水蒸気が、ドライアイスと氷になったものである。
|
| ・ | 長期間置いてあった液体窒素には酸素が溶け込んでいるので、有機物との接触による発火には
注意する。 |
| ・ | 4は長時間入れると危険である。演示実験が望ましい。 |
| ・ | 8のゴムボールは柔らかいボールがよい。材質の違いで、冷凍時間によっては危険な場合もあるので気をつける。 |
| ・ | 17ではふたが勢いよく飛ぶので気をつける。ふたに長い紐をつけておくと勢いをおさえられ、見失うこともない。ティッシュの量も多すぎないこと。 |
| ・ | 22のマシュマロは中に何も入っていないものを使う。クリームなどが入っていると、食べた時に凍傷をおこすことがある。 |
| ・ | 液体窒素は液体酸素より沸点が低いことを利用して、液体空気から分留される。 |
| ・ | 液体窒素は、食品の瞬間冷凍などに利用されている。 |
| ・ | 超伝導体になるものに、20数種の元素や多数の合金、ある種のセラミックスや有機結晶がある。イットリウム・バリウム・銅の酸化物などからできている。
マイスナー効果:ドイツの物理学者マイスナーによって発見。磁力線はふつう物質の中を通り抜けるが、極低温下でこの物質を超伝導の状態にすると、一点を除き物質中には入り込めなくなる(完全反磁性)。磁力線が通り抜けられる一点で磁石はくぎざし状態になり浮く(ピン止め効果)。 |