7.ボルボックス Volvox

和名 オオヒゲマワリ
- 分類
- 原生動物門 鞭毛虫綱 植物性鞭毛虫類
植物学では緑藻類に分類される。 - 形態・特徴
- 群体の直径は300〜800μ。球形または楕円体の寒天質被膜の内壁に細胞が一層に並び、中は細胞数は500以上20000、各細胞は原形質繊維で連絡され、それぞれ2本の鞭毛をもつ。雄性無性両方の生殖を行い、よく母体内に無性生殖で生じた新個体を含んでいる。
春から秋にかけて池沼、水田などに出現する。
- )培養法





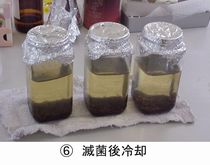




- )その他の実践例
- ハイポネックスを使用した培養液
水道水(滅菌する) 100
ハイポネックス(10倍希釈) 1
土壌浸出液(土壌100g+500ml) 1 - 「六甲のおいしい水」または「ヴォルビック」を培養液にする。1週間くらいで継培養する。
- ハイポネックスを使用した培養液
8.ミジンコ Daphnia Pulex

- 分類
- 節足動物門 甲殻綱 枝角目 ミジンコ科
- 形態・特徴
- プランクトン動物のうち最も重要な種類を多く含んでいる。
体は広卵円形の2枚の殻で包まれ、背面で合一し、腹面で開く。殻の腹縁後半部には小さいとげが列生している。頭部はまるく、左右の複眼が合一して一つになっている。触角の運動によって水中を泳ぎ、胸部にある4〜6対の葉状肢で水流によって運ばれてくる餌を食べる。
ミジンコは水槽、ビーカー、空き瓶等に畑の土や腐葉土を入れ水を加えた容器で培養し、餌はドライイーストを使用する。テトラミンなどの魚の餌も使用できる。
9.ヒドラ Hydra
- 分類
- 腔腸動物門 ヒドロ虫綱 ヒドラ科
- 形態・特徴
- 池、沼、水田、溝などの水中に沈んだ落ち葉や枯れ枝などに付着して生活している。体は円筒形で伸張したときには10mmほどになる。先端にある口の周囲に触手が5〜7本あり、体長の1.5〜2.5倍に伸びる。体の色は淡褐色であるが、体の状態とか食物の色などで異なり、体内に単細胞緑藻が共生したものは緑色になっている。触手の外皮細胞中には4種の刺胞があって、それぞれ刺糸が射出して餌を捕まえる。刺糸は種類を決めるのに大切な特徴になっている。ヒドラは購入したカナダモに付着していることも多い。餌としてミジンコを与える。ただし、好まない種類もある。(ケンミジンコ、カイミジンコ)ミジンコ類が繁殖している水槽の中であれば、特に餌を与えなくても自然に培養できる。また、魚の餌として売られているアルテミアを与えてもよい。
10.プラナリア Planaria
- 分類
- 扁形動物門 渦虫綱 三岐腸目 プラナリア科
- 形態・特徴
- 日本に産するプラナリア科には数属含まれ、すべて淡水産で、河川や池沼の水底および水生植物や石の上などをはっている。再生力が強いため、再生の実験に使用される。
培養には腰高シャーレなどを使用する。餌はレバーを冷凍保存して与える(週に1〜2度)。牛レバーを使用すると水が汚れにくい。
飼育温度は15〜20℃。汲み置きの水を使用し、餌をやった後、または1カ月に一度は水を替える。