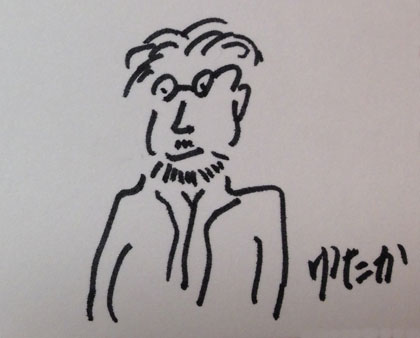 |
兵庫県立歴史博物館 館長 藪田 貫 |
- 【ご挨拶】
- 平成26(2014)年4月1日、端信行前館長の後任として第4代館長に就任しました。
- 大阪に生まれ、大阪大学大学院で修士課程を終え、大阪大学助手・京都橘女子大学助教授を経て、1990年から2015年まで関西大学文学部教授を勤めるーというのが略歴です。専門は歴史学で、おもに日本の江戸時代、「近世」と呼び慣わされている時代の「社会と人」について研究してきました。好きな言葉は、「楽しみを以て憂いを忘れる」。
- 博物館・美術館巡りは趣味で、町歩きの途中、フラッと博物館・美術館に立ち寄るのは大好きです。しかし博物館長になってからは、高齢者から幼児まで、さらに海外から、またさまざまな障がいのある人など、じつに多様な人々が来館されることに一番大きな衝撃を受けました。
- また開館以来36年目を迎え、学芸員の世代交代期を迎えているタイミングで館長に就任したので、若い学芸員諸君が、「ここが自分の居場所」だと思い、将来の夢を託せる博物館になってほしいと願っています。
- 四季折々の姫路城を見ながら仕事ができるのは最高の環境です。
- 「館長室へようこそ」は就任以来、館長ブログとして、書き綴っています。毎月15日頃に更新することとなっております。
- なお挨拶は、館長職6年目に入るのを契機として改訂しました。また写真に変えて自画像を添えました。遊び心とお許しください。
- 「歴史ステーション」にお越しになった時、気楽に立ち寄ってお読み下さい。
- みなさんの感想、お便りなども、お待ちしています。
- あて先 : Rekishihakubutsu@pref.hyogo.lg.jp
|
「淡路へ三度」〜春の海〜 2020年2月15日 |
「伊勢へ七度、熊野へ三度、愛宕山には月参り」という文句があったかと思いますが、『広辞苑』には「信心の深さ」を言うと解説しています。それに倣って「淡路へ三度」と言い換えてみたのですが、それは淡路島へ三度、行ったという意味です。明石海峡大橋が架かって、淡路はもはや「島ではない」といえる位に、車で容易にアクセスできる「島」ですが、やはり海は魅力的です。そんな淡路の海を、しかも春の海を平成30年、31年、令和2年と、三度にわたって見ることができたのです。
2月初めの週末に連続して淡路島に行く機会があるのは、博物館内に併設されている「ひょうご歴史研究室」が、淡路島日本遺産委員会と共催で毎年、講演会を開催しているからです。この連続講演会ですが、洲本市・淡路市・南あわじ市の三市と県の淡路県民局、さらに淡路島くにうみ協会・淡路島観光協会・淡路青年会議所らが官民一体となって提案した「国生みの島・淡路〜古代国家を支えた海人の営み〜」が平成28年、文化庁の日本遺産事業に選定されたことに端を発します。事業は28年度からスタートしましたが、翌29年度に海人の調査事業を進めることとなり「ひょうご歴史研究室」が協力、30年2月の講演会に至ったのです。
平成30年2月の会場は淡路市、31年は南あわじ市、令和2年は洲本市と移っていますが、講演会は毎回、200名を超える聴衆で賑わっています。
研究室長としてのわたしの役割は、講演会とその後の討論を見届け、閉会の挨拶をするというものですが、研究室のメンバーにとって誰しも淡路島はやはり特別な場所なのか、講演会の終了後、現地に宿泊し、翌日、現地視察をしようという計画が持ち上がりました。現地に詳しい文化財関係者の案内が付く、という贅沢な視察です。
その最初は31年2月の南あわじ市福良での講演会翌日、憧れの沼島(ぬしま)に行きました。淡路島から右に一つ飛び出した島で、ハモの産地としても有名な沼島には南あわじ市の土生(はぶ)港からフェリーで約20分。島内は歩いて回れますが、西側の入り江に対し、東側の岩場には圧倒されました。中央構造線が作り出す峩々たる景観の向こうに、大阪湾が広がっているのです。
|
そして今年は、いま一つの憧れの地、洲本市由良(ゆら)。南北に長い淡路島の右脇腹に窪んだような地形を見せるのが由良地区で、港から渡船で約5分。要塞跡が残る成山の頂上から見える細長い砂洲成ケ島(なるがしま)に囲まれた内海の素晴らしい景観。東の海上には友ケ島(大阪府)が位置しています。この海原が紀淡海峡です。
|
好天のお蔭で、春の海の絶景を堪能した次第ですが、昨年の7月には調査の途次、夏の海で絶景に出会いました。それは、南あわじ市阿那賀(あなが)の伊毘(いび)港に立ち寄った時です。小さな港の岸壁の先に、小さな沖ノ島が見え、その視線の先にはなんと鳴門大橋が見えるではありませんか。予想だにしなかった鳴門大橋との出会いですが、その下は鳴門海峡です。
|
鳴門海峡・紀淡海峡、そして明石海峡が生み出す絶景に恵まれた淡路島は、間違いなく島です。素晴らしい島です。ぜひ行ってください。
なお、掲載した写真は、同行されたひょうご歴史研究室坂江渉研究コーディネーターの撮影によるものです。記して謝意を表します。






