

三原高校郷土部は1952年に創立されて以来、淡路島で400年以上の伝統をもつ郷土の伝統芸能、淡路人形浄瑠璃の保存と普及に努めてきました。戦後淡路人形の伝統は絶滅の危機に瀕しましたが、郷土部は伝統を守るため幾多の困難を克服してきました。郷土部の公演活動は広範囲にわたっています。全国高等学校総合文化祭や日本各地での公演活動などがそれです。1993年には郷土部は埼玉県で開催された第17回全国高校総合文化祭郷土芸能部門で優秀賞を受賞しました。その結果、名誉なことに国立劇場で公演することができました。郷土部の部員の中には淡路人形座のアメリカ、ドイツやスペインなどの海外公演に同行し、公演したものもいます。
淡路人形浄瑠璃は人形操作と浄瑠璃、三味線の三業より構成されます。各々は習熟するのに長い年月を必要とします。

淡路人形は等身大の半分です。人形の目は動き, 眉毛は驚いて上がり、口は開いたり、閉じたりし、手と腕は写実的に動きます。主な人形は3人の人形遣いにより操作されます。人形遣いは人形を舞台で操作し、公演の間、姿を見せています。
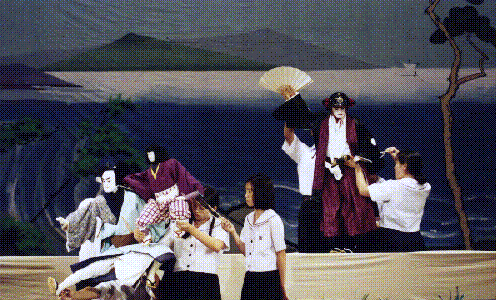
主遣いは左手で首のしん串を握り、人形の背中から人形を支え、人形遣いの右手で人形の右手を操ります。女の人形は概して足がないので、着物の裾をさばいて歩いているように見せます。

太夫は人形が演じる物語を語ったり、歌ったり、叫んだり、ささやいたり、涙とともに
劇中の登場人物の会話を語ったりします。太夫は三味線伴奏者と並んですわります。
太夫の語り(0.2MB)

三味線伴奏者は人形芝居で重要な役割を演じます。三味線は浄瑠璃の語りの伴奏だけではなく、場面に応じて雰囲気を盛り上げるために雨や風やその他の効果を作り出します。
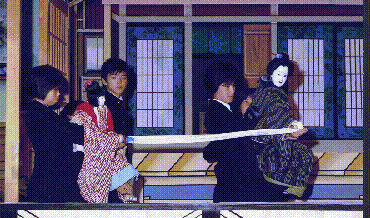
私たちはこの劇をよく演じます。
この物語は1768年に大阪の竹本座で初演されました。阿波(徳島県)からやってきた浪人、十郎兵衛は盗まれた名刀を探すなか、銀十郎という偽名で彼の妻お弓と無法者としての生活を強いられます。場面は大阪の彼らの住居で開始します。この家へ偶然に,阿波で置き去りにした娘のお鶴がやってきます。お弓はお鶴と話す中で実のわが子であることを知りますが、お鶴は気がつきません。お弓はお鶴を災難に巻き込むことを恐れて、実の母親であることを明かさずに、お鶴に阿波へ帰るように言います。後でお弓はお鶴と一緒に住むことを決心しますが、お鶴は阿波へ帰る途中で実のわが子と知らない父親の十郎兵衛によって殺され、お金を奪われます。この物語にはそのような悲しい結末が待ち構えています。
