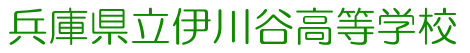

平成30年度第二学期終業式 式辞
二学期の最終日にあたり、一言あいさつを述べさせていただきます。
さて、皆さん、どんな二学期だったでしょうか?
9月3日の始業式では、「秋は、これまで取り組んできたこと、努力してきたことが実を結び、結果となって現れてくる季節」、そして「3年生、2年生、1年生、それぞれに、長い人生において、重要な季節」というお話をしました。
どんな実を結ぶことができましたか。長い人生において、意義深い時間を過ごすことができましたか。
これから、平成最後の年末・年始を迎えます。いつもより、少し休みが長く、自由な時間ができると思います。この機会に、自分自身をしっかりと見つめ、自身と深く対話してください。そして、私たちが、幸運にもいただくことができた、神秘に包まれた、崇高な、先祖から連綿と続く「命」、この最も大切な「命」・「使える時間」を過ごす中で、「私たちは、一体何をしていかなければならないのか」ということに、一度思いを寄せ、考えてみてください。
そんなとき、人生を歩む中で、道案内をしてくれたり、ヒントをくれたりするのが、「書物」、「本」です。はるかな時を越え、遠く国を越え、私たちに様々な示唆を与えてくれます。
皆さんが、毎朝、静寂に包まれる中、取り組んでいる「朝読」、これは実に素晴らしい取組です。平成22年4月から続いており、今では、本校教育活動の大きな柱になっています。先日、梶村先生が、今年の「私が感動した30冊」の冊子を届けてくださいました。これも平成24年度から継続されています。
私たちは、毎日、欠かさず食事をとらなければ生きていけないように、実は、「心」にもしっかりと「栄養」を与えなければなりません。それが、「読書」です。どうか、この素晴らしい読書習慣を生涯継続してください。
先ほどの、「私たちは、一体何をしていかなければならないのか」「何のために生きるのか」「どう生きるべきなのか」ということについてのヒントも、はるか昔、紀元前に書かれた、中国の古典の中に見ることができます。
皆さんも、聞いたことがあると思います、「四書五経(ししょ ごきょう)」。
四書とは「論語(ろんご)」「大学(だいがく)」「中庸(ちゅうよう)」「孟子(もうし)」の4つ、五経は「易経(えききょう)」「書経(しょきょう)」「詩経(しきょう)」「礼記(らいき)」「春秋(しゅんじゅう)」の5つのことです。
この「大学」という書物は、古代、人を教育する時の規範を示したもので、そこに、次のように書かれています。
古(いにしえ)の明徳(めいとく)を天下に明らかにせんと欲する者は、まずその国を治む。
その国を治めんと欲する者は、まずその家をととのう。
その家をととのえんと欲する者は、まずその身を修む。
この意味ですが、
昔むかし、自らの徳で人民の考え方や行動に影響を与え、天下を平和に治めようとする者は、まず、その国をしっかりと治めなければならない。
自ら、国をしっかりと治めようとする者は、まず自分自身の家や家庭の中を整えることが重要である。
自分自身の家や家庭の中を整えようとする者は、まず、自分自身の心を磨き、身なりを整え、徳のある行動をとらなくてはならない。
ということです。
天下太平をもたらし、国を治めるという壮大なことも、まず行わなければならない大切なこと、その本(もと)は、自らの身を修めること、「修身」、自分という人間を高め、仕上げ、心や行動が乱れないように整えること、これこそが、「原点」であると述べられています。
また、時代を大きく飛び越え・・・20世紀における最重要人物の一人と言われる経済学者の代表的存在である、イギリスのジョン・メイナード・ケインズは・・・不況の時には、政府が公共投資を増やし景気の落ち込みを防ぐことを提唱したケインズ経済学で有名なケインズですが、その最後の著書「わが若き日の信念」で、
It is much more important how to be good rather than how to do good
「いかに善を為すかというよりも、より重要なのは、いかに自らが善き人であるかということである」と書かれています。
これらを見ると、時代を越えても、アジア、ヨーロッパと洋の東西に関わらず、大切なことは同じ・・・まず、「自らをしっかり創り上げること」「自らを高めること」であることを教えられます。
では、「自らを修める」「自らを高める」には、どうすればよいのか。
特別なことではありません。
これは、日々、いただいた「命」に感謝しながら、規則正しい生活を継続する中で、今日という一日、できることを誠実に取り組む。これこそが、唯一の道なのです。
感謝の気持ちを忘れ、不規則な生活を繰り返し、今日という一日を充実させず無駄にする中で、自らを修める、自らを高めることは決してできないのです。
これを、皆さんに、「一人一人が、孤独に一人っきりで頑張れ」ということではありません。
「チーム伊川谷」ということを言い続けてきました。
「利他(りた)の心」というのを聞いたことはありますか。利他・・・利は利益の利、他は他人の他です。その逆は、「利己(りこ)」です。利は利益の利、己はおのれ、自分自身です。よく耳にする「利己主義」、これは、自分の利益のみを考え優先し、他人の利益を軽視、無視することです。
「利他の心」とは、自分以外の他人の利益を重んじ、他人の幸せを願い力を尽くす、ということなのです。
考えてみてください。私たちが、本当に幸せな気持ちになるのは・・・実は、他の人が、自分の行ったこと、言ったことが影響し、その人が心から喜んでくれ、幸せな状態になったことを知った時ではないでしょうか。
人間の心は、本来、そのようにできているのです。人を憎み、落とし入れようとして、真の幸せは決して手に入れられないのです。
他人の幸せを願い、他人の力になろうとすることが、回り回って、自らを幸せにしてくれているのです。
「チーム伊川谷」とは、本校の生徒のみんなが、お互いに、友の幸せを願い、協力しあい、その結果、皆が幸せになるという集団なのです。
まずは、明日から17日間の冬休み、目の前の取り組まなければならないことを、規則正しい生活をする中で、こつこつと取り組んでいってください。そして、家族、友人など、いつも支えてくれている人への感謝を思いながら、平成最後のお正月、2019年を迎えてください。
では、1月8日に、元気な皆さんと、ここで再会できることを楽しみにして、以上、平成30年度第二学期終業式の「式辞」とします。
平成30年12月21日
兵庫県立伊川谷高等学校校長 川 崎 芳 徳