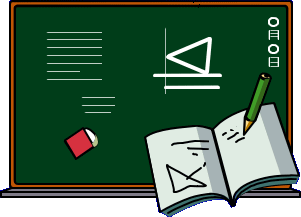 ICTを活用した授業を行う上でのポイントを紹介します。
ICTを活用した授業を行う上でのポイントを紹介します。パソコンやプロジェクタ等のICT機器を授業に取り入れることで、授業での児童生徒の理解が深まったり、興味・関心が高まる等、教育効果があがることが報告されています。
しかし、ICTを使いさえすれば「よい授業」や「わかりやすい授業」ができるというものではありません。
これまで同様、授業の目標を明確にし、授業を組み立てていく中で、ICTを授業のどの場面でどのように使えばいいのかを考えることが大切です。
授業でICTを活用する目的は、ICTを使うことではなく、あくまで学習指導要領に示されている教科等の目標を達成することです。
ICTを使えば、言葉や黒板での説明だけでは教えにくいもの(児童生徒が理解しにくいもの)を、映像等でイメージ化させたり、写真や映像を拡大して比較したりすることで、児童・生徒の理解を助けることができます。
また、ICTを活用することで、以下のような効果があります。
(1)児童生徒の興味・関心を高める
これから学習する内容のイメージを持たせるように教科書の図や動画を見せる。
(2)児童生徒に課題を明確につかませる
これから学習する課題を明確につかませるために、教科書の設問や図表等を拡大する。
(3)児童生徒の思考や理解を深める
グラフ等の変化をわかりやすく説明するためにシミュレーションソフト等を使ったり、実際にできない理科の実験等を映像で
見せる。
(4)児童生徒の知識の定着を図る
フラッシュ型教材等を使った繰り返し学習。
各教科ごとに、授業での有効な活用イメージを考え、ICTを授業に取り入れて下さい。
「導入」、「展開」、「まとめ」のいずれの場面でもICTを活用することができますが、例えば50分の授業の中の5分間程度にICTを活用する等、授業のワンポイントで活用すると効果的です。
ICTを使うからといって、授業のすべての時間でICTを活用する必要はありません。
かえって授業の本来のねらいがわからなくなったり、児童・生徒が飽きてしまったりすることもあります。
これまでの黒板を中心とした授業にICTを組み合わせた「ハイブリッド型授業」を考えて見て下さい。
