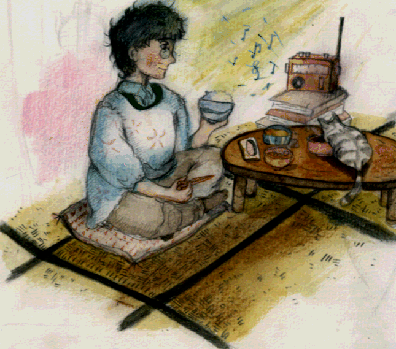
初雪の日の話
一、
日に日に寒くなって行く十二月、私が蒲団から這い出ると、井尾田氏はもう起きていた。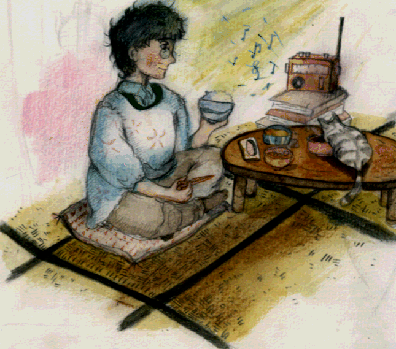
北風が、この古いアパートの窓を叩いている、小さな二階建ての、「ひなげし荘」、
二〇五号室が私達の部屋であった。
朝日が小さな台所に差し込み、味噌汁を作る井尾田氏は、ふと手を止めた。
私は石油ストーブの横を通り、ちゃぶ台の下を潜り、彼の横に座った。
彼は大根を刻む手を止めて、まだ何か考えている。
こういった時の彼は、いつだって遠い世界にいる様なものなのだ。
『やぁ、おはようガンマ、いたんだね。』
やっと、私に気がついた。もう、お気付きかもしれないが、私は猫なのである。
主人の井尾田氏にはガンマと呼ばれている。この奇妙な名前は、私の尻尾の具合が、
数学のガンマ記号に似ている事に、由来しているのだ。私は、頑固な雄のトラ猫であるが、
この、少し風変わりな主人に、この名前で呼ばれるのが好きである。
『ああ、ガンマ・・・。残念ながら、また新しい詩の発想は浮かびそうに無いなぁ。
申しわけないけど、お前にはもうしばらく、猫マンマで我慢してもらうしかないよ。』
井尾田氏は、すまなそうに呟いて、湯気で曇った眼鏡を拭きながら、古いラジオのスイッチを
ひねった。ニ、三度後ろを叩くと、雑音の中からバロックが、流れ始めた。
『さ、朝食としましょうか。』
白いかっぽうぎを、外して、えんじ色の千鳥格子の座布団に腰を下ろした。もう今年で三十三才
のくせに、未だに、かっぽうぎのよく似合う人だ。
『やっぱり、カブラは自分で漬込むのが一番だ。今年の糠床は正解だったなぁ…。』
カリリと軽快な音をたてて漬物をかじっている。私も一度食べたことがあるが、あんな物臭くて
かなわない。
井尾田氏は、なんでも美味しそうに食べる。箸の持ち方、使い方も、とても優雅に見えた。
魚の食べ方だって、こっちが習おうと思う程にきれいであった。
冬の澄んだ朝日が、少し薄暗くゴチャゴチャとした部屋の中に差して行き、壁に貼られた広重の
版画や、竹久夢二のポスターが、不思議に物悲しかった。積み重ねられた本、無造作に生けられた山茶花、
ガラス戸棚の中の、張子の虎、しわくちゃの毛布までもが、静かな朝の空気の中に沈み、あたかも密やかに
呼吸しているかの様である。
捨て猫であった私にとって、井尾田氏と暮らす、この狭い一部屋に、もう遥か遠くへ行ってしまった母の、
温もりを見出すことがある。
冷めていく朝食の猫マンマを見つめながら、私は随分とセンチメンタルな猫となっていた。